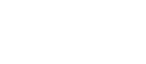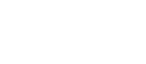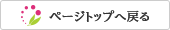ページの本文です。
佐々木幸子
2024年5月31日更新
フランスのオンライン継承日本語クラスにおけるランゲージングの様相 −プロセスと言語レパートリーの認識・活用に着目して−
| 修了年度 | 2023度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | フランスのオンライン継承日本語クラスにおけるランゲージングの様相 −プロセスと言語レパートリーの認識・活用に着目して− |
| 要旨 (1000字以内) |
グローバル化がますます進む近年の世界情勢により地球規模で盛んに人口移動が起こっていることに伴い、幼少期から複言語環境で成長する多くの子どもたちが、彼らの親や祖父母が母語とする言語を「継承語」として学んでいる。近年の継承日本語教育分野においては、親から子へと受け継ぐ「絆」としての言語ということから、様々な言語資源を持つ個人の「ことば」のレパートリーの構成要素の一つであると捉える潮流があり、継承語教育観・学習観のパラダイムシフトが起こっていると考える。 こうした潮流に沿う言語行動の概念として、社会文化的アプローチを基盤としたランゲージングがある。ランゲージングとは、Swain(2006, 2010)が提唱した「言語を通して意味を作り、知識や経験を形成するプロセス」であり、Vygotskyの認知理論を基盤としている。ランゲージングは第二言語習得研究分野を中心に研究が行われており、対象者の使用言語をL1(母語)/L2(第二言語)に分別し、主にL2の言語能力向上を目的として行われた研究が多い。しかし、近年の世界のグローバル化に対応する言語教育を行うためには、言語レパートリー、言語資源の観点からその様相を検討することでランゲージングの研究範囲を拡大する必要がある。本研究ではフランスの継承日本語クラスと参加児童と教師を対象とし、ランゲージングによる知識の再構築や認知の変容のプロセスを明らかにすることと、ランゲージング中の言語資源、言語レパートリーへの認識とその活用の仕方を検討した。研究方法はSacks, Schegloff, Jeffersonらによって開発された会話分析(conversation analysis)の方法論を用い、オンライン授業8回(×2クラス)を録画、文字化した上で、トランスクリプトの作成、分析を行なった。 結果、ランゲージング主体と、教室の場に居合わせる参与者達は、会話達成上のストラテジーを用いながらランゲージングの達成に必要な役割を担っていた。さらに,マルチリンガルである参加児童たちは,継承日本語クラスという場のランゲージングにおいて,「『日本語』を用いるべきである」「『フランス語』を用いるべきではない」という規範意識を持っていることが示唆された。同時に,自身を理想的な日本語話者とみなすことができないというモノリンガルバイアスの存在も示された。また、参与者達は、協調的に対話を構築することで「場」のレパートリーを生み出し,協働的にランゲージングを構築していったことが示された。 |