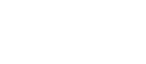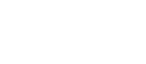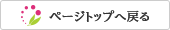ページの本文です。
薛蕙青
2024年5月24日更新
アカデミックな討論における不一致応答の類型及び単位方略 ー日中接触・中国語母語場面に着目してー
| 修了年度 | 2023度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | アカデミックな討論における不一致応答の類型及び単位方略―日中接触・中国語母語場面に着目して― |
| 要旨 (1000字以内) |
グローバル化が進む現在、異文化接触はますます増加し、異なる言語・文化的背景を持つ人々同士のコミュニケーションの問題が注目され、アカデミックなトピックをする場面では、異なる意見を率直に述べる必要があり、一般的な会話場面とは異なる言語の運用能力が求められる。 中国人日本語学習者(CJL)は接触場面での不一致に対応する時、慎重すぎて見解を言いそびれたり、逆に、直接的な表現や自己主張が強く、怖い印象を与えたり(梶原2003)といった、コミュニケーション上の問題が指摘されている。本研究はアカデミックな話題をする討論において、接触場面と中国語母語場面両方を取り上げ、発話での不一致応答の類型及び調整方略を明らかにすることを目的とする。 本研究の研究課題は、アカデミックな話題をする討論を前提に、RQ1:接触場面において、日本人母語話者(JNS)とCJLの不一致応答はどのように異なるか。RQ2:母語場面と接触場面において、CJLの不一致応答は異なるか。RQ3:母語場面において、CJLとCNSの不一致応答は異なるか。という3つである。 本研究の研究方法は、2名の調査協力者による35分程度の会話を1組として、日中接触場面と中国語母語場面では各8組が収録できた。発話データを文字化し、不一致応答に関するスクリプトを抽出し、3つの不一致の類型に従い分類する。各類型の中で、どのような単位方略を使ったのかを更に分類しカウントする。研究課題ごとに各単位方略の使用回数と比率を統計し、カイ二乗検定で分析する。 本研究の結果は次の通りである。まず、CJLとJNSの対比は日常場面と類似しており、CJLはより直接的、JNSはより間接的な単位方略を多用していた。また、アカデミックな話題を討論する場合、日常場面に比べ、CJL、JNSともに、否定型や指摘型のような直接的な単位方略を多用していた。さらに、CJLは接触場面において、より言語使用に配慮していた。事実情報や意図解釈では顕著な影響が見られなかったが、個人判断ではより間接的であった。最後に、個人判断の不一致に対しCNSはCJLより直接的な単位方略の使用比率がやや高かったが、全体的にCJLとCNSの間には顕著な差はなく、母語環境では日本語学習の影響は少なかった。 しかし、本研究から収集したデータが限られていたため、結果としてRQ2とRQ3には全体的に顕著な差異が見らなかった。従って、今後はデータを増やしより詳しい考察を行うことが期待される。 |