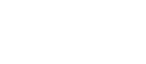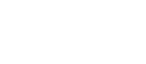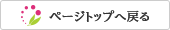ページの本文です。
周超珂
2024年5月24日更新
中国人日本語学習者におけるオノマトペの意味推測―推測の正確さと手がかりの使用に着目して―
| 修了年度 | 2023度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | 中国人日本語学習者におけるオノマトペの意味推測―推測の正確さと手がかりの使用に着目して― |
| 要旨 (1000字以内) |
本研究は中国人日本語学習者(CJL)に対して、オノマトペの未知語義の推測調査を行った。どの程度正しく推測できるか、どのような手がかりが使用されるか、習熟度と既知語義の有無によって推測の正確さ及び手がかりの使用が異なるかを研究課題として設定した。対象語は三上(2007)が選出したABAB型のオノマトペから、事前調査で既知語義が共通している語(既知語義有)4語と未知の語(既知語義無)15語、計19語を選出した。語彙手がかりの使用を考察するため、三上(2007)の作成した例文をもとに、「食べ過ぎて胃がむかむかする」のような文脈量が限定されている調査文を作成した。対象者は27人であり、SPOT90で上位群と下位群に分け、調査は口頭質問応答のインタビュー方式で行った。文字化したデータをもとに、推測の正確さは3人の採点者が評点し、使用した手がかりは先行研究をもとに8種に分類した。 その結果、既知語義有・無の正答率はそれぞれ31.3%と45.48%であり、手がかりの使用は「文の意味」と「世界知識」が最もよく使用される傾向が見られた。また、習熟度と既知語義の有無が推測の正確さに与えた影響を2要因分散分析で確認し、2つの要因とその交互作用が全て有意であった。続いて単純主効果の検定を行い、結果、既知語義有において習熟度(上>下)、下位群において既知語義(有<無)の単純主効果が有意であった。その原因を手がかり使用の傾向から質的に分析した。既知語義有では、上位群が「既知語義」手がかりを多く有効に使用した一方、下位群があまり使用せず、使用した際の有効性も高くなかった。既知語義無では、習熟度に影響されない言語外手がかり「世界知識」にアクセスしやすいことは、習熟度の影響が見られず、そして既知語義有と比べ正確さが高かった主な原因となっている。さらに、「音象徴」手がかりの使用が全体的に少ないことは既知語義無で習熟度の影響が見られなかったもう1つの原因だと分析した。 つまり、CJLはオノマトペの未知語義を推測する際に、語彙手がかりをあまり使用せず、主に「文の意味」や「世界知識」に頼って推測を行った。これはCJLがオノマトペの音象徴を十分に理解できていなかったため、音象徴でつながっているスキーマを充分に把握できなかったからである。この傾向は特に既知語義との意味的関連性が低い未知語義の推測において顕著であり、習熟度が上がるにつれて改善していくように見受けられたが、上級になっても依然として存在し、日本語の音象徴への感覚が十分に育まれていないと言えよう。 |