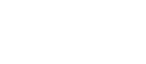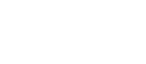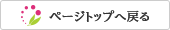ページの本文です。
曾雨
2024年5月24日更新
中国人日本語学習者の日中同形語処理: 学習環境と語彙使用頻度に注目して
| 修了年度 | 2023度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | 中国人日本語学習者の日中同形語処理: 学習環境と語彙使用頻度に注目して |
| 要旨 (1000字以内) |
日中両言語で同じ漢字で表記するという同形語がある。同形語の書字的類似性により、中国人日本語学習者(Chinese Japanese Learner;以下、CJL)の持つ漢字知識が活性化しやすく、それにより意味理解が促進されるとされている。しかし、日本語と中国語では漢字の発音がかなり異なるため、同形語の音韻への処理や、同形語が聴覚的に呈示される場合、CJLの持っている漢字知識が活性化しにくくなり、正確的な判断が難しい。本研究の目的は、CJLが聴覚呈示された同形語を形態情報に転換できるかを明らかにすることである。また、JSL(Japanese as Second Language;日本国内で日本語を第二言語とする)とJFL(Japanese as Foreign Language;海外で日本語を外国語とする)という学習環境と語彙使用頻度という2つの要因が、その処理に影響を及ぼすかどうかを検証する。研究目的の上で、以下の研究課題を挙げる。 RQ1. CJLは聴覚呈示された同形語を形態情報へ転換できるか。 RQ2. 音韻情報から形態情報への処理に、学習環境と語彙使用頻度は影響するか。 SQ2-1. JSL学習者はJFL学習者より、正しく形態情報へ転換できるか。 SQ2-2. 使用頻度の高い語は低い語より、正しく形態情報へ転換できるか。 上記の研究課題を解明するために、初中級レベルの日本語能力を有する、JSL学習者27名とJFL学習者30名を対象として、書き取りテストを実施した。対象語は、旧日本語能力試験3〜4級語22語で、高使用頻度と低使用頻度各11語である。対象語を含めた文の音声を流し、空欄に聞いた語を漢字で書いてもらった。刺激文は、1つの語に1文を作り、合計22文である。 結果として、書き取りテストの平均正答率は80.8%である。この結果から、既習の同形語が聴覚呈示された場合、CJLはだいたい形態情報へ処理できることがわかった。しかし、個人差が大きい。また、学習環境2(JSL・JFL)×使用頻度2(高頻度・低頻度)の二元配置の分散分析を行った結果、学習環境の主効果が有意でなく、使用頻度の主効果が有意であった。このことから、JSL学習者はJFL学習者より、正しく形態情報へ転換できると言えない。一方、語彙使用頻度効果が見られ、使用頻度の高い語は低い語より、正しく形態情報へ転換できるということがわかった。 今後の課題として、より長い滞在期間を持つJSL学習者、または自然環境のJSL学習者を対象として、学習者の実際の日本語接触量や接触方法を詳しく調査する必要がある。さらに、異なる難易度・種類の同形語を調査することが必要である。 |