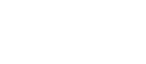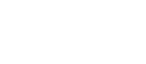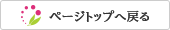ページの本文です。
OSHIRO SHIKINA CYNTHIA NATSUMI
2024年5月21日更新
ペルー日本語教育における間文化的シティズンシップ教育の実践
| 修了年度 | 2023度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | ペルー日本語教育における間文化的シティズンシップ教育の実践 |
| 要旨 (1000字以内) |
近年、グローバル化が進む中、言語的・文化的背景が異なる者同士が日常的にコミュニケーションをする機会が増えている。こういう現状の中で、さまざまなことばの存在を認め、多様な背景を持つ人々との平和的な共存の実現が課題となっている。ペルーは、文化的、民族的、言語的に多様な国であるが、歴史的な理由で、様々なアイデンティティを均質化、不可視化し、多くの文化的対立が存在する。この対立を解決するために、外国語教育の目的でもある、異文化理解教育が必要である。 Byram (2008)は、「外国語」を学ぶことにより、自分の言語や自身のアイデンティティを相対化し、異なる他者の文化やアイデンティティへの理解を深めることができるとし、言語教育を通した文化を超えたシティズンシップ教育の重要性について述べている。 しかし、ペルーの日本語教育は従来の言語形態の指導のみに留まっており、このようなシティズンシップ教育としての側面は見出しにくい。本研究では、このような背景から、ペルーの文脈で、間文化的シティズンシップ教育としての日本語教育の可能性を模索することを目的とした。そのため、ペルー人日本語学習者と日本人スペイン学習者を対象に3週間のオンライン交流を企画した。交流では、まず、各学習者はトピックである「自国の外国人労働者が抱える問題」の新聞記事を探し、学習言語に翻訳し、その後、相手の国の学習者が添削してもらった。3週目に、日本語とスペイン語で、トピックやある仮想状況について話し合った。この週の授業の発話をBarnett (1977)の尺度の「クリティカルな存在」をもとに分析した結果、3つの領域である「知識」、「自己」、「世界」で、様々なクリティカルな能力が形成されたことが確認された。また、シティズンシップ教育が形成された要因としては、学習者は自国の新聞記事の翻訳課題や添削課題の実行や、3週目の交流の中にも、アイスブレーキングやディスカッションに参加したため様々なクリティカルな能力が形成されたとわかった。 結果、間文化的シティズンシップ教育としての外国語教育がペルーを文脈とした場合にも十分有効であることが確認された。これは、研究目的に合わせ、参加者に応じた交流を計画したことや、参加者が責任を持って参加したためだと考えられる。ただし、「世界」の面ではレベル4には達しておらず、今後、実践の中で行動的側面を育成する授業を補完して行く必要がある。 |