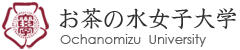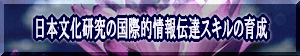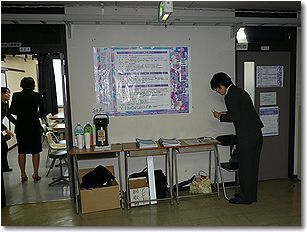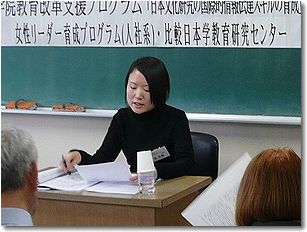12月17日(水)9時30分より、日本思想部会が、文教育学部1号館8階803号室にて開催された。コンソーシアムの部会として日本思想が参加したのは今回がはじめてになる。参加者は、本学学生、教員、海外の招待校の学生、教員、それに他大学の学生、教員(筑波大学、東京大学、岡山大学)など40名ほどでであった。司会は、本学大学院生の斎藤真希さんがつとめた。 発表のテーマ等について、以下、発表順にあげる。 【第1部】共通テーマ 「食・もてなし・家族」 ①「仏教における「食」」(頼住光子・本学) ②「神道における「食」」(高島元洋先生・本学) ③「日本文化論の中の「家族」」(張彦麗先生・北京日本学研究センター) 【第2部】大学院生自由課題発表 ④「神と妖怪―柳田國男『妖怪談義』の中で語られるお化け―」(大内山祥子さん・本学大学院生) ⑤「『日本霊異記』についての一考察」(尾崎円郁さん・本学大学院生) ⑥“On the medical paradigm Stoics and Buddhists A comparative approach” (ローレンティ・アンドレィさん・ブレーズ・パスカル大学大学院生、本学大学院留学生) ⑦「幕末期における武士階級の倫理思想-幕末の社会情勢との関連を中心に-」 (李 斌瑛さん・北京日本学研究センター大学院生) *使用言語は①~⑤と⑦が日本語、⑥が英語である。 今回は、コンソーシアム全体の共通テーマとして「食・もてなし・家族」が設定され、各分科会でもなるべくこのテーマにそって発表を計画するようにという要請があった。それを受けて、教員は第1部でこのテーマにそった発表をすることとし、大学院生については、第2部で自分自身の研究業績について発表することにした。 まず、第1部であるが、①私が仏教について、②高島元洋先生が神道について「食」をどうとらえているのかを発表した。私自身はこれまで仏教思想を専攻し、「食」という視点から仏教を考えたことはなかったが、今回の発表を契機に仏教と食について改めて考え、仏教の「食」観が、徹頭徹尾、空・縁起という仏教の基本理念と深く結び付き、また欲を抑制し修行して悟るという仏教の実践論に支えられていることを確認できたのは大きな収穫であった。 次に②の高島先生のご発表は、神道の「食」を、共同体論として構造的に考えるというたいへんに意欲的なご発表であった。仏教にとって「食」の問題は、修行上最低限摂取すべきものであり、抑制すべき欲望との関連において語られるべきものにすぎず、決して中心的な問題とはなり得ないのに対して、生々と豊穣を宣揚する神道においては、それは世界観の中心に位置する重要な問題となる。このような基本的位置付けを踏まえて、比較思想的観点から質疑を行って問題を参加者とともにさらに探求し深めたかったのであるが、時間があまりなかったことは残念であった。 ③の張先生のご発表では、戦後の日本人自身による日本文化論としての家族論の系譜が示され、その代表的な言説について分析が行われた。論旨が明快で論点がよく整理されたご発表で、多くを教えられた。また、張先生のご発表では、日本人が日本特殊論を唱え自己の優越性を主張するタイプの日本文化論に対する疑義が呈された。日本文化論自身がもつ政治的含意というものについて考えされられるとともに、ご発表を通じて、アジアの国々と日本との間のさまざまな歴史的経緯が、アジアの日本学研究にいまだに大きな影響を与えていることを改めて感じさせられた。また、国家をはじめとする共同体と学問研究との関係についても自覚的である必要を感じた。このような観点は、今回のような機会が与えられなければ、私自身あまりコミットしない観点である。その意味でも今回の部会は貴重な機会であった。 ④の大内山さんと⑤の尾崎さんは、ともに修士課程1年生であり、修士論文作成の中間報告として今回発表を行った。二人ともに、高島先生の用語でいえば外部、すなわち、共同体や人間の自我を支える超越的なるものを、日本人がどのように表象し、構造化してきたのかという共通の問題関心を根本のところで共有しつつ、それぞれ柳田國男、『日本霊異記』の研究に取り組んでいるように感じられた。二人ともに、研究対象を卒論とは変えており、今後さらに検討すべき問題も多く残されてはいるが、修論への土台を固めたという意味では今回の発表は大きな意義があった。また、国際的な場で発表し、質疑応答を行ったことは今後の研究活動の国際化のための大きな動機づけとなったことと思う。 ⑥のアンドレイさんは、日仏博士課程共同指導のプログラムから奨学金を得て、フランスのブレーズ・パスカル大学大学院から本学大学院に、頼住を受け入れ教官として留学している男子学生である。アンドレイさんと本学とのつながりの切っ掛けは、本学の大学院イニシアティブプログラムの一環として2006年にブレーズ・パスカル大学にて開催されたシンポジウムであった。今回、アンドレイさんのコンソーシアムでの発表が実現し、学生たちが質疑応答も含めてそこから多くを学べたのは、本学がこれまで推進してきた大学院教育の国際化の成果でもある。 アンドレイさんのご発表は、ギリシャのストア派の哲学と仏教の比較思想を試みたもので、明晰で論理的展開の辿りやすい発表であった。特に、「苦の癒し」ということに焦点をあてて、両者の共通点を解明したことは説得的であり、仏教、ストア派の思想の類似性について、これは人間の思惟構造の普遍性を示すのか、それとも古代におけるギリシャ文化とインド文化との交流の成果であるのかと興味をもった。アンドレイさんは英語で発表され、質疑も英語で行った。昨年度ブレーズ・パスカル大学に留学しアンドレイさんとも級友であった伊藤みずほさん(本学大学院生、哲学専攻)にフランス語通訳として同席していただいたが、学生もふくめて質疑が英語で成立したのはうれしい誤算であった。日本学の国際化において英語での発信も、今後重要なファクターとなると思われるが、その意味でも今回のアンドレイさんの英語によるご発表と質疑は大きな意味があった。 ⑦の李さんのご発表は、幕末の武士の倫理思想をさまざまな側面から探求したもので、幕末の複雑な歴史的背景をも考慮にいれつつ武士の思想を検討するという難しい課題に意欲的に取り組まれていた。李さんの充実した発表をうかがいながら、李さんご自身の豊かな才能に加えて御指導される先生方のお力を強く感じた。同世代の方のご発表に学生たちも大きな刺激を受けていた。 ①から⑦まで司会をつとめた斎藤さんは落ち着いて適切な司会ぶりであった。その斎藤さんの司会者としての報告書の一節に次のような言葉がある。「今回の国際日本学コンソーシアムにおいて、海外の日本学研究に多く触れることができた。私は普段、日本の内側に閉じこもりがちであり、海外への関心というものに乏しい傾向にあった。しかし今回のような経験を持つことは、己の視野を広げるためのよい刺激になったと思う。」斎藤さんの言葉にあるように、今回の部会が、学生たちにとって、自らの研究に国際性を導入し、より広い視野からみずからの研究を構築するきっかけとなればうれしく思う。 最後に、出席者に対するアンケートの感想・要望を紹介しておこう。「外国の先生方や学生さんの研究が聞けて、よかった。」「発表も興味深く、幅広いテーマで自分の研究においても参考となることが多かった。」「また半年後ぐらいに開催してください。」 日本語学、日本語教育学、日本文学、日本文学、日本歴史学に比べて、日本思想学は国際的にもまだまだ研究者も少なく、業績の蓄積も多くはないが、今後、コンソーシアムを通じて、この分野の研究の活性化に貢献するとともに、本学の大学院教育の学際性、国際性の向上に力を尽くしたいと思う。
7名が発表し、31名が参加した。 ・お茶の水女子大学 頼住光子先生 「仏教における「食」」 仏教においては、必要最低限の食欲は認められるが、それ以上のものは煩悩であるとして否定される。このような仏教の食に対する基本認識を踏まえて、食物をえるための托鉢行、原初的には容認されていた肉食が、大乗仏教の発生と中国への伝来を契機に、禁止されるようになったこと、禅において食が非常に重視されることなど、仏教における様々な食のあり方について説明された。 ・お茶の水女子大学 高島元洋先生 「神道における「食」」 神道においてはしばしば、神は食物の神であり、生命の神である。そのような神に食物を供犠として捧げることによって、神の活動を活性化し、自然から豊かな食物を得ようとするという、神道における思考の枠組みが説明された。 講演において、僧侶もこのような供犠の一種であるということが言われたが、修行という側面を持つ僧侶を供犠として捉えることに疑問が出され、宗教が多様な側面を持つということが指摘された。 ・中国・北京日本学研究センター 張彦麗先生 「日本文化論の中の「家族」」 様々な日本文化論において、家族とは、日本的集団主義を育成し、政治システム、社会構造、国家認識に大きな影響を与えるものと見なされてきた。このような点を踏まえ、日本の特性と民主化に関する様々な言説が考察された。 質疑応答では、普遍と特殊という語の使い方について、又、仏教・神道などの近代的カテゴリーを使用することの問題点について論じられた。 ・お茶の水女子大学大学院 大内山祥子さん 「神と妖怪―柳田國男『妖怪談義』の中で語られるお化け―」 柳田國男の主な妖怪観は、妖怪を神の零落したものとして捉えるということだ。この柳田が重視した妖怪観を取り上げ、そこに至るまでの妖怪観の変遷、フレイザーの「金枝篇」の影響、また、このような妖怪観が後の柳田の祖霊研究へ繋がっていくということが説明された。 質疑応答では、王の衰え=植物神の衰えという金枝篇の枠組みを、信仰の衰え=神の衰えという柳田の妖怪観に対比させることについて疑問が出された。 ・お茶の水女子大学大学院 尾崎円郁さん 「『日本霊異記』についての一考察」 「日本霊異記」における私度僧に着目し、僧と仏教の関係が考察された。私度僧は実際の仏道の伝道者であったために、彼らを迫害することは仏道の迫害であるとみなされていた。故に、私度僧を迫害したために、悪い報いを受けるという話が「日本霊異記」にしばしば登場するのである。 質疑応答では、「日本霊異記」における女性観について論じられた。 ・仏国・ブレイズパスカル クレルモンフェラン第二大学大学院生、日本お茶の水女子大学大学院留学生 Laurentiu Andrei ローレンティ・アンドレィさん “On the medical paradigm Stoics and Buddhists A comparative approach” 仏教とストア派は共に、人間の苦しみからの解放を目指している。両者は、医者が病気の原因と治療の手段を探すように、苦しみの原因を見つけ、そこからの解放の方法を明らかにする。その方法とは、自己を追求し、真理を体得することである。このように仏教とストア派を比較検討し、共通点の指摘がなされた。 質疑応答においては、The nature lawという言葉について、仏教やストア派の現代への影響、また、ストア派と仏教の自然観の相違などについて論じられた。 ・中国・北京日本学研究センター・大学院生 李斌瑛さん 「幕末期における武士階級の倫理思想-幕末の社会情勢との関連を中心に-」 まず、幕末期の動乱によって武士の戦闘者としての側面が強調されたこと、次に、江戸時代を通じて形成された儒教的な士道が依然として影響力を持っていたこと、最後に、外国の脅威に対して国家という意識が共有されたことの三点から、幕末の武士の倫理観が説明された。 質疑応答においては、幕末において天皇への忠誠という問題が非常に重要であるということ、また武士階級を狭く限定されたものとして考えるべきではないということが指摘された。 感 想: 今回の国際日本学コンソーシアムにおいて、海外の日本学研究に多く触れることができた。私は普段、日本の内側に閉じこもりがちであり、海外への関心というものに乏しい傾向にあった。しかし今回のような経験を持つことは、己の視野を広げるためのよい刺激になったと思う。特にローレンティ・アンドレィ氏の発表は、西洋の思想に対する関心を喚起させられるものであり、非常に興味深く聞くことができた。 (2009/01/05up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||