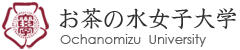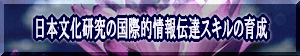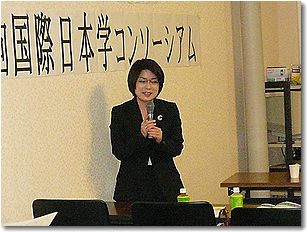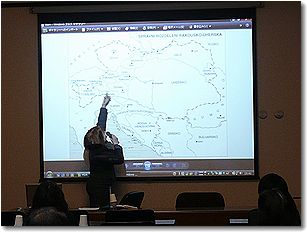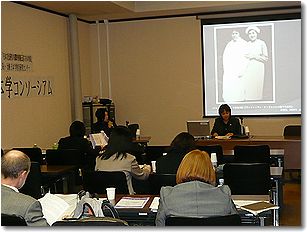今回で三回を数える国際日本学コンソーシアムだが、今年度は新しい試みが二つあった。一つは、企画段階から学生たちがかかわり、本コンソーシアムの運営において中心的な役割を果たしたこと、そしてもう一つは、「食・もてなし・家族」という共通テーマを設定したことである。 準備段階から開催期間中のすべてのプロセスにおいて、かかわった学生たちならびに事務局のスタッフのみなさんは八面六臂の活躍で、まず、心より感謝したい。また、大学間交流の観点からしても、学生間の交流こそがその中心に置かれるべきで、その意味でも今回の運営体制は望ましいものであったと思う。 なお、日本文学部会においては、会場からの質疑が不発の場合、司会者が率先して発言を行ったが、海外からの参加者のなかには、このようなあり方をいぶかしく思われた向きもあったかもしれない。しかしこれは、日本文学の各種学会においては基本的な姿勢で、司会者は、質疑の有無(会場の沈黙)についてはその責を負わねばならない。よって、会場からの質疑が不発の場合には、司会者が議論の口火を切る役割を担う。そのためには、司会者は、事前に十分な準備を要求されるわけで、今回、司会担当の学生はこの要請(日本文学内ルールだが)によく応えてくれたと思う。 共通テーマを設定したことについては、学内外において賛否両論あるところで、今後の再検討が必要だろう。しかし、「食・もてなし・家族」というテーマは、少なくとも日本近現代文学研究においては、非常に有効である。本部会においての各発表の概要については、担当者による報告にゆだね、本稿では、上記のテーマについていくつかの視座を示すことで、今回のまとめにかえたい。 近現代日本文学において、〈食〉のシーンは、その作品に内在する種々の関係性の指標として機能する。典型的なものが、島崎藤村『家』(1910)冒頭の昼食の場面である。『家』においては、地方の伝統的大家族が、近代的家父長制度への変容へと回収されていく(そのために大家族という「家」の形は崩壊する)わけだが、冒頭の食事の場面は、従来の伝統的大家族制を象徴するものである。神棚を背に家長が上座にすわり(すなわち神の代弁者)、家族の構成員(それは末端の奉公人を含む)がその家族内の位階にしたがってすわる。各自の前にあるのは銘々膳である。家の主婦であるお種は、彼らと食事を共にせず、給仕=もてなしに徹する。家長の「やってくれ」の一言を合図に大家族の構成員全員が〈同じ釜の飯〉を食する。この奉公人をも含む〈家族〉は、その労働を協同する共同体であり、その共同体の絆は〈同じ釜の飯〉を食することで確認される。一方、ほぼ同時期に書かれた夏目漱石『吾輩は猫である』(1905)で、苦沙味先生の一家が囲むのはちゃぶ台である。円形のちゃぶ台は、家族内に位階を形成せず(円卓会議と同じである)、家族は同等に位置づけられる。実際、小さな子ども達が好き勝手にふるまう苦沙味先生一家の食卓は混乱をきわめ、『家』における整然と秩序だった食事の場面とはまったく異質である。同時代において、家族秩序がこうむった変容は地方と東京とでは大きな違いがあった。地方の大家族と、東京の知識人の核家族の差違が、この食事の場面に如実に表れている。ちなみに、ある年代以上の日本人にとって、ちゃぶ台といえば星一徹、すなわちTVアニメ『巨人の星』(1970)で、頑固一徹の父親がちゃぶ台をひっくり返すシーンが自動的に連想されるが、これは父親の横暴を示すためだけのものではない。そもそもちゃぶ台をひっくり返すことができるのは、その上に並べられた食事を家族に提供し養っている家長の特権なのであって、強大な父権の象徴なのである。向田邦子脚本のTVドラマ『寺内貫太郎一家』(演出・久世光彦、1974)で、毎回、父親がちゃぶ台をひっくり返すシーンが〈お約束〉として演じられたのは、失われ行く父の権威への郷愁であり、この郷愁ゆえに、数々の向田作品は〈昭和〉を象徴するものとして、現在もなお、多くの人々から強い愛着を寄せられているのである。 家父長制に限らず、「食」のシーンは家族の問題を前景化する。もっともよく知られる例は、映画『家族ゲーム』(監督・森田芳光、1983)において、主人公の家庭教師の生徒の一家が、横一列にならんで食事をしているシーンである。ちゃぶ台では家族は相互の顔を見ながら食事をするが、この映画では彼らの視線は全く交わらず、全員が一方向を見ている。では、彼らの見ている方向、映画の画面には現れないが、彼らの座る食卓のこちら側に位置するものとは何か。それはテレビである。映画館においては、彼らは観客と向き合うことになるが、映画の内部においては、彼らはテレビを見ていると思われる。すなわち、高度経済成長の時期を経て、戦後日本の家族の中心に位置するものはテレビになったわけである。しかし今や、テレビは一家に一台ではなく一人に一台の時代を迎え、現代日本の食の場面は限りなく〈孤食〉へと変貌している。〈食卓を囲む〉という日本語のレトリックそれ自体が、空疎なものとなりつつある。 岡本かの子『鮨』(1939)は、「食」の持つ高度な象徴性を遺憾なく発揮した名短篇である。登場人物「湊」は、幼い子どもの頃、〈食べること〉ができなかった。彼が何とか口にすることができるものは卵焼きと海苔だけで、何か透明なものだけで生きていきたい、と切望していた。肉や魚を食べると体が穢れるような気がし、嘔吐した。彼は本能的に、〈食べること〉が他者の〈死〉を体内に取り込むことであることを知っていたのである。そのような子どもの状態は、必然的にその生育の責任を負う母の疎外をもたらす。家長である父は母を責め、彼を無視する。しかし、ある日彼は、縁側に茣蓙や道具を持ち出して、母親が清潔な手で握ってくれた鮨(非日常的な食事)を食べ、魚を食べることができた。このとき彼がとらわれた病的な高揚は、まさに彼が他者の〈死〉を乗り越えた勝利の快感を示している。食物連鎖の頂点に位置する征服者としての快感である。彼が〈食べること〉ができるようになって、父親は急に彼に眼をかけはじめるが、それに従い肝心の家は没落へと向かい、物語の現在時、「湊」は家族を持たない〈孤食〉の人となりはてている点に、この作品の批評性がある。家父長制、社会への適応と馴致が家の没落をもたらしているのである。 鮨といえば志賀直哉『小僧の神様』(1920)だが、ここでは鮨という食文化記号が貴族院議員の「A」と、秤屋の奉公人「小僧」のこえがたい社会階層の断絶の象徴として使われている。小僧があこがれをもって見つめたのは、現在ではなくなっている「屋台」の鮨であり、「A」の家族のように、家に鮨をとることができるのは、ごく一握りの人たちに限られていた。すなわち、ここでは鮨という料理それ自体というより、それが饗される場所・形態が文化記号としての意味を担っているのである。ちなみに、全国に店舗展開する「小僧寿し」チェーンの名前が、創業者が『小僧の神様』を読み、高級食品であった鮨を、庶民の手の届くものとしておなかいっぱい食べてほしいと思ったことに由来することは、日本ではよく知られたエピソードである。 現代社会においては、〈食べること〉が生存本能としてよりむしろ社会的行為としての意味を持つこと、とくにもっとも小さな社会単位である家族と深く関わる行為であることは、よしもとばなな『キッチン』『満月―続キッチン』(1987)が示すところだが(ちなみに上野千鶴子は、『キッチン』に登場する人間関係を、血縁によらない「食縁家族」と称した)、それをより繊細かつ鋭敏に描いたのは、大島弓子の少女マンガ『ダイエット』(1989)である。この作品で前景化されているのは少女の疎外と〈食〉の関係である。主人公の少女は、家族のなかで孤立しており(といっても、意識的にネグレクトされているわけではない)、その孤独をまぎらわすため、過食と拒食を繰り返す。最終的に、彼女は友人に救われるが、そのとき彼女ははじめて、食べ物を〈おいしい〉と思うのである。このようなテーマが目立つようになったその背景には、日本の現代社会において、とくに若い女性の摂食障害が社会問題として広く認知されつつあったことがある。この〈食べること〉をめぐるオブセッションは、女性作家の作品には繰り返しあらわれる。松本侑子『巨食症の明けない夜明け』(1988、これは過食症を描いている)、小川洋子『妊娠カレンダー』(1990)などはその一例だが、この〈食べること〉をめぐるオブセッションを、とくに母―娘関係の機能障害の象徴として描いたのは倉橋由美子の諸作である。肥満し膨張を続ける母は、グレートマザーとして娘を抑圧するものの象徴であり、対照的に拒食し嘔吐し、やせ細っていく娘は、その抑圧と支配から逃げ切れず、肥満する母への憎悪は殺意へといたる。一九六〇年代、いまだ男性作家によって領有されていた〈知〉の文学、観念性と象徴性に満ちた言語表現の領域に登場した新世代女性作家としての倉橋が、どれほどのテクスチュアルハラスメントにさらされたかは、別の場所で論じたのでここでは繰り返さないが、〈食〉をめぐる表象においても、彼女が現代女性文学の先駆けであったことは確かである。 樋口一葉『にごりえ』(1895)では、白米と黄金色のカステラが、ともに絶望の記号として機能している。『にごりえ』における、もっとも印象的なエピソードは、お力の子ども時代の想い出である。一家の命をつなぐ白米がざらざらと溝板のすきまから泥の中へとこぼれ落ちてゆく、この場面で七歳のお力の視線は溝泥の底なき底を、つまり下方を見ている。この絶望は、物語の現在時においては、もう一人の「細民」の子、太吉のカステラのエピソードに重ねられる。黄金色の「日の出屋のかすていら」、溝泥にまみれたそれは、記憶の起源として太吉のなかに生き続けるだろうし、彼の場合、自分がもらったカステラが原因で両親が離婚し、さらにそのあと父が無理心中をとげたとなれば、そのトラウマははかりしれない。お力の子ども時代の絶望は、そのまま、もう一人の「細民」の子である太吉において反復される。〈にごりえ〉の生は反復され、その絶望は引き継がれる。明治下層社会の構造が、ここでは白米とカステラという食記号に託されている。 以上、例示したのは「日本文学における食・もてなし・家族」のごく一部分にすぎない。〈食〉は文学において多様な表象としての意義を担っている。作品へのアプローチの方法の一つとして有効であることをここに確認し、日本文学部会のまとめにかえたいと思う。
日本文学部会は、国際日本学コンソーシアムの第2日目、12月16日(火)の13時から17時にかけて、文教育学部1号館1階大会議室にて行われた。部会テーマは、「日本文学における食・もてなし・家族」である。部会参加者数は、部会担当教員の菅聡子先生と司会の武内佳代の2名および発表者7名を除くと、約60人にのぼり、非常に盛況な会となった。 当部会は、第一部と第二部に分けられており、それらの最初にまず、海外の大学からお招きした教員による基調講演があり、続けて院生が研究発表をする形をとった。 第一部は、国立台湾大学(台湾)の范淑文先生による、「漱石の作品における食・もてなし―『虞美人草』を例として―」という演題のご講演で幕を開いた。范先生は、漱石の日記や友人宛書簡などから、漱石の実際の〈もてなし方〉あるいは〈もてなされ方〉を丹念に辿ったうえで、次に、初期作である『吾輩は猫である』『草枕』、後期作である『道草』における来客場面を取りあげて、漱石がいかに、もてなしの場面を意識的に描いていたか、について解説をされた。そして、『虞美人草』においては、女主人公の藤尾が、お茶や菓子をもてなす/もてなされるという振る舞いを決してしないことに着目して、そうした身振りこそ、誰にも心を許さない藤尾の心の悲劇の表出であることをご結論なさっていた。講演後には、菅先生から、これまで一切検討されてこなかった漱石作品のもてなしの表現について、改めてその重要性が明らかになったことなどが指摘された。 続いて、本学大学院生の森暁子さんが、「北条氏繁の寝茶の湯―戦国武将の生活の一齣」というタイトルで発表なさった。茶の湯は、戦国時代以降、武将たちの嗜みとして大いに持て囃されたことで知られる。森さんのご発表は、16世紀の相模の国の武将、北条氏繁が行ったとされる「寝茶の湯」という風変わりな茶の湯をめぐる考察だった。『北条記』という本の一系統で紹介されている「寝茶の湯」は、身体の養生と楽しみとを目的として、横になりながら茶を楽しむなど、本来の茶の湯のかたちを崩すことに特色がある。発表は、そうした型破りから、氏繁の滑稽な人物像を改めて浮かび上がらせるものであった。発表に対して、会場からは、「寝茶の湯」が本来の型を崩すことについて、これは、武将であるにもかかわらず茶の湯という風流をやみくもに称揚する当時の武将たちの不心得に対する批判の意味合いがあったのではないか、といった趣旨の見解が示された。 次に、国立台湾大学の大学院生の麥媛婷さんが、「芥川龍之介における母性認識―初期の母性描写の抑制から後期の母性謳歌へ―」というタイトルで、発表をされた。麥さんは、芥川龍之介の生い立ちを背景としつつ、芥川文学の「母性」の描かれ方を、初期作から晩年の作にかけて分析することによって、芥川の母性認識が、「母性に対する感情の抑制から母性賛美」へと変化していくプロセスを解明した。これについて、会場からは、芥川の母性認識を系譜的に分析した成果への評価とともに、「母性」という術語の定義をもう少し絞ったほうがより良くなるのではないか、という提案が出された。 この後、15分ほどの休憩をはさみ、第二部へと移った。 第二部は、淑明女子大学校(韓国)の李志炯先生による、「文学者の経済意識と家庭―島崎藤村と1920年代の日本を背景として ―」 という演題のご講演から始まった。李先生は、1920年代の日本社会における、円本ブームによる作家の印税収入の急増や金融恐慌といった時代的経済的コンテクストのなかで、島崎藤村が、そうした同時代的状況をどのように短編小説『分配』に描き込んだかを、丹念に読み解かれていった。『分配』は、藤村の家庭をモデルとした作品として知られるが、なかでも、藤村自身をモデルとした「父」が、莫大な印税収入を四人の子供に配分するために、異なった銀行を利用しながら奔走する本作の後半部に焦点が当てられた。そして、そのような銀行巡りの描出が、同時代的コンテクストに照らして、最善の財産分与の方法という意味合いだけでなく、そのような行動をとった聡明な作家として、読者から好意的に見られるための藤村の身振りという意味合いをも併せ持っていることを明らかになさった。講演後には、司会者のほうから、作中に銀行巡りの理由が書き込まれていないことが、作者と読者との時代認識の共有それ自体を示しうるのではないか、などの意見を述べさせていただき、李先生から応答をいただいた。 続いて、院生による研究発表として、カレル大学(チェコ)の大学院生、アンナ・クジヴァーンコヴァーさんが、「マグダレナ・ドブロミラ・レッティゴヴァ-:チェコ料理及び文学への貢献」 というタイトルで発表をなさった。アンナさんは、18世紀から19世紀にかけてのチェコの民族・文化復興の気運において、女性作家マグダレナ・ドブロミラ・レッティゴウァーがチェコ語で著した、チェコの伝統料理や家庭に関する本が、単に料理や作法を紹介するにとどまらず、いかに中流階級家庭にチェコ語を再導入する役割を果たしたか、について検討をされた。質疑応答では、一般に母から子へと受け継がれやすい言語の在り方において、マグダレナの本の読み手が主に家庭の主婦であったことが、チェコ語復興に大きく寄与した要因ではないか、という見解が出され、また、マグダレナ自身がそうした効果を期待したかどうかについての質問が出された。そうした質問に対し、アンナさんからは、質問者の述べたような意味において、マグダレナの、フェミニストとしての再評価がチェコで始まっていることが紹介された。 次に、淑明女子大学校の大学院生、朴婤榮さんが、「菊池寛の通俗小説における近代家庭の女性」というタイトルで発表された。朴さんは、1920年代に発表された菊池寛の通俗小説の代表作『真珠夫人』と『東京行進曲』における女性の表象について、前者では社会規範に闘争心を抱く女性が描かれるのに対し、後者では近代家族へと抵抗なく参入しようとする女性が描かれているという違いに焦点を当てていらした。そして、前者に比べ、後者のほうが、読者を喜ばせるような都市文化の華やかさがより重点的に描かれていることを指摘しつつ、そのように変容させられた女性像こそ、良妻賢母思想が強調されはじめた世相において、読者である大衆の期待を吸い取った形象そのものであることを結論なさった。発表後は、『真珠夫人』において女主人公に重ねられる世界的悪女ユディトとの差異についてなどの質疑応答がなされた。また、司会者のほうからは、軍国主義下の良妻賢母思想が兵士産出の国家プロジェクトの一貫であることを補足説明させていただき、そのような体制に加担する女性像という暗部が、『東京行進曲』という作品では、都市モダニズム文化の華やかさによって隠蔽、充塡されていることを述べさせていただいた。 最後に、本学大学院生の李南錦さんが「国家と家庭と女性―日・韓近代文学における看護婦表象と良妻賢母思想」というタイトルで発表をされた。李さんは、日・韓近代を代表する作家である、夏目漱石と李光洙(イ・クァンス)の作品を中心に取り上げ、文学に描かれた看護婦表象と当時の時代言説との関わりを、ジェンダー論的な観点から検討なさった。文学作品とその他の文献・画像資料を通して、当時、癒しや安らぎを提供する存在としての看護婦が、セクシュアルと貞淑という二重のイメージをはらんでいたことを考察したうえで、家父長制下の日本社会および日本の帝国主義下にあった韓国社会において、そのような看護婦表象がいかに良妻賢母思想に基づく主婦/妻の表象へと接続されていったかを解明なさった。発表後は、漱石と李光洙の看護婦の描き方の差異について質問がなされ、そうした差異が当時の日韓の権力的布置の反映であることなどが応答された。 以上が、日本文学部会の内容報告である。 最後に、司会者の観点から感想や意見をいくつか付言させていただく。 当部会は、他の部会と日時が重ならなかったため、思いの外、来場者数が多かったが、大きめの会場だったので、余裕をもってご着席いただくことができて幸いだった。とはいえ、そのような会場の大きさは、来場者からの質問や意見を少なくさせたように思う。いずれも明晰で刺激的な講演・発表であったにも関わらず、学生による質問や意見がとくに少なかったのが残念だった。今回の国際コンソーシアムでは、とくに院生主導であることが重視されていたことを考えれば、今後は学生がさらに積極的な発言ができるような、学生自身の企画による会場設営や事前勉強会などの準備が必要になるのではないか。 また、今回の日本文学部会では、明治・大正時代の近代文学に関する発表に偏ったことが、一つの問題点といえるかもしれない。しかし今回の場合、そのように近代という時代に焦点化した多角的な発表の折り重なりが、むしろ部会の全体的まとまりを保ち、時代と文学の連関に対する会場の理解がより深まる好結果に繋がったように思える。これは、今後の部会の在り方、および、テーマの切り取り方を考えるうえで、一つのケースモデルになるにちがいない。 以上、日本文学部会に関する報告を述べさせていただいたが、紙幅の関係上、質疑応答の内容などについて多く割愛させていただいたことをご容赦願いたい。 (2009/01/05up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||