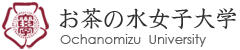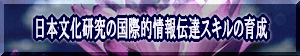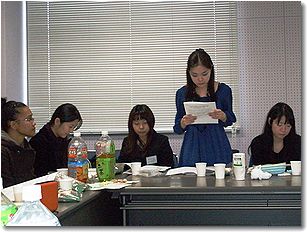全体テーマ「食・もてなし・家族」という新鮮な観点から日本語の表現をみるという、得難い経験ができたことを喜びたい、と思います。 最初の第一部の講演「タマネギ1個とセロリ1本―食べ物名詞の捉え方の日英比較と英語・日本語教育への示唆」(岩崎典子先生・英国・ロンドン大学SOAS)が始まって、いろいろな形状のおいしそうな食べ物の映像がスクリーンに映ったとき、なんてぴったりのお話か、とわくわくしました。それからはもう、どの発表も、“食”とか“もてなし”とか“ジェンダー”とか、新たな切り口で日本語を料理する、フレッシュな包丁さばきを楽しみました。ふだんの大学院の日本語学ゼミで、聞き慣れているはずの院生たちの発表内容も、器を変えて盛りつけを凝らせば-もともとしっかりした研究なので-一挙に“前景化”するのでした。 その勢いで、「交流の時間」も、いろいろなバックグラウンドを持つ参加者が、各自の研究テーマを披露し合い、刺激しあいました。今回のテーマにあまり関係がなくても、どこかで何かの接点を探り合いながら、研究姿勢への尊敬の気持ち、研究方法への示唆や、日本語研究のおもしろさへの共感が共同研究への芽に将来育っていく可能性、など、各自が得たものは、今後いろいろなところで、豊かな実りとなることでしょう。 ご発表、ご参加の先生方、院生・学部生の皆様、司会・準備・裏方、など多くのことをこなしてくださった皆々様に深く感謝申し上げます。
日本語学部会は、国際日本学コンソーシアムの第1日目、12月15日(月)の12時30分から16時30分にかけて、人間文化創成科学研究科棟6階大会議室、5階SCS室にて行われた。 今回の国際日本学コンソーシアムは、「食・もてなし・家族」をテーマとし、日本語学部会でも各自が多彩な研究発表を行った。 当部会は、第一部と第二部と交流の時間に分けられていた。まず、海外の大学からお招きした教員による講演があり、続けて院生が研究発表をする形をとった。 第一部は、英国・ロンドン大学SOASの岩﨑典子先生による、「タマネギ1個とセロリ1本“One onion and one celery”?-食べ物名詞の捉え方の日英比較と英語・日本語教育への示唆」という演題の御講演で幕を開いた。先生は、加算・付加算の文法的区別の存在(英語)と不在(日本語)が、英語母語話者、日本語母語話者の食べ物名詞の捉え方に影響するかどうかを調査された結果、食べ物名詞の捉え方には両者に有意差がなかったという報告をまず述べられ、それなのになぜ、英語の加算・不加算や日本語の助数詞の習得が難しいのかという問題を提出された。 岩﨑先生ご自身はこれを、「食べ物名」を短絡的に文法項目と直結させて教えている従来の教授活動や、授業が実際に行われている教室内で、文脈や場面の配慮より、文・単語レベルの学習が優先されている結果ではと報告なさった。そして今後の教育活動への示唆として、文脈・場面を考慮した上での加算・不加算や助数詞の選択練習や、それらの選択判断について、プロトタイプ的なものと、そこから連続性をもつものに分けて教えていくことなどを提案された。 続いて、本学大学院生の具軟和さんが、「広告と食-日・韓のコマーシャルからみることばと食-」というタイトルで発表なさった。具さんは、おいしさや味覚をどう捉えて表現するかをコマーシャル媒体から眺め、日韓で比較された。共通点としては、日本も韓国も「おいしい」、「うまい」、「健康」、「自然」という表現が多用されている場合が多いことであり、相違点としては、日本は飲料のコマーシャルが多く、酒類も加えると、飲み物の広告が全広告の4割を占めるのに対し、韓国では飲み物の広告はそれほど多くはなく、特に酒類のコマーシャルは好まれない傾向があること、代わって韓国では加工食品の広告が多くを占め、農産物の広告も日本より見られること、日本が食品の風味を表す表現が多いのに対し、韓国では食品の品質をアピールする傾向が強いこと、コマーシャルに使われている異なり語数、延べ語数ともに韓国よりも少ないことなどであることを示された。 この後、10分ほどの休憩をはさみ、第二部へと移った。 第二部は、英国・ロンドン大学SOAS大学院生の阪口治子さんによる、「日本語学習者からみたジェンダー言語」という題の研究発表から始まった。阪口さんは、日本語学習者のジェンダー認識を明らかにすることを研究目的とされ、日本に留学経験のある日本語学習者を対象に、日本社会でのジェンダーの捉え方、認識しているジェンダー言語の種類、実際のジェンダー言語の使用と自己のジェンダー意識の関係についてなどについて調査を行われた。結果、回答者の大半がジェンダー言語に対しステレオタイプ化したイメージを持ち、実際の言語行動の多様性に関しては深い認識を持っておらず、むしろ中立的な、オーソドックスな日本語を使用していることが分かったと説明された。また学習者の性差だけでなく、年齢が回答に影響を与えてことも見て取れたと述べられた。阪口さんはこれらを踏まえ、日本語教育の現場での言語行動の多様性の意識と記述的情報に基づくジェンダー言語の指導の推進を、また日本語母語話者には、自己が学習者にとって常に文化的・言語的情報源となることを意識した学習者との関わりの促進を提言された。 次に、本学大学院生、藤井禎子さんが、「日本語の歴史の中の位相と性差」というタイトルで発表された。語の位相差は、性差、地域差、階層差などによるものがあるが、中でも藤井さんは性差によるもの、特に女性によって使用された女房詞に着目し、それがどのように一般社会に広まったかを検証された。 次に、本学大学院生、アンナ・チョールナヤさんが、「江戸語の位相と遊里語」という題で発表された。前述の藤井さんの扱った女房詞と並ぶ女性特有の言葉に、主に近世に遊里で遊女やその周辺に使用された遊里語があり、また、同様に男性が専ら使用した言葉として武士詞があるが、チョールナヤさんはそれらを、敬語や人称などの観点からまとめられた。 次に、本学大学院生、イソ・アパコーンさんが、「タイ語の文末辞と日本語の終助詞「わ」:「Kha」と「わ」の対照」というタイトルで発表された。日本語の終助詞「わ」は、女性が主たる使い手である場合が多い終助詞であるとよく整理されるものであるが、イソさんはそれとよく似たタイ語の文末辞である「Kha」に注目された。両者は共通点として文末に置かれ、主に女性が使い手であることが挙げられる。また相違点としては「Kha」が相手への丁寧さや敬意などを表し、親密でない、または目上の相手に対して用いられるのに対し、「わ」は、かつては親和感を表していたのが、今は強気を表す、強い主張を表すときに使用されるようになったと観察できることであると述べられた。共にそれらの特性から、家庭内のような、親密な関係の人間で構成され、かつ状況にもよるが、基本的には強い主張がなされることがない場面で使用される言葉であることを発表された。 次に、本学大学院生、高橋秀子さんが、「平安時代の和歌の贈答について」という題で発表された。平安時代には和歌や和歌を書いた文を、花や葉、枝のような植物に添えたり、またそれらに直接和歌を書き付けて贈ることが行われた。先行研究において、和歌や消息などの文に添える植物のことを「文付枝(ふみつきえだ)」と称されていることを受け、高橋さんは、それに加えて書きつけられた植物そのものをも「文付枝」と位置付けられた。特に『うつほ物語』と『源氏物語』における文付枝の例を比較検討した結果、例の数はほぼ同数であるが、用いられ方に相違があり、『源氏物語』では用いられ方が「添える」ことにほぼ終始しているのに対し、『うつほ物語』では用いられ方が様々で、その植物の種類も多いということが分かったと述べられる。具体的には、木の実をくりぬいて中に和歌を入れて贈る、植物そのものに和歌を書きつける、手習いの手本に植物を添えて贈るなどの例である。結果として、『源氏物語』よりも『うつほ物語』の文付枝の用いられ方の方が、独立した表現手段としては弱いところがあるが多彩であると高橋さんは観察された。さらに、『うつほ物語』では特に植物に書きつけられた歌は全て恋の歌であり、相手を慕う心を伝えるには書きつく方法が最適であるとされていることが考えられ、また実の中に和歌を入れる方法は文付枝の用いられ方として特異であり、これが晋の故事を踏まえているとすると、作者は物語への故事の採用に留まらず、それを和歌の贈答手段に転じさせたことになるとまとめあげられた。 この後、10分ほどの休憩をはさみ、場所を変えて、交流の時間がもたれた。 交流の時間 ①参加大学院生のスピーチ は、今回のテーマとは直接関係はないが、本学大学院の日本語学ゼミで行われている研究内容の紹介も兼ねて、各人が簡単なスピーチを行った。 本学大学院生の星野祐子さんの、「目的をもった会話の研究―多人数による話し合い場面を中心に」の発表で始まった。星野さんは話し合い場面を中心に、目的をもった会話を人はどう行っているかについて考察されている。問題解決というゴールに向かって提案と応答がどのように連鎖するか、話し合いの進行に関わる手続き的な発話にはどのようなものがあるか、話し合いにおける引用表現の機能にはどのようなものがあるかなどを着眼点としていると説明をされた。 次に、本学大学院生の百瀬みのりが、「中世期日本語資料にみられる接続詞の機能」について発表した。中世期は、日本語が音韻、語彙意味、文法のあらゆる面で古代語から近代語へと移行した時代である。中でも接続詞の成立は、日本語の近代語化に寄与するところ大であった出来事といえる。研究では、①接続詞の成立②接続詞の機能③接続詞の運用に特に注目し、接続詞の成立要因の解明、諸言語単位を「つなぐ」だけではない接続詞の機能、文章や談話中での接続詞の運用のされ方を考えている。特に最近の観察では、接続詞には「区切る」機能が見られることが分かり、それについてさらに考察中であることを述べた。 次に、本学大学院生の井之浦茉里さんが、「歌舞伎テクストにおける義太夫節の機能」について発表された。井之浦さんは、歌舞伎テクストにおける義太夫節がもつ、地の文を語ること以外の機能を見、特に引用、くり返し、オノマトペ(音象徴詞)などの多様な表現に注目して考察を行われている。特に、ある演目内での義太夫節と台詞の言語量の調査と義太夫節の出現パターンの分析、義太夫節の表現の分析、義太夫節が登場人物の台詞となりうるような内容を語ったり、登場人物の心情、心境、思考を語ったりしている箇所の分析について研究上の着眼点とされていることを述べられた。 次に、本学大学院生の王湘榕さんが、「日中語の指示詞の対照研究」について発表された。王さんは、指示詞によるテクストの一貫性や結束性を保証する機能に注目され、日本語の指示詞は「コ・ソ・ア」の三体系であるが、中国語のそれは「這・那」の二体系であり、日本語の「ソ」系と中国語の「那」系はそれほど一致はしておらず、中国語の場合、聞き手との関わりではなく、話し手とのかかわりの有無によって、対象が「われわれ」の領域内に属するものと捉えられれば「這」で、「われわれ」の領域外に属するものと捉えられれば「那」で指示すると説明される。さらに、日本語の「ソ」系が中国語の「這」で訳されている例文に着目し、日中の文章の結束性の相違点を観察されている。 次に、本学大学院生の高橋由衣子さんが、「三島由紀夫の戯曲の研究」について発表された。高橋さんは、三島由紀夫の戯曲と短編小説の表現に着目し比較することで、その戯曲の表現について明らかにしようとされた。それによれば三島の場合、戯曲と小説では比喩表現、人物の会話的特徴、外的特徴、空間・時間表現などが異なると説明される。三島は戯曲では意外にも技巧を凝らした比喩を用いることはないこと、台詞に地域方言を用いる場合、品のない人物がその使い手である場合が多いこと、「海」が重要な場面で登場すること、時間は順序を変えることなく、一方方向に進んでいくのみであることなどが分かったと述べられた。 次に、本学大学院生の石井佐智子さんが、「言い切りのタについて」を発表された。第二言語習得において難しいとされる時間表現のうち、石井さんは日本語の「タ」に注目される。学習者は初級で学習した「タ=過去」の用法が全てであると思い込む傾向があるようだが、日本語の「タ」には過去テンスを表す以外の多くの用法がある。石井さんはそれらに注目し、過去を表す以外の「タ」の用法について、日本語母語話者、非母語話者を対象にアンケートを行い、両者の相違の有無や、相違がある場合、どこにそれが見られるかを調査された。また、母語話者がこの多様な「タ」をどう捉えているかを明確にするために、クラスター分析、正誤判断を行い、定量的な調査から「タ」の使い方を検討することも準備中であると発表された。 交流の時間 ②SOASなど参加協定校における日本語学研究の現状報告、共同研究の可能性、等、自由な意見交換 は、①で行った発表を受け、茶話会形式で交流がもたれた。 まず英国・ロンドン大学SOASの岩﨑先生、阪口さんから、ジェンダー言語の捉え方が最近日本でも変わってきたのではという提言がなされ、日本語母語話者として生活基盤を日本に置くその場のほとんどのメンバーが、自身のジェンダー言語観について語りあった。 また、会には日本語教育専門の森山新先生や日本文学専門の台湾大学 范淑文先生、麥媛婷氏、あるいは、学習院大学の日本語学ゼミの方々等関係諸分野からの出席もあり、それぞれ自身の専門について、また母校の語学教育のあり方、日本語学専攻の現状についてなど、話が弾んだ。 以上が、日本語学部会の内容報告である。最後に、司会者の観点から感想や意見をいくつか付言させていただく。第二回コンソーシアムの日本語学部会に比し大きな収穫の一つは、この【交流の時間】の設定であったと考えられる。話がしやすいように座を正方形に配置し、正に「もてなし」の形式にして話を行ったことで、普段は接することができない他校からの参加者らとも触れ合い、議論ができたことは、参加した大学院生の研究の深化や振り返りに大きな役割を果たした。惜しむらくは、他の部会と開催時間が重複し、参加を希望していながら不参加とせざるを得ない方々も若干いたことである。時間の設定や教室の配置などについて再考し、次年度の第四回国際日本学コンソーシアムにぜひ生かしていきたい。 以上、日本語学部会に関する報告を述べさせていただいたが、紙幅の関係上、質疑応答の内容などについて多く割愛させていただいたことをご容赦願いたい。 (2009/01/05up) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||