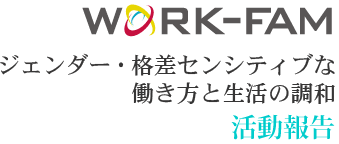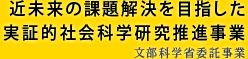イベント
-
⇒調査報告(調査結果の概要をご覧頂けます)
- 研究会 オランダのWLB政策
- 日時2013年1月31日(木) 18時~21時
- 会場お茶の水女子大学 本館(経済資料室)
- テーマ 「オランダの女性就労の高まりと福祉国家改革」
- 講師廣瀬 真理子 氏(東海大学教養学部教授)
 専門分野は、社会保障法・政策、高齢者福祉。
専門分野は、社会保障法・政策、高齢者福祉。
著書『グローバル化のなかの福祉社会』(共著)ミネルヴァ書房、2009年
・「オランダにおける最近の地域福祉改革の動向と課題」『海外社会保障研究』第162号、 国立社会保障・人口問題研究所、2008年
・「EU社会政策とオランダ福祉国家の変容」『福祉社会学研究2』東信堂、2005年












オランダではこれまで専業主婦も多く、子どもを保育園に長時間預けるのは母親として躊躇する感情があることや、法的には所得保障がなく、女性の多くがパートタイム職に従事していることなどから、育休取得率は4割程度となっている(2006年)。近年、急速に女性の社会進出が進んでいるが、北欧とは異なり、女性の自立のためというよりは、より生活の豊かさをもとめるための就労といえよう。相対的に高学歴の女性からは、女性がコントロールできるお金を持ちたい、という動機があるという声も聞く。
オランダの福祉国家の特徴としては、「北欧型」「大陸型」にも当てはまらない「ハイブリッド型」であるという点が挙げられる。北欧型と違うのは、伝統的に社会保障はサービスよりも現金給付に比重が置かれたため、子育て支援策が遅れている点、保守中道政権期に福祉国家が発展した点である。大陸型と違うのは、職業的地位の確保よりも格差是正を重視している点である。そのため、所得比例で保険料出すが受け取るのは定額という、税金に近い制度となっている。
オランダの特徴として、国民は国からの介入を嫌う傾向にあり、地方自治の独立性が高く、キリスト教民主主義の伝統から、一番近い人(家族等)がまず面倒を見るべきという補完性原理、連帯(ソリダリティ)、人間の尊厳の重視(パーソナリズム)等が重視されている。そのため、性別役割分業観が根強く、社会保険制度に基づく現金給付が中心であり、国家にも市場にも依存しない、民間非営利セクター(労使を含め)の役割が大きくなっている。
オランダの女性就労の高まりの背景には、EUの影響がある。1975年の男女平等賃金指令に始まる様々な指令によって、それまでオランダ国内に存在していた男性稼ぎ手原則が問題化された。国内では、1970年第以降、キリスト教会離れにより女性の社会進出に対する意識が変化し、高学歴化が進み、女性解放運動が高まった。1982年には、長期失業者対策として、政労使合意による賃金抑制政策と雇用の創出がめざされたが、実際にはそれまで家にいた女性がパートとして働くようになった。
最近のEU専門委員会が示す「家族政策」とは、児童/家族のための現金給付、出産・育児休業政策、子どもがいる家族への住宅給付、高齢者や扶養家族のケア責任を有する家族への支援などである。オランダの「家族政策」は、基本方針としてEU政策が目指す「現代化」、すなわち就労重視、自己責任原則を強化している。保育サービスは、保育所の整備と費用負担と民営化を進め、その他の要保護児童対策は、分権化と自治体の責任を強化している。そのため、地域格差が生まれ、インフォーマルなケアの担い手へのプレッシャーが強くなっている。
オランダにおける両立支援と家族関連政策について、所得保障として児童手当法がある。1995年の改正により子どもの人数加算がなくなり、年齢区分のみによる給付が行われるようになった。休業保障は就労とケア法によってなされ、出産・育児休業、父親休業、緊急対応休業(子どもの病気、水道管の破裂等)、養子縁組休業等がある。オランダでは男性の育児休暇取得率が16%に上り、EUの中でも高い方である。保育保障としては、保育サービス法があり、保育所(0歳~4歳まで)、在宅保育(保育ママ)、学童保育などがある。共働き増加の陰で、離婚や非婚を原因としたひとり親家庭(母子世帯)も増加し、こうした家庭は貧困に直面している。一方、社会保障給付が削減され、若年層の就労が難しく、障害給付をもらう若者が増加していることが問題となっている。
最後にまとめると、オランダの福祉国家の基盤であったキリスト教民主主義の伝統が崩れ、アングロサクソン化(新自由主義)しつつある。また、失業率を低くするために福祉国家改革によって就労促進策を進めているが、同時に、有期雇用や派遣などのフレキシブル労働者と呼ばれる不安定就労層が拡大している。パートタイム雇用の増加についても、1.5人働きといっても男女が平等に0.75ずつ働くというよりは、これまでのところ、男性1、女性0.5のように、フルタイムの配偶者が存在してこそパートタイム就労が生活に豊かさをもたらすものとなっている。この理想と現実が乖離している点については、国内だけではなく、OECDやEUレポートなどにおいても指摘されている。
- 講師廣瀬 真理子 氏(東海大学教養学部教授)
- 最終成果報告会「家族のウェルビーイングとワーク・ライフ・バランス」
- 日時2013年1月23日(木) 18時~21時
- 場所お茶の水女子大学 共通講義棟2号館201号室
- 司会戒能 民江 氏(お茶の水女子大学)
式次第
1.羽入佐和子お茶の水女子大学長挨拶
2.プロジェクト「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」紹介
3.報告
永瀬伸子〈労働・人事制度研究〉
女性の就業継続と日本の雇用慣行
舘かおる〈ロールモデル研究〉
「女性活躍社会」へのロールモデル形成政策(福井県の事例から)
石井クンツ昌子〈家族・男性の育児家事研究〉
男性の育児参加とワーク・ライフ・バランス
菅原ますみ〈発達心理研究〉
子どもの発達と父親と母親のQOL
神尾真知子〈法政策研究〉
新たなワーク・ライフ・バランス
(成果報告の詳しい内容は、後日HP上で公開します)
4.コメント
麻生裕子氏 (連合総合開発研究所 主任研究員)
岩田克彦氏 (職業能力開発総合大学校教授)
加藤邦子氏(宇都宮共和大学 子ども生活学部教授)
呉本紀子氏(パナソニック株式会社エコソリューションズ社 ダイバー推進室主事)
後藤憲子氏(ベネッセ次世代育成研究所主任研究員)
松田茂樹 氏(第一生命経済研究所 主任研究員)
三橋明弘氏(旭化成アミダス株式会社 企画管理部長)
5.報告者によるパネルディスカッション、質疑応答
羽入佐和子 お茶の水女子大学学長 挨拶
本日はお出でいただきまして誠に有難うございます。
このシンポジウムは、文部科学省・日本学術振興会の委託事業「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学推進事業」として、2008年に採択されました事業、(研究課題名)「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」の最終成果報告会として実施するものです。
この事業のテーマは「生活の豊かさを生む新しい雇用システムの設計」です。
本日は当時の文部科学省研究振興局長でいらっしゃいました磯田さまにもお越しいただきました。
採択から4年間にわたり、労働経済学、家族社会学、ジェンダー論、発達心理学、労働法、比較政治学と多方面の研究者が集まり、学外の研究者、労働組合、企業の方々等にもご協力いただき、学際的な研究を続けてまいりました。
さらに、調査にご協力くださった大勢の方々に支えていただき、本日を迎えることが出来ましたことを、関係の皆様に心から感謝申しあげます。
本学には、ジェンダー研究の歴史と蓄積があり、とくに21世紀COEプログラム「ジェンダー研究のフロンティア」(2003年)を機に、それまで以上に国際研究拠点の形成に努めてまいりました。
また、国立の女子大学として、女性研究者の支援をはじめ、男女共同参画社会の実現のための取組や提案を行っております。
今回のテーマ「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」では、多くの方々のご協力によりまして、まさに「生活の豊かさを生む新しい雇用システムの設計」に有効な調査と分析がなされていると思っております。
今回のプロジェクトが、確かに、「家族のウェルビーイングとワーク・ライフ・バランス」の在り方を提案し、それが実現に至ることを期待して、ご挨拶とさせていただきます。 本日はまことに有り難うございました。
永瀬伸子 代表研究者 挨拶
今日は、大勢の皆様においでいただきまして誠にありがとうございます。
研究に応募した5年前を思い起こします。5年前は、お茶の水女子大学21世紀COEプログラム「ジェンダー研究のフロンティア」が終了した年です。引き続きジェンダーの視点の学内共同研究をと声があがったことが、この競争的研究資金への応募のきっかけです。
当時、そして今も、私が大きい問題と考えるのは、日本の次世代育成がいろいろな意味で滞っていることです。第1は少子化です。結婚希望は下がってはいないがシングルの男女が増加している。第2は大きい男女賃金格差です。女性の高学歴化が年々進んでいるのですが、驚かれると思いますが、フルタイムで働く大卒女性の半数は20歳代に限定されています。この理由の1つは、女性の多くが出産離職し、大卒女性ほどフルタイムの仕事に戻ってこないことです。さらに最近は、若年層の次世代育成も、人的資本が蓄積されない非正規雇用という働き方が広がっていることで滞っています。
これらは、日本の労働市場の問題ですが、夫婦関係や親子関係の問題でもあります。労働市場のあり方と、家族のあり方、そして子育ては、相互に非常に深く関わっています。従来型の働き方や家族の在り方が、日本の大きなボトルネックになっているのではないだろうか、そのどこに問題があるのか、実証研究をしたいと考えました。
これまでのワーク・ライフ・バランス研究は、企業内の人事制度や働き方としてのワーク・ライフ・バランス研究が多かった。しかし、仕事も大事だけど家庭も大事、子どもも育てたい人々が、仕事と家庭のあつれきを、どうバランスしていくのかということを考えれば、企業だけでなく家庭への視点も重要だと思いました。すなわち労働経済学や労使関係の研究者だけでなく、家族社会学、発達心理学の研究者と協業し、また法政策の研究との協業も大事である。そうした研究者たちと学際的に研究したいと考えたのです。この研究の2つ目の特徴は、女性の経験を大事にするということです。実はこの近未来事業にたくさんのグループが応募したそうで、実際に通していただいたのは4グループですが、女性を主として構成される研究グループは私どもだけです。これまでの学術研究、政治や政策決定の世界でも、女性の経験は十分に反映されにくい構造がありました。女性の経験を大事にしていくこと。私たちの研究グループの中には、ジェンダー法学、ジェンダー研究者も多く含まれています。そして研究だけにとどまらず、現実の社会を変える現実的な提言ができる研究でありたいという思いから、企業の方や労働組合の方、政府や自治体の方々などと交流しながら研究をしてきました。
本日はその成果として、仕事や企業だけでなく家族のウェルビーイング、子どもの良い育ち、女性だけでなく男性も継続的なキャリア形成を実現できる政策を提言していきたいと思います。
- 研究会「非正規労働者と新しい雇用制度を考える」(3)
- 日時2012年12月13日(木) 18時~20時30分
- 会場お茶の水女子大学 本館カンファレンスルーム
- テーマ非正規労働者の賃金
- 講師森ます美 氏(昭和女子大学)「非正規労働者の公正な賃金」
佐藤博樹 氏(東京大学)「人事管理と賃金管理;唯一望ましい賃金管理(賃金制度)は存在するのか?」
「非正規労働者の公正な賃金」
森ます美氏
昭和女子大学 人間社会学部教授 著書『ジェンダー社会科学の可能性 第2巻 承認と包摂へ』(共著、岩波書店 2011)、『同一価値労働同一賃金原則の実施システム』(共著、有斐閣2010)ほか
 非正規労働者の賃金はなぜ低いのか。その主要な要因は、正規労働者と非正規労働者は労働市場を異にすることにある。企業の内部労働市場に属する正規労働者に対しては日本型雇用慣行に基づく企業独自の人事・賃金制度が適用され、日本的能力主義による職能評価と年功的処遇によって賃金が決定されてきた。これに対して外部労働市場におかれた非正規労働者の賃金は、労働市場での世間的相場を反映して決定され、職種別・地域別市場賃率とは言われるものの、その賃金水準は、同一職種の正規労働者の賃率が適用されるわけではない。この低賃金のベースにあるのが「主婦パート」の家計補助的賃金相場で、これに従って今日の非正規全般の低賃金が規定されている。1997年の金融経済危機以降、グローバル競争の進展の中で、コスト高の「男性稼ぎ主」賃金とフレキシビリティーを欠く長期雇用が企業にとって時代不適合となり、その賃金コスト削減のため、非正規雇用化が強力に進められてきた。
非正規労働者の賃金はなぜ低いのか。その主要な要因は、正規労働者と非正規労働者は労働市場を異にすることにある。企業の内部労働市場に属する正規労働者に対しては日本型雇用慣行に基づく企業独自の人事・賃金制度が適用され、日本的能力主義による職能評価と年功的処遇によって賃金が決定されてきた。これに対して外部労働市場におかれた非正規労働者の賃金は、労働市場での世間的相場を反映して決定され、職種別・地域別市場賃率とは言われるものの、その賃金水準は、同一職種の正規労働者の賃率が適用されるわけではない。この低賃金のベースにあるのが「主婦パート」の家計補助的賃金相場で、これに従って今日の非正規全般の低賃金が規定されている。1997年の金融経済危機以降、グローバル競争の進展の中で、コスト高の「男性稼ぎ主」賃金とフレキシビリティーを欠く長期雇用が企業にとって時代不適合となり、その賃金コスト削減のため、非正規雇用化が強力に進められてきた。
非正規労働問題は欧米諸国にもあるが、日本とは問題の争点が異なっている。EU諸国においては、職種・職務給制度が中心で、正規・非正規労働者いずれに対しても産業別に設定される協約賃金が適用されることから、正規・非正規労働者間に基本給についての処遇格差をめぐる紛争はあまり見られない。手当や福利厚生等のフリンジベネフィットをめぐる紛争が中心となっている。これに対し、日本では、正規・非正規労働者間の、とりわけ基本給をめぐる処遇格差が大きな問題となっている。日本の場合は、労働市場の二重性がもたらす賃金格差に対する法的規制が弱いどころか、むしろ労働法によってそれを固定化したとも言える。EU諸国のように、正規・非正規労働者間に、共通の賃金システム(ex.職種・職務給制度)が適用されていないことが根本的な問題である。
本報告での非正規労働者の「公正な賃金」とは、「同一価値労働同一賃金原則による賃金」を指しているが、その「公正さ」とは何か。それは、雇用形態に中立な職務評価によって賃金を決定する同一の賃金制度が正規・非正規労働者間に適用されること、すなわち同一の賃金決定システムの下で仕事を評価することにある。
今後、「公正な賃金」を実現していくうえで、賃金制度設計の発想を転換していく必要がある。具体的には、賃金決定におけるこれまでの「正社員」優位主義、すなわち「典型的正社員」の働き方を基準に、それに見合わないものに対しては賃金の「減点主義」で臨んできた発想を改め、「同一価値労働同一賃金による同一基本給+合理的理由のある加給」による「加点主義の賃金体系」へと移行することを提案したい。同一価値労働同一賃金原則、均等待遇原則の上に立つ男女共同参画社会の形成は、少子化社会到来に向かって猶予のない課題である。
「人事管理と賃金管理;唯一望ましい賃金管理(賃金制度)は存在するのか?」
佐藤博樹氏
東京大学情報学環教授。著書『人材活用進化論』(日本経済新聞出版社 2012)『ワークライフバランスと働き方改革』(共著 勁草書房 2011)ほか
 公正な賃金制度にしなければいけないと思う。ただし、唯一望ましい賃金制度が存在するわけではない。また、無期(正社員)・有期、フル・パートの処遇差の中で、合理的に説明ができない格差がどのぐらいかというのはなかなか難しい。不合理な格差はまず解消すべきだが、パート労働者の職業能力が高まるようなキャリアラダーをつくるとか、能力開発機会を提供しないと、全体としての賃金水準は上がらないと思っている。
公正な賃金制度にしなければいけないと思う。ただし、唯一望ましい賃金制度が存在するわけではない。また、無期(正社員)・有期、フル・パートの処遇差の中で、合理的に説明ができない格差がどのぐらいかというのはなかなか難しい。不合理な格差はまず解消すべきだが、パート労働者の職業能力が高まるようなキャリアラダーをつくるとか、能力開発機会を提供しないと、全体としての賃金水準は上がらないと思っている。
人事管理の世界で職務給や職能給の用語の使い方、つまり賃金決定要素といったときの職務要素や職能要素は何かということを少し整理しておきたい。仕事給や職務給は従事している仕事や職務で賃金が決まるという考え方である。Aという仕事に関して、その仕事を遂行するのに不可欠な最低限の能力は必要だが、Aの仕事に従事している限りその人の能力がそれ以上向上しても基本的に賃金は上がらない仕組みである。他方、職能給は、能力で賃金が決まる。Aという仕事とBという仕事の両方ができる能力のある人(aさん)は、Aという仕事しか担当できない人(bさん)に比べて能力が高いと判断でき、職能給であれば、aさんとbさんの両者が同じAという同じ仕事に従事していても、aさんの賃金が高くなる。この場合、Aという仕事での生産性は、aさんのほうが高くなるような性格の仕事である(能力が向上すると同じ仕事に従事していても生産性が高くなる仕事)。
言い換えれば、Aという仕事を担当して人の能力が高くなっても、アウトプットのレベルが変わらない場合には職務給が合理的となる。他方、Aという同じ仕事を担当している人の能力の違いがアウトプットに差を生む場合には、職能給が合理的となる。そうした場合には、企業は職務遂行能力を高めるように能力向上を処遇に反省する仕組みなどを整備することにもなる。
実際の賃金制度は、100%職務給、100%職能給などはなく、他の賃金決定要素を含めて、いくつかの要素の組み合わせによる。賃金決定要素は、個人が持っている職務遂行能力(発揮可能な保有能力)、従事している仕事内容、実際どういう働きをしたかという発揮された能力、仕事の成果(成果給)などがある。賃金を決める要素は、通常これらの4つである。これらの要素の組み合わせとそれぞれの比重は、仕事の性格に加えて、企業の経営戦略や人事戦略などで決まるものであり、唯一望ましい賃金制度があるわけではない。
有期契約のパート労働者は、一般的には職務で決まる賃金要素の部分が大きい。成果のウェイトも小さい。職務の比重が大きく、職務遂行能力の比重は相対的に小さい。これらのかなりの部分は、仕事の性格と人材活用の方法によるものである。人材育成についても、育成を考える期間は無期の社員に比べれば相対的に短期となる。もちろんキャリアラダーがあるにしても、それほど深くない。賃金額に関しては、外部労働市場の影響が大きい(外部均衡)。
処遇差が問題となるのは、有期契約のパートタイム勤務の社員とフルタイム勤務のいわゆる正社員と、仕事だけではなく人材活用の仕方が全く同じである場合である。同じような仕事や人材活用の仕方であるにもかかわらず、正社員は職能給で賞与もあり、パートは職務給で賞与がない、という事態は合理的に説明できない。その場合、正社員のほうも職務給にする方法、パートについて職能給にする、両者とも第3の賃金制度にするなどいくつか改善の方法がある。
- 講師森ます美 氏(昭和女子大学)「非正規労働者の公正な賃金」
- 研究会 企業の中の「女性活用」取組
- 日時2012年11月20日(火) 10時~12時
- 会場お茶の水女子大学 本館カンファレンスルーム
- テーマワークライフバランスの観点からの「女性活用」について
―会社、上司、女性自身はどうすべきか- 講師銅伝由香氏(㈱JSOL 西日本ビジネス本部 名古屋営業支社長)
- 著書『女性を活用できない会社に未来はない!』(講談社、2008)
 株式会社JSOLでは2006年に女性社員が働きやすい職場作りを目指して女性活用諮問委員会を設立(2012年度よりWoman’s committeeへと発展)。銅伝氏は同委員長を務める傍ら、名古屋営業支社長のベースを活かし、中部地区を中心として女性の活躍推進に関する講演活動を行ってきた。中部地区における取り組みとしては「中部ダイバーシティnet」があり、製造業分野の企業を中心に67企業・団体が所属、企業を超えた情報交換や女性を対象とした研修が企画されている。行政も女性活躍を支援するための取り組みを始めており、名古屋市には「女性の活躍推進企業認定・表彰」、「子育て支援企業認定・表彰」等独自の制度が整備されている。行政表彰を受けた企業は入札時に有利になるなどのインセンティブがあることも、制度の実効性を高める上で重要な点である。
株式会社JSOLでは2006年に女性社員が働きやすい職場作りを目指して女性活用諮問委員会を設立(2012年度よりWoman’s committeeへと発展)。銅伝氏は同委員長を務める傍ら、名古屋営業支社長のベースを活かし、中部地区を中心として女性の活躍推進に関する講演活動を行ってきた。中部地区における取り組みとしては「中部ダイバーシティnet」があり、製造業分野の企業を中心に67企業・団体が所属、企業を超えた情報交換や女性を対象とした研修が企画されている。行政も女性活躍を支援するための取り組みを始めており、名古屋市には「女性の活躍推進企業認定・表彰」、「子育て支援企業認定・表彰」等独自の制度が整備されている。行政表彰を受けた企業は入札時に有利になるなどのインセンティブがあることも、制度の実効性を高める上で重要な点である。












中小企業にはワークライフバランス体制を整備するだけの体力がないという声がよく聞かれるが、愛知県のある企業では現場の女性社員の意見から時間休制度を導入し、働き続けやすい職場を作った例がある。大企業のような制度や委員会がなくても、社長の判断ひとつで実際の現状を理解した働きやすい職場作りができるという中小企業ならではのメリットもある。
JSOL社の女性活用諮問委員会のメンバーは 「良い会社」、働きやすい会社を作りたいというモチベーションを持ち、 メンバー全員がロールモデルとなることをテーマとしている。例えば介護休暇の取得経験がある自分自身が制度を利用しワークライフバランスを保ち、メリハリのあるビジネスライフを紹介することでも、部員も休暇制度を利用しやすい雰囲気を醸成しており、育児休暇から復帰後も、委員会活動を続ける社員もいる。
よい制度を作っても利用されないという問題の解決のためには、「会社・上司・本人」の視点が必要である。本人と上司がしっかりとコミュニケーションを取り、制度や運用方法へとフィードバックすることで、きめ細やかで”、使える”制度を作っていくことができる。また、制度を運用する際に、上司側の性役割分業観がネックになることがある。例えば女性は転勤を嫌がるだろう、といった上司側の思い込みが女性の活躍を妨げる場合がある。 上司と社員のコミュニケーションを密にし、意欲のある女性社員に対しては本人の意志を尊重してサポートするのが上司の役目である。
JSOL社においてはマネジメント層への研修に女性活用に関する項目を組み込み、意識改革をはかっている。また、女性社員と社長・副社長が直接意見を交換できる「レディース会」を定期的に開催している。この取り組みには具体的な女性社員の存在を可視化するという効果もある。
ワークライフバランスの観点から見て、女性のキャリアタイプをいくつかにカテゴリー化し、昇進することだけを目指すのではなく、希望と能力に応じ、適所で最大の力を発揮できるようなキャリアパスを構築することが求められる。
時短勤務の社員への評価に関して、JSOL社ではスキルとパフォーマンスを重視し、上司の裁量で柔軟に評価できるようにしている。時短勤務者へのサポートが大変だという現場の意見については、原因が社員自身のスキルにあるのか、労働時間の短さにあるのかを見極め、それに応じたサポートを考える必要がある。また、業界・業種による働き方の特性を鑑みた人事管理が必要である。
- 講師銅伝由香氏(㈱JSOL 西日本ビジネス本部 名古屋営業支社長)
- 研究会 「女性政策」について
- 日時2012年11月15日(金) 18時~21時
- 会場お茶の水女子大学本館(経済資料室)
- テーマ 「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和―女性労働政策」
- 講師伊岐典子氏
 著書
著書
・『女性労働政策の展開―「正義」「活用」「福祉」の視点から―』日本労働研究・研修機構、2011年
・『大企業における女性管理職登用の実態と課題認識―企業人事等担当者及び女性管理職インタビュー調査―』(労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.105)、2012年
女性労働政策の展開を理解することを目的に、元厚生省雇用均等・児童家庭局長の伊岐典子氏に女性労働政策展開と視点の変化などについて話を伺った。伊岐氏は、前職である労働政策研究・研修機構主席統括研究員時代の著書などに基づき、個人の立場で次のように説明された。












女性に対する労働政策には以下の3つの視点がある。
①男女差別や女性の酷使は正義にもとるという「正義」の視点。
②経済社会の発展のため女性労働者を「活用」すると言った視点。
③女性の幸せが増大することがのぞましいといった「福祉」の視点。
歴史的にみると、戦後の女性労働政策は「正義」視点で始まり、その中でも厳しい労働環境の中女性を保護する視点が強かった。その後1952年ごろから「福祉」視点、「活用」視点が登場した。1975年国際婦人年以後は「正義」視点の中で保護から平等へのパラダイム転換があった。男女雇用機会均等法が施行された1986年から2001年までは、「活用」視点が顕在化して継続雇用を目的とした育児休業法が成立し、育児介護休業法に発展したり、「正義」視点の平等が進んで男女雇用機会均等法が強化された。この時期が、女性労働政策の歴史の中で最も華やかな時期であった。2001年以降は「福祉」「正義」両視点の政策の充実と共にその政策効果が問われた転換期であった。特に「福祉」視点の広がりは目覚しく、この視点から育児介護休業法はたびたび改正され制定当初は17条であった法律が、68条にまで膨らんだ。少子化を背景に両立支援策が重視されたこともある。
1986年施行の男女雇用機会均等法は、それまで啓発が中心であった行政組織(当時は「婦人少年室」現在は「都道府県労働局雇用均等室」)の質的変革をもたらし行政権限行使ができるようになった。このことが、育児介護休業法、パートタイム労働法に関してもこの「室」を施行機関とする前提での立法につながった。
2007年のワークライフバランス憲章策定(2010年改定)以降は、女性「活用」の視点も背景に、女性だけでなく男女にとってのワークライフバランスが強調されるようになった。 2012年になると「女性の活躍による経済活性化」行動計画(働くなでしこ大作戦)がスタートし、女性活用のポジティブアクションがようやく注目されるようになった。
これまでの経緯から、女性政策が発展するのは、女性「活用」の視点があるときであるということができる。現在の女性活躍促進施策強調の背景には、これまでの両立支援策の充実だけでは必ずしも女性の就業継続につながっていないという反省があると考えられる。
女性の就業継続を実質的に確保するためには両立支援による働きやすい環境づくりのみならず、女性が高いモチベーションを維持できるような支援、実質的に職場での女性の地位を上げるための方策が重要であると考える。相互に有機的に関連付けられた両立支援政策と均等政策の推進が求められている。
- 研究会「非正規労働者と新しい雇用制度を考える」(2)
- 日時2012年11月8日(木) 18時~21時
- 会場お茶の水女子大学 本館カンファレンスルーム
- テーマ非正規雇用とジェンダー
- 講師脇田滋氏(龍谷大学)「派遣労働とパート労働」
今野久子氏(弁護士)「パート労働とジェンダー」
「派遣労働とパート労働」
脇田滋氏
龍谷大学教授 専門は労働法、社会保障法。1996年から派遣労働者の悩み相談のHPを開設。
 ◆日本の労働者派遣法は悪法である
◆日本の労働者派遣法は悪法である
本来、派遣の仕事というのは、テンポラリー(臨時)ワークであり、雇用期間はふつう数か月というような短いものである。日本のように26業務※にあるよう長年勤務しているケースは世界でも珍しい。だが、日頃、派遣労働者からの悩み相談を受ける中で一番多いのは、雇止め、中途解約のことだ。派遣先の企業は、直接雇用でない労働者に対し、痛みを伴わずに雇止めすることが可能だ。派遣労働者には組合の組織がなく、既存の労働組合にも入れないこともほとんどであり、雇止めや解雇が怖くてものを自由に言えないということも珍しくない。
ここ数年、男性の非正規労働者が増え、ワーキングプアの問題として取り上げられているが、こうした低賃金の問題は元をただしていけば、日本的雇用慣行という世界に例のない特殊な労働政策の裏返しにあると考える。そこには男性を一家の稼ぎ手モデルとし、女性を家計補助的な派遣労働者化するという、性差別もあったと考える。1985年に派遣労働法が成立されたことで、こうした働き方が制度化され、ますます強化された。これは悪法と考えている。
◆EUや韓国並みの均等待遇を目指す
EUでは同じ職務であれば均等待遇が原則だが、日本では差別的な取扱いが残る法規制になっていることが問題である。さらに雇用の不安定な人が低待遇であるのはおかしく、むしろ不安定雇用手当をつけるべきと考える。
韓国の動きを紹介する。2006年、弁護士出身のノ・ムヒョン政権時代に非正規職保護法が改正されて、有期契約者、短時間・派遣労働に共通して、賃金その他の勤労条件などにおける差別を禁止する規定が出来た。これには派遣元と派遣先両方が努力義務を負う。また雇用期間が2年を超えたときは無期契約とみなす処置も盛り込まれた。最近でもソウル市の非正規職員1000人あまりが正規職員になるなどの事例もある。
※26業務 労働者派遣法の施行令で定められた「派遣期間制限の無い26種類の業務」のこと
2004年施行の改正法で期間の制限が撤廃された。
「パート労働とジェンダー」
今野久子氏
弁護士。丸子警報器差別事件など多くの労働裁判に多く携わる。全国のパートタイマー問題について各地を回り勉強会を行った。
 ◆基幹化するパート労働者
◆基幹化するパート労働者
日本ではフルタイムパート、疑似パートというようなおかしな言葉があるように、パートタイマーの労働実態は大変厳しい。しかも、平均賃金もここ10年変わらず待遇は低く抑えられている。地方へ行くと、経済が落ち込んでいて、最低賃金を下回る時給で働いているケースもある。日本のパートタイマーの能力水準は高いものと思う。本当によく働くなと感心する。しかし、雇用保障はなく不安定であり、そうした中で将来の展望が持てないという若い人たちも多い。これは日本社会にとって大きな問題ではないだろうか。
ではなぜ、パートで働くのか、と聞くとパートを選ばざるを得ない理由がある。正社員の長時間労働が原因で家庭的責任を負わざるを得ない女性たちにとっては、家族の都合にあわせながら働く時間を選ぶからである。するとどうしても短時間であり、職場も近いところとなりパートになってしまう。また最近では、働きたくても正社員の働き口がないという理由もある。しかも公務の職場でも非正規化がどんどん進んでいるのが現状だ。
◆法改正に注意
パートに対する不利益取り扱い事件を長年裁判で扱ってきたが、日本では、非正規労働者が仕事をしているときは、解雇されることを恐れて、不満や権利を言うことがなかなか難しい。仕事をやめて、それで裁判になってようやく明るみになる。それほど裁判を起こすのは大変なこと。丸子警報器事件※1の時は、原告団が「孫の代まで差別を残したくない」という強い思いで立ち向かったことに、とても感動したことがある。2007年にパート労働法改正があり、差別的取扱いの禁止(パート法8条1項)※2が盛り込まれたので、画期的なものと思ったが実効性に欠けた。この要件で実際に救済できる対象者は統計的にみると、絞り込まれてしまい0.1%ほどである。残り99.9%の人たちの改善についてどう進むのか、今後の法改正の動きを注意する必要がある。
※1 丸子警報器差別事件 長野地裁上田支部平8.3.15判決(労判690号32頁)
正社員と同じ時間・同じ仕事をしているパートタイマー「特殊従業員」の賃金差別について争われた事件。女性正社員と職種、作業の内容、勤務時間及び日数等が同じ「臨時社員」について、賃金が正社員の賃金の8割以下となるとき、公序良俗違反として違法であるとして、差額分の損害賠償を命じた。
※2 差別的取扱いの禁止(8条1項)
通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止とは
通常の労働者と
ⅰ)職務内容(業務の内容及び責任)が同じ
ⅱ)人材活用の仕組みや運用(人事異動の有無及び範囲)が同じ
ⅲ)契約期間が無期 (又は実質的に同じ) である条件としている。
- 講師脇田滋氏(龍谷大学)「派遣労働とパート労働」
- 研究会「非正規労働者と新しい雇用制度を考える」(1)
- 日時2012年10月19日(金) 14時~16時
- 会場お茶の水女子大学 本館カンファレンスルーム
- テーマ非正規労働者の均等待遇
- 講師浅倉むつ子氏(早稲田大学) 「雇用における均等待遇原則をどう実現していくべきか」
水町勇一郎氏 (東京大学社会科学研究所)「非正規労働者と均等待遇をめぐる理論と政策」
「雇用における均等待遇原則をどう実現していくべきか」
浅倉むつ子 氏
早稲田大学教授 専門は労働法、ジェンダー法。
著書『同一価値労働同一賃金原則の実施システム』(有斐閣,2010年)ほか
 ◆崩れる日本的雇用慣行
◆崩れる日本的雇用慣行
日本企業は、非正社員を、正規社員の長期安定雇用を保障する不可欠な存在としてきた。しかし、両者間の取扱いは、大きく異なる。そして、今や、雇用の複線化、多様化、流動化、規制緩和が進み、正社員であっても決して安泰ではない時代になった。日本的雇用慣行とその背景にある、「男性稼ぎ主型」のモデルは、男性世帯主の非正規化が進み虚像化している。ところがジェンダー差別は温存・強化され、一向に変わらないところが問題である。
労働法をはじめとするジェンダー関連の法改正は、頻繁に行われてきたが、法改正をもたらした要因は、「規制緩和」と「少子化対策」である。今日のテーマである「均等待遇原則」について言えば、97年の均等法改正後も、指針は「雇用管理区分」ごとに差別的取扱いを判断し、雇用管理区分が違う男女間では男女差別を争えなくしている。この「雇用管理区分」ごとの比較を前提としていることが、均等待遇原則を大きく機能させない理由の一つである。それだけに、法改正が行われても、女性に対する差別的実態はあまり変わらない。すでにILO(国際労働機関)第100号条約(同一価値労働同一賃金原則を定めている条約)を日本は批准しているが、「同一価値労働同一賃金原則」を明記する法改正の措置は取られていない。労基法4条の規定は、同条約そのものを履行するには不十分である。
◆「同一価値労働同一賃金原則」実施が鍵
さて、正規・非正規に関する均等待遇原則の手掛かりになる条文は、パート法9条の「均衡処遇原則」(努力義務)とパート法8条の「差別待遇禁止」である。しかし、法には、パートの職務と正社員の職務の価値を比較する手立てが、具体的に示されていない。
格差を解消する一つの鍵となる考え方が、「同一価値労働同一賃金原則」である。同一価値労働同一賃金(職務が違ってもそれぞれの職務の価値が同じであれば、同一賃金が払われるべきという考え方)の尺度は、「職務」「仕事」であり、多くの日本企業がこれまで採用している職能基準とは異なるからだ。
私は、日本の企業に、同一価値労働同一賃金原則の基礎である「客観的職務評価制度」を実施するように推奨する制度、「平等賃金レビュー」を提案したい。同一価値労働をしている男女間の賃金格差を、段階的に企業が解消していくという制度である。労働を比較するときには、「得点要素法」を採用することがポイントである。これは、ILOも客観的・分析的な職務評価としているもので、4大ファクター(1知識・技能、2肉体的・精神的負荷、3責任、4労働環境)を細分化させ、労使の話し合いの下に点数を設定してくやり方である。また、裁判に関しては、職務評価の専門家に、裁判所が、職務の価値評価を委託できる制度を作るべきだ。
「非正規労働者と均等待遇をめぐる理論と政策」
水町勇一郎氏
東京大学 教授 専門は労働法。
著書『非正規雇用改革―日本の働き方をいかに変えるか』(鶴光太郎氏・樋口美雄氏との共編著)日本評論社 ,2011年)ほか
 ◆「均等待遇」をめぐる法政策―日本の非正規労働法制の動向
◆「均等待遇」をめぐる法政策―日本の非正規労働法制の動向
最近の法改正の動きを紹介する。今年(2012年)の8月に労働契約法改正が成立し、3つの条文が追加されることとなった。その中で特に大きく取り上げられているのは、労働契約法の18条(2013年4月1日施行)で、有期労働契約が5年超えると無期契約に転換が可能である「無期労働契約の転換」である。来年4月施行にあわせて、5年のカウントが始まるため、現在企業のほうでも取組みを検討しているところである。もう一つ、「期間の定めがあることを理由とする不合理な労働条件の禁止」(労働契約法20条)については、今後の非正規問題についての大きな意味を持つ潜在的な可能性があるかもしれない。ここでの最も重要なポイントは、不合理であるかどうかは、「個々の労働条件・待遇ごとに個別に合理性を判断する」ということ。パートタイム8条にも、3つの要件を満たした人はすべての労働条件について差別禁止という規定ではあるが、3つ全ての要件を満たさないと適用がなされないので、いわば「100かゼロ」の世界だった。したがって、今回の改正は、個々の給付(たとえば、基本給、賞与、退職金などの個別の労働条件)に基づいて判断する点で、これまでとは異なる。厚労省の通達では、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理については労働条件の相違があってはならないとしている。
◆残された課題 均等待遇と均衡待遇の整備
欧米では差別禁止と平等取扱いは、別のものになっていてはっきりと分けているが、日本では必ずしも別に扱われていない。かつ、努力義務でバランスを取るという「均衡」の話が出てくるのは日本だけである。しかし、正規と非正規の置かれている状況が日本と欧米とでは違う。日本では社会の構造や正社員中心の取扱いのなかに非正規があるという状況では、均等にすることは難しいため、そのバランスをとるために均衡をとる。均等と均衡の中身を今後よりきちんとしたものにするためには、企業は自主的に行動計画という形で推進していく事、国は推進するために政策的なインセンティブをつける事、さらに、労使の現場の間で非正規労働者も含めた話し合いをしていく事、このようなインフラや政策の枠組みをきちんと作って均等と均衡を取り上げて、中身を作りあげていくことが大事だ。
- 講師浅倉むつ子氏(早稲田大学) 「雇用における均等待遇原則をどう実現していくべきか」
- 研究会「有期契約労働と育児休業―労働者調査から―」
- 日時2012年7月27日(金) 18時~21時
- 会場お茶の水女子大学 本館大会議室
- テーマ「有期契約労働の育児休業―ヒアリング調査結果から―」
「非正規労働者の出産退職状況-『女性の働き方と家庭生活に関する調査』の分析結果から-」 - 講師池田心豪氏(労働政策研究・研修機構 副主任研究員)
- 労働政策研究・研修機構(JILPT)では、2005年施行の育児・介護休業法で新たに育児休業の対象となった、有期契約労働者の育児休業の現状と課題を明らかにするため、企業5社と有期契約雇用者2名にヒアリング調査(2006年~2007年)を行った。
調査の結果、育児休業対象者要件の「子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと」は、特段の事情がない限り、契約更新している場合は該当しないため、実際には考慮されていない。問題なのは「子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること」という要件である。見込みがあるのか、ないのかは、客観的な判断が難しい。そのため、この要件については、自社の規定から外しているか、規定があっても労働者本人に継続意思があれば休業を認めているとする企業が多かった。
ヒアリングを行った企業からは、有期雇用者に対する育児休業制度導入のメリットについて以下のことがあがった。
○採用競争で有利になり、人材確保の点でメリットがある(小売業・派遣業)
○意欲・ノウハウ・経験のある有期雇用者が育児休業後も働くことは、企業・本人双方にメリットがある(小売業)
○業態として、消費者は女性であるため、有期・無期にかかわらず女性が結婚・出産してもやめずに働き続け、基幹的業務を担うメリットは大きい。(小売業) ○雇用保障の点で、育児休業制度は自社の強みを補完(派遣業)
2010年にJILPTが実施した『女性の働き方と家庭生活に関する調査』では30-44歳の女性を対象に、職歴、婚姻歴、育児歴、両立支援の利用状況等を調査した。(回答1240人; 回収率62%)その中で、非正規労働者の出産退職状況について明らかになったのは以下のことである。
○2005年以降、有期契約であるか否かに関わらず、第1子妊娠時の勤務先に育児休業制度があったという非正規労働者の割合は上昇している。
○第1子妊娠・出産期の女性に占める育休取得者の割合は上昇傾向にあるが、未だ水準は低い。
○非正規労働者の企業定着と職域の拡大が、出産退職率低下の背景にあるが、産休制度が「ない」という比率も高く、出産退職率を高い水準にとどめている。
育休制度が整っていない会社では、就業規則が「ない」ことが多い。例えば、30人以下の小企業などにそのようなケースが見られる。基本的な労働法制を守らせることは今後の重要な課題である。いろいろな規則を作っても無視されることがあり、産休、育休がないことが明るみに出れば注意を受けるが、日本はそもそも労働基準監督官の数が少なく、その実態を把握しきれていない。
また企業の行動をチェックする組織として労働組合の役割も重要であるが、育休制度を含めた女性労働問題に、日本の労働組合が熱心に取組んでいるとはいい難い。賃金上げは組合員みんな関心事であるが、子育て支援は対象が限られる。当事者である子育て期の女性にとっては切実だが、独身者や子育てが終わった女性の関心は薄いということも珍しくない。そのため、組合の活動方針として子育て支援に優先的に取組むということになりにくい。
今後の政策においては、企業だけでなく労働者にも働きかけていくことが必要なのではないか。企業に働きかけ、企業の行動を規制することにこだわりすぎていないか。それよりは、学生に対して、どういう企業を選ぶかといったキャリア教育など、労働者個人に働きかける方が効果的な場合もある。こうした点から労働者に対する情報提供が必要である。日本の雇用慣行では、労働契約がはっきりしておらず、入ってみないと産休や育休がきちんとあるかどうか、どんな休暇制度があるか、さらには初任給でさえもわからないことが多い。こうした情報を正しく知ることが大切であるし、女子学生にはこのような知恵をぜひ身に着けてもらいたい。
講師 池田心豪さんプロフィール
参照: JILPT 労働政策研究報告書 No.150 (2012) 『出産・育児と就業継続』
- 研究会「意思決定の場に多くの女性を~140名の働く女性インタビューから~」
- 日時2012年7月19日(金)18時~21時
- テーマ「意思決定の場に多くの女性を~140名の働く女性インタビューから~」
「非正規労働者の出産退職状況-『女性の働き方と家庭生活に関する調査』の分析結果から-」 - 講師越堂静子氏 (ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク WWN代表)
- この研究会は、日本の女性正規社員の現状を理解することを目的に、報告者であるワーキングウィメンズンネットワーク(WWN)代表の越堂静子氏に、働く女性を対象にしたインタビュー調査から、女性が管理職を希望しない理由や背景についてお話しいただきました。
?WWNは1995年、住友メーカー男女賃金差別の裁判支援を契機に発足したNGOである。同一価値労働同一賃金の明文化、ジェンダー中立な職務評価の確立、間接差別の禁止(コース別制度の廃止)を目的とし、主に国際機関への発信、ロビーイング活動、メディアとのコラボレーション、国会議員、各省庁との 意見交換を行っている。国連やILOに訴えて、その力で国会議員、省庁に訴えて、メディアに取り上げてもらうなど、精力的な活動を続けている。代表者である自身も、長年のキャリア経験をいかし女性の地位向上に向けた活動をライフワークと位置付けている。
?雇用均等法では第5条(採用)、第6条(昇進・昇格)で性別を理由とする差別禁止を規定している。しかし、また指針においても、一の雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態 等)での差別的な取り扱いは禁止すると規定された。ここに「職種」とは、総合職、一般職のことをいうと記載され、コースが違えば男女差別を問われなくなり、企業に「コース別制度の導入」の道を開いた。このコース別制度により、コース別のある企業の総合職女性は5.6%(2010 年)に過ぎず、多くの女性は一般職という性差がある。これは均等法が成立した25年前からほとんど変わっていない。総合職の女性は均等法6条によって、昇給、昇進するが、100%女性で占める一般職の賃金は低いまま推移している。
この事は、下記のように2009 年、CEDAW(女性差別撤廃委員会)からも懸念事項がだされている。
「とりわけ、雇用機会均等法に基づく指針の「雇用管理区分」、女性を差別するコース別制度を導入する余地を雇用者に与えているかも知れないと懸念している。」
こうしたコース別は間接差別であると、WWNは政府に均等法改正を提案し続けている。
?「意思決定の場に多くの女性を」と政府に出された国連・CEDAWのフォローアップ項目を受けて、NGOとしてもレポート作成のためWWNは数回の勉強会を経て、企業で働く正規社員女性140名への実態調査を実施した。しかし女性の正規社員、かつ管理職を目指せるような立場にある女性を見つけること自体が困難であった。インタビュー調査結果は以下のとおりである。管理職を「希望しない」は45%、「希望する」は33%であった。希望しないと 回答した職種で一番多かったのは、一般職で77%であった。「管理職になるにあたり何が不安か」を尋ねたところ、コース別がない企業に勤める女性において は、“長時間労働”、“人間関係が大変”、“仕事と生活の両立”が挙げられた。一方、一般職の女性が挙げた中では“訓練や経験の不足”が一番多く、一般職 にはキャリア登用への訓練がされていないことがうかがわれる。
参考:ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク(WWN)
- 公開講演会「日米のワークライフバランス」
 日時2012年7月2日(月)18:00~21:00
日時2012年7月2日(月)18:00~21:00- 場所お茶の水女子大学 理学部3号館 701号室
- 司会申キヨン氏(お茶の水女子大学 准教授)
-
■講演要旨
■ 「米国における家族と仕事の変化 ~進歩と課題~」
Upjohn Institute for Employment Research シニアエコノミスト
スーザン・ハウスマン 氏
 統計データを用いながら、米国における女性の就業の変化について説明。女性が男性に比べ教育水準が高いこと、労働市場参加の男女差はほぼ均衡なこと、明白な雇用差別は縮小しているものの、シングルマザーが多いことや出産年齢は上昇していることが挙げられた。
統計データを用いながら、米国における女性の就業の変化について説明。女性が男性に比べ教育水準が高いこと、労働市場参加の男女差はほぼ均衡なこと、明白な雇用差別は縮小しているものの、シングルマザーが多いことや出産年齢は上昇していることが挙げられた。
また米国では、男女賃金格差や性差別は縮小し、高収入の職への女性の就業の拡大も進展した。しかし課題が残されていないわけではない。米国でも20代後半以降には男女賃金格差が大きくなることから、家族のケア責任を女性が負担しているとみられている。また、シングルマザーの労働時間はそうでない者よりも相対的に長い。
家族責任をとる例では、専門性の高い医師として働く女性であっても、開業を避け、夜間診療や緊急呼び出しが少ない条件の仕事を選ぶということもある。米国でも、今なおファミリー・フレンドリーな職場をつくるには、古い職場のしきたりを変えないとならないと考えられている。
今後の課題として、依然としてファミリー・フレンドリーな職場が少ないこと、低学歴・非白人の女性の多くが、子育てをしながら生計をたてる中で貧困・福祉依存に陥っていることなどを解決することが求められている。
■「日本女性のキャリアと出産 ~両立の現状と課題~」
お茶の水女子大学 教授 永瀬 伸子 氏
「女性のキャリア形成」について、2010 - 2011年度に日本とアメリカで量的調査を行った。両者を比較すると、日本の方が、結婚を境に、さらに出産を境に働き方が変わる度合いが大きい。これには日本の正社員の退社時間が、①米国よりも大幅に遅いこと、②日本の方が仕事の融通が利きにくいこと、③企業を超えて仕事の専門性が評価されにくいことがあると思われる。また、学生時代に女性も稼得役割を持つべきと学んだ者の割合は米国より大幅に低く、いったん無業になった有配偶女性は、日本では就業しても130万円以下の年収が約7割と、米国よりかなり低所得である。これは社会保障や税制の壁に代表されるように、既婚女性は家計補助者でよいという社会的な暗黙の合意が大きいと思われる。
では、日本で女性が大企業の管理職となるための条件は何か。質的調査から得られた成功要因を挙げると、●大学卒業時に就業意識が高いこと、●20歳代で仕事に打ち込む経験を持つこと、●夫が妻の就労を後押すること、●夫が家事育児に協力すること、●本人が上司や同僚と高いコミュニケーション能力を持つこと、●出産前に一定の業績を挙げ、出産後も必要であれば残業できる体制を整えていることなどがあった。米国の質的調査でも、管理職として成功するための共通点は多いものの、米国は中途入社であっても、また入社時は低学歴であってもその後の状況によって大企業で昇進するチャンスがあることが、日本とはかなり異なる。
日本で実施したWEB調査から、日本で有配偶女性が正社員継続できる要因を分析すると、妻の職場の男女の均等度とファミフレ度が高いだけでなく、夫の職場のファミフレ度が高いこと、加えて妻が働くことに夫が賛成し、家事育児に参加することが重要だった。夫婦双方にとって妻が働くことが良い選択と認識されなければ、妻が正社員として就業継続するのは難しい。総務省『労働力調査』の大規模標本の分析をしたところ、2000年以後の不況において、男性の雇用状況がこれまで以上に悪化していることにより、女性が仕事を持つことでリスク分散の必要性が高まっていることが示された。
これらの研究結果から、普通の夫婦が子どもを持ち、仕事をお互いに続けられる環境の整備と、男性が仕事と生活を調和できる環境の整備が必要という示唆が得られた。
■「家族責任差別 Family Responsibilities Discrimination
~ ワーク・ライフ・バランスの課題解決にむけて ~」
カリフォルニア大学ヘイスティング法科校 教授 ジョアン・ウィリアムズ氏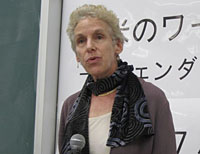
日本や米国の白人における出生率低下の原因のひとつは、子どもがいることが働くことの障害になっていることである。育児を担う母親が12時間以上働き続ける理想の働き手にはなり得ないため、良い仕事を得ることはできないし、逆に、長時間働く良い働き手になったら、今度は悪い母親であると言われてしまう。母親というものへの偏見が働き続けることの障害になっているのである。また、男性が育児に参加するために仕事を休むと、男らしくないと言われるような職場が存在している。育児をする男は悪い働き手、「女性っぽい」という烙印(スティグマ)を押される。つまり、仕事には、効率ではなく、男らしさが要求されるのである。
このような問題を解決するための方法をいくつか提示する。ひとつは、米国政府のように育児休業取得者に対して報復してはいけないというキャンペーンを展開し、性差別を禁ずる法律を作り、厳しい罰則を設けることである。育児休業をとれないような企業は告訴される。2つ目は、スウェーデンなどのように、女性が公的部門で働き、未就学児がいる間は時短勤務をしやすい職場にすることである。3つ目は、オランダのように、働く時間を自由に決められる権利を労働者に与えることである。
家庭での性別役割分業を変えるには、職場を変えることが必要である。職場の働き方を変えて、女性が差別されることがないようにしなければならない。そうしなければ、離婚したときなど、女性と子どもが貧困に陥ることになるだろう。また、このような変化なしでは、男性も、ワーク・ライフ・バランスを実現することはできない。
■コメント 内閣府男女共同参画局 推進課長 小林洋子氏
 講演者の報告にあったように、女性への家事・育児負担の偏りが男女の賃金格差につながっているのは、日米共通の課題であることがわかった。日本のWLB政策としては、育児休業法や労働基準法の改正により、男性の育児参加促進、長時間労働の抑制を進めている。ワーク・ライフ・バランス行動指針に3つの柱があり、その一つに、シングルマザーの経済的自立のための就業促進も入っている。
講演者の報告にあったように、女性への家事・育児負担の偏りが男女の賃金格差につながっているのは、日米共通の課題であることがわかった。日本のWLB政策としては、育児休業法や労働基準法の改正により、男性の育児参加促進、長時間労働の抑制を進めている。ワーク・ライフ・バランス行動指針に3つの柱があり、その一つに、シングルマザーの経済的自立のための就業促進も入っている。
また、講演者に対してフレキシビリティのある働き方というのは、どのようにすれば可能か、柔軟な働き方の一つである短時間勤務に対する人事評価はどうするのかという質問がなされた。ハウスマン氏からは、二人で一つの仕事をすること(ワークシェアリング)や在宅勤務を取り入れることで可能である、永瀬氏は、日本においては、正社員の人事制度が画一的であることが問題であるので、これを柔軟なものに変えること、ウィリアムズ氏は、長時間仕事をするのが正社員であるという定義を変えるべきとの回答がされた。
■会場からのご質問と回答
Q. 企業につとめる女性。企業はワーク・ライフ・バランス制度を整えてはくれるが、実際には労働者が使いにくいことがある。これはもしかすると、女性に専業主婦を望み、男性の働き方も変えないといった古い考え方のままだからではないか、と思っている。アメリカでも同様なことがあるか?また、こうした伝統的な考え方はどのように変えることができると思うか?
A. ウィリアムズ氏
アメリカでも、伝統的な考え方を持った世代と若い男性たちの間でのギャップはある。企業がそうした世代間ギャップが広がらないように、間をうまく取り持つようにする努力はすべきだと思う。なかなか考え方が変わらないというのは、「成功を収める男性はこうあるべき」と固定概念が以前あったと思うが、今は、家族的責任をとり、育児も行い、「よき父親になりたい」と思う男性が増えてきている。こうした新しい世代の人たちをサポートする仕組みを作っていくことが必要。
ハウスマン氏
アメリカでは連邦政府、州政府がリードを取って、公共政策の一環として女性にいい職を与えるようにした。より寛大に休暇取得を促進し、男女ともに育休を与え、在宅勤務も行うなど、政府として模範となること大事。
Q. 小学校教員の男性。日本の男性は、「育児」という言葉より、「子どもと生きる」という概念だと意識も変わってくるかもしれない。小学校の早い段階から、学校の授業でこうした意識を取り入れてほしい。
A. ウィリアムズ氏
日本男性の家事・育児にかける時間は国際的にも少ない。より関与を増やすアプローチとして、男性にはっぱをかけて促す方法もあるが、職場自体を変えるほうが効果はあるだろう。
ハウスマン氏
私のところの職場(研究所)でも韓国人の研究者がいるが、韓国に比べて働く時間がフレキシブルになり子どもと触れ合う時間が多くなったと喜んでいる。
・司会者・講演者からのひとことメッセージ
申氏
講演者の報告からあったように、アメリカでも短時間労働制度を利用した場合に、フレキシビリティ・スティグマ、まともな労働者でない、という偏見があり、差別的な扱いを受ける。制度だけではなく職場そのものの変化が必要だとわかった。
ウィリアムズ氏
日本は出生率の低さがいかに深刻であるのかということを重視して、本気で職場を変えるべき。
永瀬氏
今、雇用が正規と非正規にどんどん分かれている。少ない椅子の正規になっても長時間労働となってしまう。新しい働き方を作って行かないといけない。皆さんが一人一人、職場でも取り組み、私たちも発信していき、政府も取組んでほしい。
ハウスマン氏
なかなか物事が変わっていかないように見え、ストレスも感じるかもしれない。しかし、自分が日本に初めて来た20年前に比べると、女性の社会進出には大きな変化があったと感じている。
シンポジウム『日米のワークライフバランス』の様子がお茶の水女子大学 広報誌 GAZETTE11月号「キャンパス点描」に掲載されております。
- 公開研究会「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」
- 日時
 2012年7月1日(日)10:00~18:00
2012年7月1日(日)10:00~18:00 - 場所お茶の水女子大学 理学部3号館 701号室
Session1 家族的責任をとる労働者に対する法政策
■「家族責任差別 Family Responsibilities Discrimination」
カリフォルニア大学ヘイスティング法科校 教授 ジョアン・ウィリアムズ氏
家族責任差別とは、性別に関係なく、育児や介護など家族ケアを担う人々へ向けられる職場での不当な扱いのことである。米国社会においては「選択と責任」という名のもとにワーク・ファミリー・バランスがないがしろにされてきた。米国社会における「理想的な就業者」の条件は会社に忠誠をつくすである。一方で「理想的な母親」の条件とは家族が必要とする時、いつでもそばにいられるである。このような社会的理想の衝突は、男女ともにネガティブな影響を生じさせ、特に母親の就業を困難にさせることによって子どもの貧困が引き起こされる。
職場では母親であるというだけで能力が劣ると見なされている。こうした固定観念が差別と結びついていることは、母親の賃金や採用率、昇進率といった具体的数字をもって知ることができる。
家族責任差別に関する訴訟は1980年代から増加し、2004年までで1500件以上にのぼる。特徴的なのは家族責任差別に関する訴訟での原告側労働者の勝訴率は50パーセント以上であり、これは他の差別に関する訴訟と比較して高い勝訴率といえる。
このような背景もあり、米国雇用平等委員会(EEOC)は2007年にケア責任をもつ就業者に対する不法な取り扱いを是正するための指針をまとめている。-
■ 「家族的ケア責任を有する労働者に対する日本の法制度」
日本大学 教授 神尾真知子 氏
家族的ケア責任を負う労働者に対する育児サービスや育児休業制度は、その取得の選択肢が限られ、また経済的補償がなく、取得要件が厳格等の理由から、女性を中心とした非正規雇用労働者が利用しにくいものとなっている。こうした現状から、日本の法制度の課題として、①適切なニーズを把握していくこと、②今後、保育サービスと育児休業の組み合わせについて議論すること、③家族ケア責任を有する労働者に対し、量的・質的に充実した選択肢を用意すること、④育児のための短時間労働勤務を労働者の権利とすること、⑤育児休業と育児休業給付が制度として連動することをやめること、⑥ひとり親に配慮した育児休業制度にすることが挙げられ、これらが実現できれば、家族的ケア責任を負う者が利用しやすい法制度となるであろう。
※神尾真知子先生が今回の「家族的責任差別」についてお書きになった記事が、『労基旬報』(7月25日号)に掲載されています。⇒ アメリカの新理論『家族的責任差別」
■コメント■労働政策研究・研修機構 主任研究員 池添 弘邦氏
主に国の規制権限、法制度の相違から、本問題に係る日米の隔たりは大きいように見える。アメリカでは市場経済を優位に捉える考えが根強いこと、議員立法が中心であること、さらに、労働者保護について必要な手当が講じられているものの、差別禁止法を除けば限定的であることがその理由として挙げられる。日本はアメリカと異なり、どちらかといえば欧州に類似した政策を推進し、国は社会情勢に応じた政策立法を行ってきており、労働者保護は相対的に手厚い。このようなことから、本問題について、日本は雇用政策的アプローチを取り、アメリカでは性差別禁止アプローチを取ってきたという相違がある。また、アメリカでは、事後救済として固定観念を根拠とする損害賠償請求訴訟が可能であり、陪審評決においては高額の賠償金が認められている。一方、日本では、雇用機会均等法が数次の改正により性差別禁止法となり、また、育児介護休業法は権利行使を理由とする不利益取扱いを禁止している。東朋学園事件最高裁判決*は、労働者の権利行使を著しく抑制する取扱いを公序良俗違反と判断し、事後救済が可能であることを示した。以上から、立法、司法判断を全体的に見ると、この問題に係る日米の法政策は機能的には等しいと評価できるように思われる。もっとも、仔細には、日本にはどのような法的課題があるのか、すなわち、雇用機会均等法と育児介護休業法それぞれについてどのような法的課題があるのか、また、性差別禁止と育児介護休業とを車の両輪として機能させるべく両法を接合しうる法政策とはどのようなものであるのかについて、育児介護休業給付や保育サービスのあり方などを視野に入れつつ、今後更に検討していく必要があろう。
*東朋学園事件最高裁判決…育児休業取得者の賞与不支給をめぐり最高裁で争われた事件。
Session 2 家族的責任をとる労働者に対する法政策
家族的責任をとる労働者に対する法政策
■「女性の雇用、出産と賃金」 お茶の水女子大学 教授 永瀬 伸子 氏
日本では1985年の均等法の実施やその後の改正、育児休業法の拡充を経た今でも、出産後の状況を見ると、仕事を続ける女性の割合は増えてはいない。代わりに増えているのは出産を遅らせる女性、子どもを持たない女性である。こうした変化を分析するために、本プロジェクトでは個人及び企業を対象にしたインタビュー調査、個人への大量調査を実施した。
女性が出産後も働き続けるためには、学卒時から働き続けることを意識していること、出産前にキャリアを一定程度形成していること、夫のサポートがあること、が重要と、大企業の管理職女性へのインタビューから分かった。また、企業インタビューから、日本の女性が管理職になりにくい理由の1つは、中途採用が少ないため、同じ企業に働き続けないと管理職候補にはなれないという人事制度の硬直性があるとわかった。
女性が結婚後仕事を辞めてしまったり、パート等の非正社員を選択したりする理由を、仕事と家庭の両立が難しいからではないかと、全国調査データを分析した。その結果、女性が出産後も働き続けるためには、ファミフレな職場であること、それは本人だけではなく夫についても重要なことが示され、またそもそも正社員で採用されなければ育児休業制度は利用できないことなどが問題として示された。また出産後の仕事の継続が当たり前の慣行とはまだなっていない中、企業でWLBのための制度が整っている方が、育児休業とその後の仕事の継続に希望をつないで、女性が出産時期を遅らせる(が必ずしも続けられない)という傾向も見出された。
女性の出産の機会費用を下げるには、育児休業制度を非正社員に対しても利用しやすくすることが必要である。またいったん離職した者も再就職が容易になるような政策が必要である。
■「シングルマザーの貧困:「臨時雇用」は救いになるか?」
Upjohn Institute for Employment Research
シニアエコノミスト スーザン・ハウスマン 氏
アメリカでは結婚する人の数が減少し、未婚の母親(シングルマザー)が急増している。シングルマザーの多くが非白人層の教育水準が低い10代の若者である。これは子どもの貧困をもたらす大きな原因の一つである。
アメリカは「1997年の改革」で、シングルマザーの就職支援に重点を置くようになった。これまでの福祉依存を減らし、貧困から抜け出せるよう、また結婚した上での出産を増やすことも目標にした。
福祉の現金給付を受けるには、フルタイムの職に就いていなければならず、また給付も一人一生涯に5年までという制限がある。国から委託された就職斡旋団体がシングルマザーに仕事を紹介する「ワークファーストプログラム」があるが、紹介された仕事が直接雇用ならまだよく、多くは派遣の単純作業である。昇進やスキルを磨く機会が少なく、良い条件の仕事を探す時間もとれず問題になっている。就職斡旋後も団体からのフォローがないなど、厳しい状況におかれる。シングルマザーは手っ取り早く仕事に就くことよりも、雇用の安定性が重要だろう。1997年の改革は1994年から2000年の間にシングルマザーの就業率を68%から78%に引き上げたが、この年代は景気がよかったこともあり、むしろ景気が悪い現在は現金給付を一生涯で5年までの制限を徹底しようという動きもでている。
■「日本における母親の就労と子どもの発達」
お茶の水女子大学 教授 菅原ますみ 氏
日本における母親の就労について、子どもの発達という視点からの実証的な検討結果を報告する。日本における母親の就労の現状は、特に低年齢児を持つ母親が就労していない傾向にある。このような状況の背景要因として、1)心理的な抑制要因、2)家庭外保育の整備の遅れ、3)家庭内の性役割分業の固定化、の3点がある。複数の縦断調査のデータを用いて、1)母親の就労が及ぼす発達初期の子どもへの影響、及び2)就労要因と親のウェルビーイングや子どもの発達との関連、を検討した。
母親の就労が発達初期における子どもに及ぼす影響については、短・中・長期的なデータによる分析結果から、子どもが低年齢の時点から就労している早期就労群と、専業主婦群の間に、ネガティブな有意差は認められないことがわかった。一方で、時代背景などによる変化の可能性も否定できないため、引き続き信頼性の高い方法論に基づいた定点観測の継続的な実施が必要である。
さまざまな指標を用いたデータ分析の結果を総合すると、親の就労と子どもの発達については、「親の就労要因→親のウェルビーイング→子どもの発達」という流れモデルにおける検討の重要性、また、父親においても「就労時間の短さ→子どもとの関わりの頻度の増加→父子間の愛着の形成および父親の子育てに対する肯定的な感情の向上」という流れが、時系列的なデータ分析により確認された。この結果、母親のサポートという視点から検討されることが多かった父親の就労についても、父子関係の発達という点から考える必要性があることがわかった。以上の結果に加え、就労と関連する収入という視点から、「収入→子どもへの教育投資→子どもの発達」という流れモデルも考慮した検討が今後の課題として挙げられた。
最後に、親の就労と関わりの深い家庭外保育について、アメリカでの研究や現状の国際比較、日本における分析の結果の報告があり、保育の良質さを保障することの重要性、および親の就労時間の長短と関係する保育時間の十分な検討の必要性が指摘された。
■コメント■千葉大学 教授 大石 亜希子氏
大石氏からは、母子世帯の貧困と自立支援のあり方について、日米の共通点と相違点を簡潔にまとめた報告があった。ハウスマン氏に対して、シングルマザーの長期的自立のためには、就労プログラム(Work First)と教育訓練プログラム(Training First) のどちらがいいのか、このような就労支援が子どものウェルビーイングにどのような影響があるか、また現金給付は普遍的給付か、条件付きがよいのか?という質問がなされた。それに対し、ハウスマン氏からは、就労プログラムが米国でされたが必ずしもうまくいかなかったため、ミックス戦略が必要であり、就労支援が子どものウェルビーイングへ与える影響については、家庭内の保育状況があまりよくない場合は就労し家庭外の保育を利用したことで子どものウェルビーイングによい影響を与えることもあり、最後に現金給付は米国では子どものいる低所得者に給付を厚くする給付つき税額控除の制度(Earned Income Tax Credit)があってうまくいっているという米国での事例が紹介され、回答があった。
永瀬氏に対しては、仕事と育児の両立支援策を企業へ義務付けると女性の雇用や賃金にマイナスの影響を及ぼす可能性が高いのではないか?仕事と育児の両立支援策がある企業ほど、女性が出産後も就業継続するのは、長期勤続するつもりの女性ほど仕事と育児の両立支援策を進めている企業を選んで就職しているという面があるのでは?と2点指摘があった。それに対し永瀬氏からは、非正社員への支援策が薄いため、支援策がある一般職採用が減って、非正社員が増えたこと、または学卒時に長期勤続を望んでいたかどうかは、現在調査しているところであり、今後はそれも含めて分析していきたいとの回答があった。
最後に菅原氏に対し、規制緩和の中でどうしたら保育の質が確保できるのか、プロセス評価の導入は可能かどうか?また、母親たちの早期復職傾向が子どもの発達にもたらす影響はあるか?の質問があった。菅原氏は、保育の質のアセスメントはお金がかかるが行うべきであり、保育士の人数と子どもの人数の比率・クラスサイズ・保育士の専門性の高さなどが保育の質に影響を与えることはわかっているのでこうした構造的特徴とともに実際におこなわれている保育のプロセスに関する評価のシステムを確立すべきであると回答があった。母親たちの早期復職傾向が子どもの発達にもたらす影響については、家庭外保育と家庭保育の質とをセットで考えるべきで、両者の質が高ければ、ネガティブな面は防げると思われるとの考えが示された。
Session 3 階層・格差視点からみたWLB -男性の家族ケア責任と地域性- ■「日米父親のワーク・ライフ・バランス~家事・育児参加の視点から~」
お茶の水女子大学教授 石井クンツ昌子 氏
■「日米父親のワーク・ライフ・バランス~家事・育児参加の視点から~」
お茶の水女子大学教授 石井クンツ昌子 氏
子育て期の男性を対象にした調査を家族班が担当して、2011年2月に12歳以下の子どもを持つ日本の父親2750人を対象とし郵送法による「子育て期における働き方と生活の調和に関する全国調査」(715人回収:有効回収率26.0%)、同年11月には米国の主要都市在住(ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴなど)の12歳以下の子どもを持ち配偶者と同居している50歳以下の父親に対するオンラインによる調査(1500人) を行った。
主な分析結果は、生育歴との関連から実父の家事・育児参加に対する肯定感は男性のロールモデルとなることである。社会的格差と職場環境要因・心理的ディストレスとの関連から、職場環境の柔軟性と自主性が高いこと、負担感が低いことは男性の家庭役割遂行を促進する要因となることも示された。以上から、男性のワーク・ライフ・バランス実現への提言として、長時間労働の短縮と職場環境を改善し柔軟性を創出し、仕事満足度の向上と負担感の軽減、ディストレスの排除を行うことが上げられる。さらに、家庭科教育により父親の家庭内役割についての教育や伝統的な性別役割観を是正すること、女性教育を重視すること、WLB講座を開設して家事・育児関わりのロールモデルを提供し父親のネットワークを広げることなどが上げられる。
■「地域社会のロールモデル形成政策―福井県の事例から」お茶の水女子大学 教授 舘かおる 氏
ワーク・ライフ・バランス政策を分析する際には、ジェンダーや階層、民族、地域性等にセンシティブな視点が必要となる。本報告では女性労働力率全国1位、女性管理職率全国最下位という特徴を持つ福井県を事例とし、地域社会のロールモデル形成政策の展開と今後の課題が検討された。
福井県は「女性活躍社会」の実現を目的として女性活躍支援事業を展開し、県内の企業や行政組織等に働きかけ「ふくい女性ネット」を設立、働く女性の業種横断的なネットワーク拡大を目指してきた。ロールモデル班では「ふくい女性ネット」に参加したメンバーに対しワーク・ライフ・バランス意識、「ふくい女性ネット」参加の意義などについて、アンケート調査およびインタビュー調査を実施した。アンケート調査の結果から、福井県におけるワーク・ライフ・バランスの特徴として、①女性が働くのが当たり前であるという文化や親族との同居・近居により働きやすい環境がある一方、賃金水準が低いために共働きせざるを得ないという状況があること、②仕事では人間関係力の必要性を意識させられる傾向にあること、③身近な人を人生・仕事選択のロールモデルとする傾向があることが挙げられた。また、インタビュー調査からはワーク・ライフ・バランスを「ワーク」と「ライフ」の「両立」・「選択」であるととらえず、「ライフ」の中に当然「ワーク」があると認識しているという点が大きな特徴として挙げられた。
「ふくい女性ネット」の意義としては①異業種交流により、事業体の性格を客観的に把握する能力の向上、②多様なリーダー像の認識、③自分の能力の発見と意欲の喚起、④変革へのアイデアの醸成が挙げられた。また、次のステップへの課題としては、「ふくい女性ネット」の第1期、第2期メンバーが中心となり、行政から独立して立ち上げられた「ふくい女性ネットNEXT」の維持基盤体制の構築等が指摘された。
■コメント 「日本における母親の就労と子どもの発達」 ルイジアナ州立大学 准教授 賀茂美則 氏
石井クンツ氏が指摘した『ワーク・ワーク・ライフ・バランス』という考え方は非常に重要であると思う。共働きが多くなる中、家庭の中にもワークがあり、家庭のワークと就業のワークとの間のコンフリクトは今後男女に関係なく存在していくだろう。そしてそうした場合にはWFC(Work to Family Conflict)とWLB(Work Life Balance)は分けて考えられるべきである。またWLBとは頭の中の意識ではなく、行動としてどうあるのかを測って行くことに意義があるという石井クンツ氏の意見に賛成である。次に、行政が主導するWLBはアメリカではまずあり得ない。アメリカの特に男性においてはWLBとは市民のレベルで意図して行動するものであるからだ。アメリカの父親は、家庭での居場所を確保するという意味でも家庭参加をしているようである。舘氏の福井県の報告を聞き、福井県は日本の将来の縮図であるように思われた。それは共働き世帯が当たり前となり、その共働き家庭の世帯収入は高いが個人収入は低く、妻も仕方がないから働くという家族である。したがってこの将来像においては格差が生じてくるから今後は日本でももっと格差研究を行っていくべきである。
・「女性のワーク・ライフ・バランスに関する継続調査」(2012年7月~8月実施)の調査結果
・「女性のワーク・ライフ・バランスに関する調査」について日本と米国を比較した調査結果
・「男性のワーク・ライフ・バランスに関する調査」について日本と米国を比較した調査結果
・アンケート調査「子育て期における仕事と家庭の調和に関する調査」結果報告
・WEBアンケート調査「仕事と生活に関するWEB調査」結果報告
・「ワーク・ライフ・バランスに関する調査」概要報告(女性対象)
・「ワーク・ライフ・バランスに関する調査」分析結果(男性対象)
⇒論文出版(一部、論文がご覧頂けます)
・論文・出版(2009~)
⇒学会報告(要旨がご覧頂けます)
・学会報告(2009年度~)
⇒研究会 (2008年度~)
・2012.12.13 研究会「非正規労働者と新しい雇用制度を考える」(3)非正規労働者の賃金
・2012.11.8 研究会「非正規労働者と新しい雇用制度を考える」(2)非正規雇用とジェンダー
・2012.10.19 研究会「非正規労働者と新しい雇用制度を考える」(1)非正規労働者の均等待遇
・2012.07.27 有期契約労働と育児休業―労働者調査から―
・2012.07.19 研究会「意思決定の場に多くの女性を~140名の働く女性インタビューから~」
・2012.07.2 公開講演会「日米のワークライフバランス」
・2012.07.1 公開研究会「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」


「父親役割意識と家事・育児参加の実態」(346kb, PDF)
・「仕事を持つ妻の就業実態と就業意識:子どもがいないか学齢期以下の子どもを対象に」
概要
目次
第1章「調査の目的、対象と方法、基本的属性」
第2章「子どものいる有業女性の各ライフステージにおける就業状況」
第3章「正社員の結婚・出産後の就業継続」
第4章「保育園及び学童保育の利用状況と満足度―第一子年齢と地域別にみた分析―」
第5章「有業女性の無職経験と再就職」
第6章「子どものいる有配偶者といない有配偶者」
第7章「初職における就業意欲、卒時関す図と仕事」
付録「各ライフステージにおける就業状況」
・「父親役割意識と家事・育児参加:学齢期とこれ以下の子どもを持つ父親を対象に」
概要
序章「調査概要」
第1章「男性の属性と子育て参加頻度との関係」
第2章「男性の成育歴と子育て参加頻度との関係」
第3章「男性の職場環境と子育て参加頻度との関係」
第4章「男性の子育てネットワークとの関係」
第5章「妻の就業や子ども数と子育て参加頻度との関係」
第6章「仕事に対する意識と子育て参加頻度との関係」
第7章「性別役割分業意識と子育て参加頻度との関係」
第8章「男性の父親アイデンティティと子育て頻度」
第9章「夫婦の関係性と男性の子育て」
論文・出版(2009~)
2012年度(平成24年度)
2011年度(平成23年度)
2010年度(平成22年度)
2009年度(平成21年度)
2011年度(平成23年度)
2010年度(平成22年度)
2009年度(平成21年度)
2008年度(平成20年度)