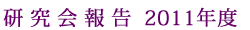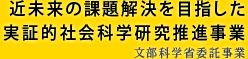-
・2012.03.19 女性労働と人的資本形成に関するコンファレンス
- 女性労働と人的資本形成に関するコンファレンス
- 日時2012年3月19日(月)10時から14時
- テーマ 「女性労働と人的資本形成に関するコンファレンス」
(東京労働経済学ワークショップとの共催) - 第1報告
藤井麻由氏(一橋大学経済研究所 世代間問題研究機構)「出産後の母親の就業行動が子どもの発育に及ぼす影響について:米国のパネルデータによる実証分析」 -
 アメリカのデータ(National Longitudinal Study of Youth 79 :1979年に14から21歳だった男女12682人を追跡している調査および NLSY79 Children and Young Adults:NLSY79の対象となっている女性の子どもに関する情報を1986年から追跡的に収集している調査)を用いて、出産後6、12、24週間で復職する場合に子どもの発育に与える影響を検証した。サンプルは、1988年から1994年までに生まれた子ども1098 名である。
アメリカのデータ(National Longitudinal Study of Youth 79 :1979年に14から21歳だった男女12682人を追跡している調査および NLSY79 Children and Young Adults:NLSY79の対象となっている女性の子どもに関する情報を1986年から追跡的に収集している調査)を用いて、出産後6、12、24週間で復職する場合に子どもの発育に与える影響を検証した。サンプルは、1988年から1994年までに生まれた子ども1098 名である。
先行研究においては、1時点のみに着目し、発育が遅れているために母親が復職するタイミングが遅くなるといった内生性への対処法に問題があったが、本研究においては、複数時点に関して分析し、子どもの発育の決定式と母親の時間の決定式を同時推計することで内生性に対処している。
分析の結果、1~2歳児の知的精神面の発育については、12週以上家にいることが有意によい影響を与え、1~2歳児の身体的発育については、6週以上家にいることが有意によい影響を与えていた。また、4~5歳時の問題行動については、12週以上家にいることが有意に問題行動を減らしていた。以上の結果から、出産後母親が家にいることは子どもの発育に対して正の効果を及ぼし得ること、母親の時間と子どもの発育の関係は指標によって異なる傾向があることが明らかになった。
- 第2報告
臼井恵美子氏(名古屋大学) 「Employer Learning, Job Mobility, and Wage Dynamics」 - アメリカのデータ(National Longitudinal Study of Youth 79 :1979年に14から21歳だった男女12682人を追跡している調査)を用いて、企業が学ぶ従業員の労働生産性(employer learning)は、すべての企業が知り得るもの(public)か、知り得ないもの(private)かについて検証した。サンプルは、8年以上教育を受けた男性に限定した。
先行研究においては、試験の点数が賃金に影響を与えていたらpublic learning、勤続年数が賃金に影響を与えていたら、private learningであるとしており、両方の説がある。
本研究においては、新しい方法を開発して検証する。それは、public learningであれば、賃金が経験に対してconcaveであり、private learningであれば、勤続年数に対してconcaveであると仮定する方法である。その場合に、 企業との相性と勤続年数の相関を考慮にいれなければならないため、差分の賃金関数を推定した。
企業との相性と勤続年数の相関を考慮にいれなければならないため、差分の賃金関数を推定した。
分析の結果、学歴別にみてみると、高卒の人では、最初の10年間 public learningであり、大卒では、経験年数が8年以上であればpublic learningであることが明らかになった。また、職種別にみてみると、サービス業の人ではpublic learningであるが、マネージャーではprivate learning であることが明らかになった。 - 第3報告
永瀬伸子(お茶の水女子大学)「女性の就業と出産・子育てに与える職場環境の影響」  お茶の水女子大学文部科学省委託事業「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」研究プロジェクト(2008~2012)で、2011年2~3月および5月に実施した日本国内に居住する26~38歳の女性を対象にしたアンケート調査(住民基本台帳から層化二段抽出法を用いてサンプリングした)の結果を用いて、女性の就業継続要因および結婚・出産タイミングの影響要因を検証した。
お茶の水女子大学文部科学省委託事業「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」研究プロジェクト(2008~2012)で、2011年2~3月および5月に実施した日本国内に居住する26~38歳の女性を対象にしたアンケート調査(住民基本台帳から層化二段抽出法を用いてサンプリングした)の結果を用いて、女性の就業継続要因および結婚・出産タイミングの影響要因を検証した。
分析の結果、結婚を決める頃は、賃金が高いほど、育児休業制度があるほど就業継続していた。結婚後は、仕事時間の融通性、育児休業制度があること、夫の収入見通しへの不安、親の家事・育児協力を見込めること、学校卒業時の就業継続意志が、正社員継続を推進していた。出産後は、出産前の企業の子育てサポートの雰囲気、妻の年収の高さ、学校卒業時の就業継続意志が正社員継続を推進していた。
また、結婚・出産タイミングの影響については、仕事と家庭の両立ができそうである見通しがあるほど交際期間は長期化し結婚が遅れること、大卒正社員離職者は交際期間を長期化し正社員での就業期間を伸ばした後に離職していること、大卒出産後の正社員継続者はタイミングを見計らってようやく出産していること、出産タイミングの遅れは子どもを持たない割合を引き上げることが明らかになった。また、育児休業制度があること・モデルがいる職場であることは、十分に利用しやすい職場にはなっていないため、出産タイミングを早めるよりは、むしろタイミングを遅らす可能性があることが明らかになった。- <WORKFAM研究員による報告>
「子どもを持つことを躊躇する要因」 - 有配偶正社員女性に対するグループ・インタビューの結果、子育てしながら働きにくい職場であること、妻が家事を担っていることにより、子どもを持つことを躊躇している女性たちの存在が明らかになった。また、WEBアンケート調査の分析によって、出生意欲があっても、「子育てしやすい職場」よりも「子育てしにくい職場」の場合に子どもの数が少ないこと、また、「子ども2人」よりも「子どもいない」「子ども1人」の場合に子育てしにくい職場であることが明らかになった。
- 「キャリア形成意識とキャリア選択」
- 無作為抽出アンケート調査の分析によって、初期キャリア意識9項目のうち、「長く勤務できそうである」と「女性が活躍している」が就業キャリアに正の影響を与えていることが明らかになった。また、WEBアンケート調査の分析によって、キャリア形成志向とともに、夫の退社時間が早いほど、夫の家事育児割合が高いほど、妻が仕事をすることに対する夫の賛成度が高いほど、妻が現在パート等ではなく、正社員を選択していることが明らかになった。
- 「保育園及び学童保育の利用状況と満足度 -第一子年齢と地域別にみた分析-」
- WEBアンケート調査の分析より1歳時点で、地域別に認可外保育園の利用割合をみると、首都圏で1割を超えており、北陸、東海に比べて高い。利用の理由として、6割の者が認可保育園に入園できなかったと回答している。また、保育園を利用しなかった理由として、首都圏では、「入園できなかった」と回答した割合が他の地域と比べると高かった。
- 公開講座『育メンと育児休業制度:個人と行政の視点から』
- 日時2012年2月11日
- テーマ 「育メンと育児休業制度:個人と行政の視点から」
- 講師 山田正人 氏(横浜市副市長)
-
『経産省の山田課長補佐、ただいま育休中』の著者である、現横浜市副市長の山田正人氏にご講演会場には小さなお子さんを連れたお父さんの姿が目立ち、父親の育児休業というテーマへの関心の高さがうかがえました。山田氏のウィットとユーモアに富んだご講演の概要は以下の通りです。
 2004年11月から1年間、第3子の誕生の際に育児休業を取得した。そのきっかけは、第3子の妊娠がわかったときに、妻の「私ちょっと産めないなあ」という一言だった。思えば、夫婦が初めての子ども(双子)を授かった際には当然のように妻が育児休業を取得した。しかし、3番目の子どものときには、自分と同じようにキャリアを築いてきた妻の存在もあって「今度は自分が育児休業を取得する番かな」と。
2004年11月から1年間、第3子の誕生の際に育児休業を取得した。そのきっかけは、第3子の妊娠がわかったときに、妻の「私ちょっと産めないなあ」という一言だった。思えば、夫婦が初めての子ども(双子)を授かった際には当然のように妻が育児休業を取得した。しかし、3番目の子どものときには、自分と同じようにキャリアを築いてきた妻の存在もあって「今度は自分が育児休業を取得する番かな」と。
こうして育児休業取得を決断したわけであるが、その際の周囲の反応は様々であった。特に、双子の子どもの反応ははっきりしていた。それまでは、平日は深夜に帰宅、週末も土曜日の午後から徐々にエンジンが入ってそれから子どもと接するような状態であったので、子どももいまひとつ自分になついてくれていなかったように思う。しかし、父親が育児休業をとると決めたその日の夜から、子どもはそのことを鋭敏に察知し、父親と一緒に寝てくれるようになった。
「子育てはお母さんにしかできないの?」という一種の社会実験も意識して育児を始めたが、実際には初乳をあげることを除いて父親は何でもできると思った。しかし、「育児は片目をつぶってもできるだろう」という当初の思い込みは見事に打ち砕かれた。男性なのだから体力や筋力で根をあげることはないと思っていたが、育児休業を取得して数カ月でテレビのリモコンも持てないほどの腱鞘炎になった。また、日中に小さい子どもしか話し相手がいないこともつらかった。風邪をひいた子どもを医者に連れていくと「今日ママはどうしたの」と何度も聞かれ、近所から好奇の目で見られているのを感じた。育児休業を取得して2,3ヶ月目に、気持ちの落ち込みが回復しない、一種の「プチうつ」を経験したように思う。そうした閉塞感を打開してくれたのは、職場の仲間からの何気ない励ましだった。妻も理解してくれ、気分転換に職場での飲み会にも月1回ほど参加するようになり、そこで相も変らぬ職場の人間関係を確認できたのも精神衛生上良かった。
育児休業を取得して良かったと満足していると思っている。その理由はいくつもあるが、子どもの成長が目に見える喜びと人間としての成長、そして夫婦間のコミュニケーションの改善などがあると思う。特に仕事の面では、サービス利用者としての視点が養われ、また部下に対しても寛大な気持ちを持てるようなった。
現在は横浜市政に身を置く立場であるが、市民のためのイクメン施策をいくつか実施している。男性が子育てを学べる「横浜インクメンスクール」、父親同士の出会いの場を提供する「パパ講座」「ヨコハマダディ」、そして子育て支援の取組みを積極的に行っている企業に対する認定・表彰制度「よこはまグッドバランス賞」などがある。
市役所内でも、育休適齢期の男性職員とランチミーティンングを実施するなどして、育児休業を取得しても、人事上の不利益を受けないというメッセージを発信し続けている。
 「育児休業」というと文字通り「休んでいる」との印象を持たれがちだが、実際は全く違う。男女ともに仕事も子育ても楽しめる社会の実現には、当然個人の意識改革が必要であるし、また企業側も男性の長時間労働を助長させる会社への忠誠心をはかるような評価制度を改めていく必要がある。また、企業に平均残業時間数、育児休業・介護休業の取得率及び取得期間等の情報を公開させるような社会的仕組みも重要だろう。
「育児休業」というと文字通り「休んでいる」との印象を持たれがちだが、実際は全く違う。男女ともに仕事も子育ても楽しめる社会の実現には、当然個人の意識改革が必要であるし、また企業側も男性の長時間労働を助長させる会社への忠誠心をはかるような評価制度を改めていく必要がある。また、企業に平均残業時間数、育児休業・介護休業の取得率及び取得期間等の情報を公開させるような社会的仕組みも重要だろう。
講演のあと、会場からの活発な質疑応答にお答えいただきました。
※横浜市の取組みの事例を紹介します。
横浜市から発信!パパ育児を面白くするサイト「ヨコハマダディ」
- 政策研究 「日本の『WLB』政策 その批判的検討と改革の方向」
- 日時2012年1月18日
- テーマ 「日本の『WLB』政策 その批判的検討と改革の方向」
- 講師 萩原久美子氏 (東京大学社会科学研究所)
-
 「WLB」なるものを政策分析の対象とする際、いくつかの困難が伴う。まず、「ワーク・ライフ・バランス」というタームを使って、個人レベルのコンフリクトやスピルオーバーを語っているのか、企業レベル、あるいは国の政策として語っているのかを明瞭に区別しないまま、3つのレベルが混在した議論がなされることである。しかも、このタームにユニバーサルな定義があるわけではないために、政策領域として何をカバーしているのか変幻自在だ。「よきもの」という価値をあらかじめ得ているため、「WLB」をどのように浸透させるか、どのように実践するかという方策は語られるが、その政策をけん引する論理や歴史的な背景はあまり検討されてこなかったように思う。
「WLB」なるものを政策分析の対象とする際、いくつかの困難が伴う。まず、「ワーク・ライフ・バランス」というタームを使って、個人レベルのコンフリクトやスピルオーバーを語っているのか、企業レベル、あるいは国の政策として語っているのかを明瞭に区別しないまま、3つのレベルが混在した議論がなされることである。しかも、このタームにユニバーサルな定義があるわけではないために、政策領域として何をカバーしているのか変幻自在だ。「よきもの」という価値をあらかじめ得ているため、「WLB」をどのように浸透させるか、どのように実践するかという方策は語られるが、その政策をけん引する論理や歴史的な背景はあまり検討されてこなかったように思う。
日本で政策として「WLB」が取り上げられるようになったのは2003年ごろからだが、そこでの「work」の概念は雇用労働中心のものだ。正規雇用を基準として、特に女性の場合には同一事業所で一貫してキャリアを追求する一貫継続就労型がいわゆる「両立」「WLB」の達成すべきモデルとして重視されている。この点から、育児休業制度や子育てのための短時間勤務制度への取り組みが進んできた。これは重要な成果であるが、だが、多くの女性労働者の実態には必ずしも対応したものとは言えず、雇用上のジェンダー差別禁止への国家介入の弱さがいわゆる「WLB」政策の効果を掘り崩し、「work」総体のジェンダー公平な分配のありかたにより深刻な内部矛盾を生み出している事態もある。
女性が非正規雇用者の約7割を占めるという構造的特徴を維持したまま、非正規雇用者数は年々増加している。しかし、均等法の限定的な差別概念、同じ雇用管理区分でなければ差別は問えないとする同法運用指針によって、この非正規雇用者の多くは「正社員」という雇用管理区分の労働者との不当な待遇格差や差別を問えない。しかも、これらの女性の多くが実態として育児休業制度・短時間勤務制度の利用から排除されている。「WLB」政策が整備拡充される同じ時期に、これらの利用が難しい女性労働者が層として厚みを増したのである。しかも、均等法の限定的な差別概念によって職場での格差再生産の機能を内包させたままに、である。このように考えると、改めて公的保育制度の重要性が認識されるところだ。だが、現状の保育政策の方向性は普遍的な供給制度を追求しつつもそれは待機児童解消と市場開放を基軸としている。親の従業上の地位や経済状況による階層化メカニズムの側面が強化されるかもしれず、注意深く見守る必要がある。このように、「WLB」と称される政策展開をアプリオリにジェンダー平等を促進するものとしてとらえるのではなく、その政策展開によってもたらされる分業体制、不平等なジェンダー関係を検討することが求められている。
以上の報告の後、出席者と「均等法の中における雇用管理区分」、「働き盛りの男性に対する企業側の取組」など、様々な視点から活発な意見交換を行った。
- シンポジウム
- 日時2011年10月30日 13:00~16:00
- テーマ 「養育環境の現代課題“子ども・子育て新システムをめぐって」(グローバルCOEと共催)
- 【発表者】
岡本 利久(元内閣府共生社会政策統括官付参事官補佐/現厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課)
「子ども・子育て新システムについて」
永瀬 伸子(お茶の水女子大学/本学「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」拠点リーダー)
「親の就労の視点から」
菅原 ますみ(お茶の水女子大学/グローバルCOEプログラム事業推進担当者)
「養育・保育・養護の質と子どもの発達」
平岡 公一(お茶の水女子大学/グローバルCOEプログラム事業推進担当者)
「社会政策・社会福祉政策のなかでの子ども・子育て政策の問題」
【主催】お茶の水女子大学グローバルCOEプログラム「格差センシティブな人間発達科学の創成」基礎問題プロジェクト
【共催】お茶の水女子大学「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」(文科省委託研究)
詳細はこちら お茶の水女子大学 グローバルCOEホームページ
- 公開報告会
- 日時2011年10月13日 15:00~17:00
- テーマ 「アメリカ女性のワーク・ライフ・バランス」~企業ヒアリング・フォーカスグループヒアリング・専門家へのヒアリングから得たこと~
-
第1報告「カリフォルニア州の有給家族休暇制度(Paid Family Leave)とその評価」
申キヨン(法政策研究班)
 第1報告では、カリフォルニア州が定める『有給家族休暇制度(PFL)』に焦点をあて、その制度をめぐり法学者、弁護士、労働組合支援者のそれぞれの立場での家族的責任に関する取組みについて報告された。まず法学者たちは、職場における差別“work life discrimination”の解決を広く取り扱っているが、その解決方法の一つとして集団訴訟がある。訴訟を通して、家族的責任による差別をなくす反差別理論の研究をしている。それに対してLegal Aid Society で働く弁護士たちは、労働者にとっては訴訟のような負担の大きなものよりも、職場環境改善策のほうが効果的であると考えそのモデルを構築していた。たとえば、家族を持つ労働者が家族的責任にある場合には、家族を持つ労働者の働く環境に、職場が合わせなければならないというモデルである。最後に労働組合の役割についてであるが、アメリカのように政府が労働者を守る法律が少ないところはでは、労働者の権利を守るために労働組合の活動が非常に重要になっている。彼らもまた、様々な問題を「労働者の視点」から再構築しようとする試みをしていた。
第1報告では、カリフォルニア州が定める『有給家族休暇制度(PFL)』に焦点をあて、その制度をめぐり法学者、弁護士、労働組合支援者のそれぞれの立場での家族的責任に関する取組みについて報告された。まず法学者たちは、職場における差別“work life discrimination”の解決を広く取り扱っているが、その解決方法の一つとして集団訴訟がある。訴訟を通して、家族的責任による差別をなくす反差別理論の研究をしている。それに対してLegal Aid Society で働く弁護士たちは、労働者にとっては訴訟のような負担の大きなものよりも、職場環境改善策のほうが効果的であると考えそのモデルを構築していた。たとえば、家族を持つ労働者が家族的責任にある場合には、家族を持つ労働者の働く環境に、職場が合わせなければならないというモデルである。最後に労働組合の役割についてであるが、アメリカのように政府が労働者を守る法律が少ないところはでは、労働者の権利を守るために労働組合の活動が非常に重要になっている。彼らもまた、様々な問題を「労働者の視点」から再構築しようとする試みをしていた。
カリフォルニアでは家族的責任のための有給休暇制度がアメリカで最初に導入された。最大の特長は有給(6週間まで、平均週賃金の55%・最大987ドル)である。また導入の効果について2010年に報告されたものによると、導入以前に懸念されていた経営者側の経営の負担にはつながらなかった、としている。しかし、休暇後の雇用保障がないことや、認知度が労働者全体に均等ではないことが問題点として上げられる。今後は家族的責任をめぐり、雇用保障や制度の拡充と使いやすい法体系にする取組みが期待される。
第2報告「フォーカスグループに学ぶアメリカ女性のワーク・ライフ・バランス」
石井クンツ昌子(家族研究班)
 第2報告では、カルフォルニア州リバーサイド市において子どもを持つ働く女性に対するフォーカスグループインタビューの結果が報告された。日本の働く女性と比較すると、仕事面において、多様な職業履歴(転職経験が多い)があげられるが、このことはアメリカでは転職によって職業のランクを上げていくので珍しいことではない。子どもとの関係については、日々の過ごし方、接し方、周りからの援助の有無や状況などについて細かく聞き取りをした中で、自分の生活のバランスを持つために、忙しい中でも自分だけの時間“Me time”を作り出す工夫をしているエピソードが紹介された。
第2報告では、カルフォルニア州リバーサイド市において子どもを持つ働く女性に対するフォーカスグループインタビューの結果が報告された。日本の働く女性と比較すると、仕事面において、多様な職業履歴(転職経験が多い)があげられるが、このことはアメリカでは転職によって職業のランクを上げていくので珍しいことではない。子どもとの関係については、日々の過ごし方、接し方、周りからの援助の有無や状況などについて細かく聞き取りをした中で、自分の生活のバランスを持つために、忙しい中でも自分だけの時間“Me time”を作り出す工夫をしているエピソードが紹介された。
夫が必ずしも家事・育児に十分参加しているわけではなく、また専門性の低い職種では低賃金になるため、経済的困難に陥りやすい状況など、苦労はあるものの、総じてアメリカ女性は明るく精神的にたくましい様子が語られた。ワーク・ライフ・バランスの困難性をどのように乗り切るかということについて、「計画性」「福利厚生」「フレキシビリティー」が有効的であるという示唆が聞き取りからもたらされた。
第3報告「アメリカ東海岸における幼い子どもを持った女性のワーク・ライフ・バランス」
山谷 真名(労働研究班)
 ボストンにおける幼い子どもを持った高学歴女性6人のワーク・ライフ・バランスの聞き取り調査について報告された。彼女たちは転職や解雇などを経験しているが、女性であることが職探しにおいて不利になることはないということであった。連邦制度の出産後の休業は12週のみであり、ボストンにおいて保育費用は非常に高いなど、仕事と育児の両立支援策は日本と比べて整っていないが、出産後に仕事を継続、または復帰する女性は日本より多い。報告の中での参考資料としてあげた『少子化社会に関する国際意識調査』(内閣府2005)によると、日本とアメリカの末子年齢による就業状況をみると、日本では子どもが0~2歳のとき無業である割合はアメリカの2倍になる。その理由としては、夫や親族の家事・育児の分担割合が高く、また、女性のリスク管理意識が高いことが考えられる。夫の家事・育児分担については、インタビュー者の夫は必ず協力をしており、またすべての夫が育児休暇を取得していた。日本では、当プロジェクトが今年1~2月に実施した調査によると、妻が正社員であっても、家事・育児の80%以上を妻が行っている家庭が5割を超えている。
ボストンにおける幼い子どもを持った高学歴女性6人のワーク・ライフ・バランスの聞き取り調査について報告された。彼女たちは転職や解雇などを経験しているが、女性であることが職探しにおいて不利になることはないということであった。連邦制度の出産後の休業は12週のみであり、ボストンにおいて保育費用は非常に高いなど、仕事と育児の両立支援策は日本と比べて整っていないが、出産後に仕事を継続、または復帰する女性は日本より多い。報告の中での参考資料としてあげた『少子化社会に関する国際意識調査』(内閣府2005)によると、日本とアメリカの末子年齢による就業状況をみると、日本では子どもが0~2歳のとき無業である割合はアメリカの2倍になる。その理由としては、夫や親族の家事・育児の分担割合が高く、また、女性のリスク管理意識が高いことが考えられる。夫の家事・育児分担については、インタビュー者の夫は必ず協力をしており、またすべての夫が育児休暇を取得していた。日本では、当プロジェクトが今年1~2月に実施した調査によると、妻が正社員であっても、家事・育児の80%以上を妻が行っている家庭が5割を超えている。
ただし、アメリカにおいても仕事継続はできても夫婦二人ともがキャリアアップをめざすことは難しく、子どもが小さい頃は妻か夫が家庭中心の生活を送らなければいけないとのことであった。
第4報告「アメリカの有子女性の仕事経験―東海岸、中西部、西海岸での質的調査から」
永瀬 伸子(研究代表者)
 企業4社を訪問し、そこで働く子どもを持つ女性18人を対象にワーク・ライフ・バランスを聞き取った。米国では、職株ごとの賃金相場が参照されて賃金水準が決まる。同じ職に長く勤務しただけでは賃金は上がらない。このため中小企業に勤務している者は、転職を通じて上位職への移動によるキャリアアップを目指し、大企業では社内公募を通じてキャリアアップをしていた。学歴も重要で、働きながら大学に通ったという発言も少なからず聞かれた。日本では長期雇用を前提として、長期勤続のもとでの昇進が多いが、アメリカは転職や社内公募による昇進が一般的であった。また失業や解雇経験も少なくなく、労働市場の流動性が直に感じられた。
企業4社を訪問し、そこで働く子どもを持つ女性18人を対象にワーク・ライフ・バランスを聞き取った。米国では、職株ごとの賃金相場が参照されて賃金水準が決まる。同じ職に長く勤務しただけでは賃金は上がらない。このため中小企業に勤務している者は、転職を通じて上位職への移動によるキャリアアップを目指し、大企業では社内公募を通じてキャリアアップをしていた。学歴も重要で、働きながら大学に通ったという発言も少なからず聞かれた。日本では長期雇用を前提として、長期勤続のもとでの昇進が多いが、アメリカは転職や社内公募による昇進が一般的であった。また失業や解雇経験も少なくなく、労働市場の流動性が直に感じられた。
仕事の範囲や権限が明確なため、管理職になると、労働時間は長くなるが、勤務時間はむしろ自分で調整できるという。早めに帰宅して、家族で夕食を食べた後に、自宅で携帯電話やコンピュータを使って家で仕事をこなすのは一般的であった。子育てにおいては保育費用が高いこともあり、夫や親族のサポートは大変重要であった。
以上聞き取りをしたアメリカの労働環境をみると、多様な人種をはじめとする「多様性」「夫の家事・育児の協力」「高い転職率」を特徴としてあげられる。これらが作用しあいながら、ワーク・ライフ・バランスを形成し、そこにうまく適応しようと努力する女性たちが多くいた。
報告の後、参加者からは、「アメリカの制度は日本より整っていないが、少子化は日本より進んでいない。日本がこの現状を改正するためにはどうすればいいか考えさせられた」「最近は女性本人の仕事を続ける意識や男性労働者の理解が高まっているが、女性はライフスタイルにより働き方が変わりやすいので、お互い理解しながら働くことが重要である」「日本の女性の働く意識の両極化があって、働き続ける女性も増えるが、専業主婦志向も増えている」などのコメントがあった。
- 公開講座【アメリカでワーク・ライフ・バランス施策が求められる理由】
- 日時2011年6月10日 10:00~12:00
- テーマ 「アメリカでワーク・ライフ・バランス施策が求められる理由」
- 講師 大沢真知子氏(日本女子大学 教授)
-
 アメリカにおけるワーク・ライフ・バランスが登場した背景は、1960年代にさかのぼる。サービス経済が発展していく中、女性の社会進出の拡大路線が始まった頃で、既婚女性の労働参加が増えた。1960年代から80年代にかけての女性の高学歴化は、女性の就業率を高める要因となってきた。その結果、90年代になると共働きと片働きの所得格差が広がったのである(まさに今の日本の現状と似ている)。アメリカの男性実質年収額が減少傾向にある状況において、共働きでないと生活が困難となり、ワーク・ライフ・バランスに対する意識が高まるきっかけとなった。90年代に入り、グローバル経済化の競争激化の流れは、共働き世帯、労働時間ともに増加させ、IT導入により所得の両極化が進み、アメリカ社会に大きな変化をもたらした。このことは、企業側の意識改革をもたらせた。
アメリカにおけるワーク・ライフ・バランスが登場した背景は、1960年代にさかのぼる。サービス経済が発展していく中、女性の社会進出の拡大路線が始まった頃で、既婚女性の労働参加が増えた。1960年代から80年代にかけての女性の高学歴化は、女性の就業率を高める要因となってきた。その結果、90年代になると共働きと片働きの所得格差が広がったのである(まさに今の日本の現状と似ている)。アメリカの男性実質年収額が減少傾向にある状況において、共働きでないと生活が困難となり、ワーク・ライフ・バランスに対する意識が高まるきっかけとなった。90年代に入り、グローバル経済化の競争激化の流れは、共働き世帯、労働時間ともに増加させ、IT導入により所得の両極化が進み、アメリカ社会に大きな変化をもたらした。このことは、企業側の意識改革をもたらせた。
ヨーロッパ諸国では、家庭を持つ女性労働者に対し労働条件や権利が確立されていることに比べると、アメリカでは育児休業や労働時間の管理についても企業の自主性に任されており、法制度があまり整っていない。そこで90年代にはいってから財団が中心となって、企業が働き方の選択肢をふやし、従業員のワーク・ライフ・バランスに配慮した働き方を導入するためにどうしたらいいのかということに関する研究を行い、社会全体の意識改革を促すムーブメントを起こそうとしている。いまアメリカは企業のなかに働き方のオプションを増やすことで多様な人材を活用する可能性を追求しているのである。
 質疑応答のあと大沢氏から、日本の正社員の多様な働き方を生み出すには制度だけでなく「何のために必要か」を考える意識改革が必要という話から、参加者との間で日本のワーク・ライフ・バランスのおよび女性の働き方についてディスカッションを行った。
質疑応答のあと大沢氏から、日本の正社員の多様な働き方を生み出すには制度だけでなく「何のために必要か」を考える意識改革が必要という話から、参加者との間で日本のワーク・ライフ・バランスのおよび女性の働き方についてディスカッションを行った。
- 公開シンポジウム「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」平成22年度 活動報告会
- 日時2011年6月9日(木)16:30~19:30
- 場所お茶の水女子大学 大学本館1階103室(大会議室)
- 毎年、行っている年度の研究活動報告会を今年は初めての試みで、一般の方も傍聴いただける公開型としました。前半に各班からの研究成果の報告、後半は、各班のリーダーが今後の研究の方向性について、議論を行いました。
1.報告議題
〈労働班〉「「女性のキャリア形成と出産、子育て」
量的調査からの分析結果として、女性の就業継続を高める要因は、①本人が学校卒業時に仕事を継続したいと思っていた、②結婚時、出産時、それぞれのライフステージで働く女性に職場が支援的でそうした女性モデルがいること、③仕事のや りがいがある、④夫の協力見通しが高く、職場環境もそれを可能にすることである。質的調査では、大企業総合職では、全国転勤ありなしを入社時点で契約するコース別人事が定着し、労働時間も長いが、出産後の継続が厳しいと出産を考える年齢になると苦渋する。また就業継続不安の一方、専業主婦になることへの不安から、出産を躊躇している正社員も見出された。
りがいがある、④夫の協力見通しが高く、職場環境もそれを可能にすることである。質的調査では、大企業総合職では、全国転勤ありなしを入社時点で契約するコース別人事が定着し、労働時間も長いが、出産後の継続が厳しいと出産を考える年齢になると苦渋する。また就業継続不安の一方、専業主婦になることへの不安から、出産を躊躇している正社員も見出された。
〈家族班〉「父親の育児・子育て・家事参加ワーク・ライフ・バランス」
量的調査からの分析結果として、男性の家事・育児参加を推進する要因として、①職場環境が柔軟である(短時間勤務や育児休業が昇進に影響しないなど)、②フォーマルサポートの充実、③仕事や家庭内における性別役割分業意識がない、④妻との良好な関係性、があげられる。制度の充実ばかりでなく、利用可能性や男性の意識教育、男性に対する育児・支援体制の構築、妻の家庭役割に対する意識改革、の必要性が見出された。
〈発達心理班〉「親の就労状況と子どもの発達」
ベネッセコーポレーション次世代研究所「妊娠・出産・子育て基本動向調査」(毎年パネルの調査)の分析から、①男性については育児時間が増えることが子どもとの関わりの増加につながり、育児に対する自信を高めること、②子育て期の女性については、仕事を持つことを希望していた者が仕事を持つことで、心の健康が良好になることなどの因果関係を実証的に示した。同じ調査の分析から夫の就労時間が短ければ、育児参加が進み、父子関係が良くなり、父の子育て肯定感が高まるという関係が明らかになった。
〈ロールモデル班〉「ふくい女性ネットの活動展開 -ふくい女性ネットNEXT設立と参加者アンケート調査から」
福井県にある企業や公共機関に勤務する「ふくい女性ネット」参加メンバーに対する聞き取り調査を中心に分析した。働き続けることが自然の福井県の女性に求められる課題として、①「昇進」と「活躍」への両方のかじ取り―ポジションを得る「昇進」と、自身が納得できる仕事をする「活躍」の違いのバランスをとる、②「福井県の企業・社会における保守的な規範や価値観」や女性自身の「県民性、意識・意欲」への打破および改善が見出された。
〈法政策班〉「育児休業取得による賞与不支給取扱いの違法性について」「労働相談制度の調査」
ワーク・ライフ・バランス政策にかかわる判例研究として、①個別紛争解決制度、②育児休業取得による労働者の不利益についての事例研究を行った。以上のことから①相談内容の深刻化により、より専門性の高い人員の確保の必要性、②産前産後休業、育児休業を争点とした判例は、育休の権利とその取得の意義を世間に認識させたが、取得者に対する賃金(賞与)の支払いを企業の裁量によるものであるとしている点については、労働条件の格差をもたらすことである。今後、改善の余地を含め検討課題とする、ということが見出された。
2.ディスカッション
〈労働班〉女性については、就業だけでなく結婚や家族形成から見た視点にも関心がある。労働経済学では仕事だけを取り上げるところだが、プロジェクトでは、男性・女性・家庭・子どもといった4つの分野での複合的なかかわりで取り組みたい。
〈家族班〉家族研究では研究概念図が概念図のためだけのものでなく、具体的な施策の提言実現できるようさらに分析したい。男性の労働時間など様々な就業上における「構造的」なものと、父親としての意識やロールモデル形成など「意識的」なものの2つが改革されていかないとならないと考える。
〈発達心理班〉これまでは、0歳児など小さい子どもに注目していたが、5歳児くらいにも大変な時期がある。年齢を上げてデータを取っていきたい。子どもの発達段階というのはどの年齢にもある、「次世代育成」に重きをおいて、考えていきたい。
〈ロールモデル班〉ロールモデルを個人としてみた場合、どう変容していくのか、育っていくのかに注目したい。地方と大都市、大企業と中小企業では違ってくるだろう。福井を取り上げているが3月11日の震災の影響は大きい様に思う。原発や地場の産業のありかたなど、そうした福井の独自性をさらに明らかにしていきたい。
〈法政策班〉ワーク・ライフ・バランス政策に関する研究は他にもあるが、私たちのジェンダー・格差センシティブという独自性を出せるようにしていく。具体的には、ワーク・ライフ・バランス概念の定義についての検討をする。生活の質を向上するという意味で、ワーク・ライフ・バランスと子ども政策との関係も重要。たとえば保育の問題。そういう他ではあまりない視点から特色を出せるのではないかと思う。
法律は一体何が出来るのかという原点に立つと、法律の力は強力である。しかしなんでも法律にするということにはいかない。提言するにあたって、最低限、規定してほしいこと、政策として詰めてほしいことなどを盛り込むべきだ。罰則だけ設けても意識がなければ浸透しない。
- 【法制度に関する研究会】
- 日時 2011年6月7日
- テーマ 「アメリカにおけるワーク・ライフ・バランス関連法制度について」
- 講師 池添弘邦氏(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 主任研究員)
-
 アメリカはワーク・ライフ・バランス発祥国。しかし政策としては、ワーク・ライフ・バランス憲章をはじめとする明確な政策が打ち出されている日本と比べ、1993年に制定されたFamily and Medical Leave Act(FMLA、無給の育児休暇、看護・介護休暇)の取得を使用者に義務付ける法律があるにとどまる。
アメリカはワーク・ライフ・バランス発祥国。しかし政策としては、ワーク・ライフ・バランス憲章をはじめとする明確な政策が打ち出されている日本と比べ、1993年に制定されたFamily and Medical Leave Act(FMLA、無給の育児休暇、看護・介護休暇)の取得を使用者に義務付ける法律があるにとどまる。
アメリカと日本との大きな違いは、WLBにかかわる法的規制が極端に少ないことである。その法律も連邦法と州法の重層構造になっており、州が独自に制定することができるため、地域によって差がある。このように個人の働き方に政府の関与が少ない分、企業が中心となって自主的にWLBにかかる取組みが行われているのがアメリカの特徴である。
 さらに差別禁止法による規制は強力であり、男女役割分業など男女の性に関する伝統的固定観念を排斥、妊娠・出産差別についても、不利益な取扱いを差別とすることで、男女平等の実現を志向し、それがWLB推進の一助となっている。
さらに差別禁止法による規制は強力であり、男女役割分業など男女の性に関する伝統的固定観念を排斥、妊娠・出産差別についても、不利益な取扱いを差別とすることで、男女平等の実現を志向し、それがWLB推進の一助となっている。
ご講義のあと、全員で日本の労働環境の課題や、WLB政策を有効にするための政策提言のあり方について、ディスカッションを行った。
各国のWLB制度の比較研究については、独立行政法人 労働政策研究・研修機構 報告書
「ワーク・ライフ・バランス比較法研究〈中間報告書〉」 を参照下さい。
・2012.02.11 公開講座『育メンと育児休業制度:個人と行政の視点から』
・2012.01.18 政策研究「日本の『WLB』政策 その批判的検討と改革の方向」
・2011.10.30 シンポジウム「養育環境の現代課題“子ども・子育て新システムをめぐって」
・2011.10.13 公開報告会「アメリカ女性のワーク・ライフ・バランス」
・2011.06.10 公開講座【アメリカでワーク・ライフ・バランス施策が求められる理由】大沢真知子氏
・2011.06.09 公開シンポジウム【WORKFAM 2010年度事業報告】
・2011.06.07 【アメリカにおけるワーク・ライフ・バランス関連法制度について】池添弘邦氏