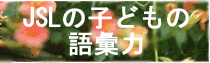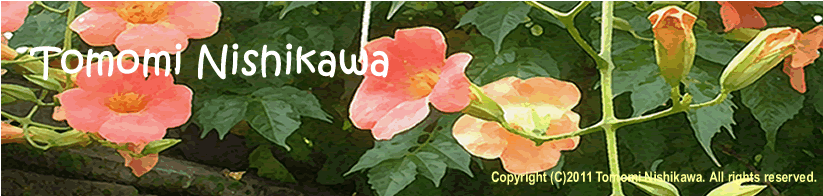
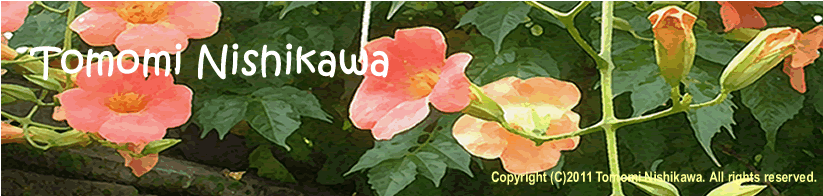
■MY NOTES
CONTACT
〒112-8610
東京都文京区大塚2-1-1
2-1-1 0tsuka, Bunkyo-Ku,
Tokyo 112-8610 JAPAN
nishikawa.tomomi <at> ocha.ac.jp
■ RESEARCH
研究テーマ Research Interest
■ 第二言語習得における臨界期仮説・年齢要因
修士課程の学生時代に、小学校で日本語を母語としない子どもたちと接しながら、Johnson & Newport (1989)の「7歳」の壁は、設定が遅すぎるのではないかと思ったのが、きっかけです。
■ バイリンガルの語彙能力
上の臨界期仮説・年齢要因の研究は、語彙は対象外とされることもあります。しかし、実際にバイリンガルの子どもの教育においては、語彙力はかなり重要な位置を占めていると思います。こちらは、まだ手をつけ始めたばかりの研究分野です。
■ 継承語の習得研究
ハワイ大学在学中に「継承語としての日本語習得」に関わるプロジェクトに参加する機会があり、興味を持ちました。日本で、ベトナム系児童の継承語調査を行ったこともあります。
■ 日本語関係節の習得研究
博士論文で、調査対象とした言語項目が関係節でしたので、こちらにも少し興味があります。
科学研究費プロジェクト Research Projects
■ 「日本語を母語としない子どもの語彙とコロケーションの知識に関する研究」2011~2014年度、科学研究費・基盤研究C、課題番号23520619、研究代表者 [Website:関係者のみ]
■ 「子供の第二言語としての日本語能力の研究-母語能力との関連に注目して-」2008~2009年度、科学研究費・若手研究B、課題番号20720136、研究代表者
論文・Papers
西川朋美(印刷中)「おとなの語学力の発達(特集:おとなの発育発達)」『子どもと発育発達』第13巻,第3号
西川朋美(2015)「子どもを対象とした日本語のSLA研究の可能性-SLA研究と年少者日本語教育の接点を探る-」『言語文化と日本語教育』48/49合併号,32-40.
西川朋美・青木由香・細野尚子・樋口万喜子(2015)「日本生まれ・育ちのJSLの子どもの日本語力-和語動詞の産出におけるモノリンガルとの差異-」『日本語教育』160号,64-78.
Nishikawa, T. (2014). Nonnativeness in near-native child L2 starters of Japanese: Age and the acquisition of relative clauses. Applied Linguistics, 35, 504-529.
西川朋美(2014)「『母語話者レベル』のL2能力に関する一考察-YNU書き言葉コーパスの『超』上級日本語学習者を対象に-」金澤裕之(編)『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』ひつじ書房
西川朋美・青木由香・細野尚子・樋口万喜子(2013)「子どものL2能力評価における母語話者基準とは?-動詞に焦点を当てた語彙力調査の結果から-」2013 CAJLE Annual Conference Proceedings, 190-199. 【PDF】
西川朋美(2012)「JSLの子どもを支える教員の養成-日本語教育分野からの貢献-」『横浜国大国語研究』第30号、1-13.
西川朋美(2011)「『小学校の日本語教育スペシャリスト』の養成-小学校教員養成課程・日本語教育専攻の取り組み-」『学校の多文化化で求められる教員の日本語教育の資質・能力とその育成に関する研究』(pp.95-115)、平成19~22年度科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書、研究代表者 齋藤ひろみ
西川(長谷川)朋美(2011)「在日ベトナム系児童の継承語としてのベトナム語能力」『母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)研究』第7号、46-65.【PDF】
長谷川朋美(2008)「第二言語習得における臨界期仮説・年齢要因 ?日本語を対象とした研究に向けて?」『第二言語習得・教育の研究最前線―2008年版―:言語文化と日本語教育 2008年11月増刊特集号』、107-137. 【PDF】
Kanno, K., Hasegawa, T., Ikeda, K., Ito, Y. & Long, M. H. (2008). Prior language-learning experience and variation in the linguistic profiles of advanced English-speaking learners of Japanese. In D. Brinton, O. Kagan & S. Bauckus (Eds.), Heritage language acquisition: A new field emerging (pp. 165-180). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hasegawa, T. (2008). Measuring the Japanese proficiency of Japanese heritage language children. In K. Kondo-Brown & J. D. Brown (Eds.), Teaching Chinese, Japanese, and Korean heritage students: Curriculum, needs, materials, and assessment (pp.77-97). Mahwah, NJ. Lawrence Erlbaum Associates.
Hasegawa, T. (2005). Relative clause production by JSL children. In M. Minami, H. Kobayashi, M. Nakayama & H. Shirai (Eds.), Studies in Language Sciences (4): Papers from the Fourth Annual Conference of the Japanese Society for Language Sciences (pp. 189-204). Tokyo: Kuroshio Publishers.
Kanno, K., Hasegawa, T., Ikeda, K. & Ito, Y. (2005). Linguistic profiles of heritage bilingual learners of Japanese. In J. Cohen, K. McAlister, K. Rolstad & J. MacSwan (Eds.), Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism (pp.1139-1151). Somerville, MA: Cascadilla Press.
菅野和江、長谷川朋美、池田佳子、伊藤泰子(2005)「習得環境の違う日本語上級学習者の言語知識プロファイル」. Journal of the Canadian Association for Japanese Language Education: Japanese Linguistics and Pedagogy, 7 , 1-22
長谷川朋美(1999)「イギリスの小学校における「トピック学習」:日本の小学校に通う外国人児童とイギリスの小学校でのわたし」『横浜国立大学国語教育研究』第11号、1-16.
テキスト・Textbooks
西川朋美(2011)『子どもの日本語教育』(私家版テキスト、約100ページ)、横浜国立大学教育人間科学部
長谷川朋美(1999)「日本語のレッスン」府川源一郎・高木まさき・長編の会編『合科的・総合的な学習のための読書関連単元100のプラン集』(pp.180-181)東京:東洋館出版社
その他・Other Written Work
西川朋美(2012)「前期実習を振り返って」横浜国立大学教育人間科学部日本語教育コース(2011年度)『日本語教育実習報告書-外国人児童・生徒・成人を対象として-』(pp.3-8)、横浜国立大学教育人間科学部日本語教育運営委員会
西川朋美(2011)「前期実習を振り返って」横浜国立大学教育人間科学部日本語教育コース(2010年度)『日本語教育実習報告書-外国人児童・生徒・成人を対象として-』(pp.3-4)、横浜国立大学教育人間科学部日本語教育運営委員会
西川(長谷川)朋美(2010)「前期実習を振り返って」横浜国立大学教育人間科学部日本語教育コース(2009年度)『日本語教育実習報告書-外国人児童・生徒・成人を対象として-』(p.3)、横浜国立大学教育人間科学部日本語教育運営委員会
長谷川朋美(2009)「前期実習を振り返って」横浜国立大学教育人間科学部日本語教育コース(2008年度)『日本語教育実習報告書-外国人児童・生徒・成人を対象として-』(pp.1-2)、横浜国立大学教育人間科学部日本語教育運営委員会
長谷川朋美(2008)「前期実習を振り返って」横浜国立大学教育人間科学部日本語教育コース(2007年度)『日本語教育実習報告書-外国人児童・生徒・成人を対象として-』(pp.1-4)、横浜国立大学教育人間科学部日本語教育運営委員会
長谷川朋美(2007)「小学校の国際教室にて」『横浜国大国語教育研究』第27号、1-2.
講演・Invited Talks
西川朋美(2013)「バイリンガルの子どもの言語習得-「できない」ことにも正面から向き合える 年少者日本語教育を目指して-」日本言語文化学研究会第45回研究会講演、お茶の水女子大学
西川朋美(2013)「日本語のSLA研究に大切なもの-世界の中に自分を位置付けるグローバルな視点-」第85回第2言語習得研究会(関東)講演、お茶の水女子大学
Nishikawa, T. (2012). Age effects in SLA. JKC2012, Ochanomizu University.
長谷川朋美(2009)「第2言語習得と臨界期仮説-小学校日本語教育現場から第2言語習得理論へ-」第69回第2言語習得研究会(関東)講演、お茶の水女子大学
長谷川朋美(2008)「小学校の日本語の先生?」横浜国立大学国語・日本語教育学会講演、横浜国立大学
発表・Presentations
細野尚子・西川朋美・青木・由香(2015)「日本生まれ・育ちのJSLの小中学生の和語動詞の産出力-日本語モノリンガル幼児との比較-」2015年度第3回日本語教育学会研究集会(富山・富山大学)
青木由香・西川朋美・細野尚子・樋口万喜子(2014)「日本生まれ・育ちのJSLの子どもの≪日常語彙≫の産出能力-小1~中3調査の結果と誤答の分析-」日本語教育学会秋季大会,富山国際会議場
樋口万喜子・西川朋美・細野尚子・青木由香(2014)「日本生まれ・育ちのJSLの子どもの《日常語彙》の産出能力-小学校高学年調査の結果-」日本語教育学会春季大会,創価大学
西川朋美・青木由香・細野尚子・樋口万喜子(2013)「子どものL2能力評価における母語話者基準とは?-動詞に焦点を当てた語彙力調査の結果から-」Canadian Association for Japanese Language Education Annual Conference 2013, University of Toronto, Canada. (ポスター発表)
吉田綾・伊藤智美・赤木美香・西川朋美(2013)「対象者の言語レベルはどのように判断・記述するべきか-『第二言語としての日本語の習得研究』における対象者の記述の分析から-」お茶の水女子大学日本言語文化学研究会第46回研究会(ポスター発表)
西川朋美・樋口万喜子・細野尚子・青木由香(2013)「JSLの子どもにとっての≪日常語彙≫-動詞に焦点を当てた語彙力調査に向けて-」日本語教育学会春季大会、立教大学(ポスター発表)
西川朋美・樋口万喜子・細野尚子(2012)「JSLの子どもの教科の学びを支える≪日常語彙≫」日本語教育学会春季大会、拓殖大学(研究協力者:青木由香)(ポスター発表)
西川朋美(2010)「教員養成課程・日本語教育専攻における『日本語教育実習』の取り組み」パネルセッション(代表:齋藤ひろみ)「学校の多言語・多文化化に対応する教員を養成するための教育課程について考える?教員養成系大学における日本語教育コースの取り組みから?」日本語教育学会秋季大会、神戸大学
Nishikawa, T. (2010). Vietnamese as a heritage language in a Japanese public elementary school. Fourth Summer Heritage Research Institute: Heritage Speakers: Linguistics and Pedagogy, as part of the Panel "Teaching and research for heritage learners of Asian and Pacific languages" organized by Kimi Kondo-Brown, University of Hawaii at Manoa.
西川朋美(2010).「外国にルーツを持つ子どもを対象とした日本語教育実習@横浜国立大学」外国にルーツをもつ子ども(外国籍児童生徒)の教育と学校教員について考える研究会、宮城教育大学
長谷川朋美(2009)「在日ベトナム系 バイリンガル児童の 言語能力」2009年度MHB研究大会、立命館大学
Hasegawa, T. (2009). Growing up as Vietnamese-Japanese bilinguals: Vietnamese heritage children in Yokohama. Port-City University League (PUL), The 4th Meeting, Yokohama National University, Japan.
Hasegawa, T. (2008). Multilingualism in Yokohama, Port-City University League (PUL), The 3rd Meeting, University of Lisbon, Portugal.
Hasegawa, T. (2008). Relative clause comprehension and production by young L1/ L2 speakers of Japanese. Second Language Research Forum 2008, University of Hawaii at Manoa.
Hasegawa, T. (2008). The uninevitability of native-like attainment in child L2 acquisition of Japanese. The 9th Annual Tokyo Conference on Psycholinguistics, Keio University, Tokyo, Japan.
長谷川朋美(2007)「日本語を第二言語とする児童生徒の学習言語能力と統語能力の関係を探る」日本語教育学会春季大会、桜美林大学
Hasegawa, T. (2006). Native like knowledge without native like performance in (very) early child L2 acquisition. The 30th Boston University Conference on Language Development, Boston University, USA. (Poster Presentation)
Hasegawa, T. (2006). How native-like are early child L2 learners, really? The 8th Annual Conference of the Japanese Society for Language Sciences, International Christian University, Tokyo, Japan. (Poster Presentation)
Hasegawa, T. (2004). Producing marked relative clauses: What near-native child L2 Japanese speakers cannot do. The Second Language Research Forum 2004, Pennsylvania State University, USA
菅野和江・長谷川朋美・池田佳子・伊藤泰子(2004)「習得環境の違う上級学習者の言語知識プロファイル」言語科学会第六回年次国際大会、愛知淑徳大学 (ポスター発表)
長谷川朋美(2004)「年少日本語学習者の格助詞の習得に関する研究」日本語教育学会春季大会、東海大学
Kanno, K., Hasegawa, T., Ikeda, K., & Ito, Y. (2003). Linguistic profiles of advanced English-speaking learners of Japanese. The 6th National Council of Organizations of Less Commonly Taught Languages, as part of the Colloquium "Profiling the Advanced LCTL Learner" organized by Michael H. Long and Catherine J. Doughty, University of California, Los Angeles, USA.
Kanno, K., Hasegawa, T., Ikeda, K., & Ito, Y. (2003). Linguistic profiles of bilingual learners of Japanese. The 4th International Symposium on Bilingualism, Tempe, Arizona, USA.
Hasegawa, T. (2002). The acquisition of Japanese relative clauses in child SLA. The Second Language Research Forum 2002, University of Toronto, Canada.
長谷川朋美(2002)「第二言語としての日本語における関係節の習得研究-年少者の場合-」言語科学会第四回年次国際大会、日本女子大学
長谷川朋美(2001)「外国人児童の複文使用の実態―インタビューと7ヶ月間の授業記録より―」第34回第二言語習得研究会、お茶の水女子大学
宇土泰寛・玉井裕子・長谷川朋美(2001)「地球子供教室における日本語学習空間―テキストからコンテキストを重視したカリキュラムへ―」日本国際理解教育学会第11回大会
宇土泰寛・玉井裕子・長谷川朋美(2000)「多文化共生を目指した協動的実践研究―「地球子供教室」における日本語学習を通して―」日本国際理解教育学会第10回大会