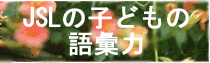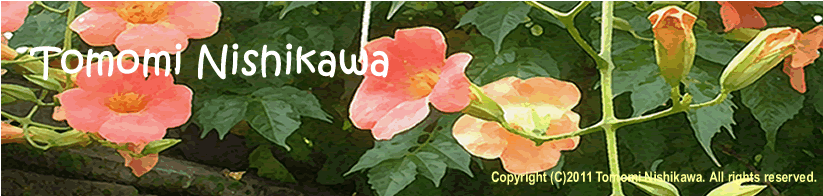
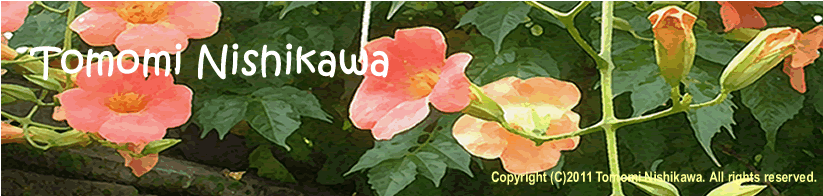
■MY NOTES
CONTACT
〒112-8610
東京都文京区大塚2-1-1
2-1-1 0tsuka, Bunkyo-Ku,
Tokyo 112-8610 JAPAN
nishikawa.tomomi <at> ocha.ac.jp
■ COURSES
ゼミ・SEMINAR
ゼミのテーマは、第二言語習得(SLA)です。第一言語習得では、100%に近い確率で「ネイティブ」と呼ばれる言語能力を身に付けることができるのに対して、第二言語習得では、非常に個人差が大きいです。そのメカニズムを解明するのが、第二言語習得研究の目標の一つです。私自身は、その中でも特に年齢要因に興味があり、学生時代から、幼児から大人まで幅広い年齢層の学習者を相手に研究を行ってきました。
なお、SLA分野で、第一線の研究を理解するためには、英語で論文を読む力は不可欠です。最初から、完璧に英語論文を読みこなせなければいけないと言う訳ではありません。ただ、英語論文を読むのは絶対にイヤだというに人は、たとえ日本語の習得研究と言えども、SLA研究はおすすめできません。
[西川ゼミWebsite:関係者のみ
授業・CLASSES
| 大学院博士後期課程 | 第二言語習得論/同演習(ゼミ) |
| 大学院博士前期課程 | 応用日本言語学研究法実習(日本語教育コースM1必修) 言語学習論特論/同演習 第二言語習得特論/同演習(ゼミ) |
| 学部(副プログラム) | 第二言語教授法演習Ⅰ(副プログラム必修) 日本語教育学特殊講義 日本語非母語話者年少者教育学概論 日本語教育学研究法実習 |
| 留学生科目 | 日本事情演習ⅡA/B |
研究生を希望される方へ
まずは、SLAという分野がどのようなものかを知るために、概説書を数冊しっかりと読み込むことをお勧めします。メールで送られてきた研究計画書を拝見すると、他の分野の先生の指導を受けたほうが良いと思うものが、多々あります。そして、本当に自分が勉強したい分野がSLAだと確信したら、なぜお茶大の研究生になりたいのかを良く考えてみてください。「お茶大は素晴らしい大学だから」というような理由は、期待していません(素晴らしい大学であることには間違いありませんが)。他大学のこともしっかりと調べた上で、なぜお茶大が良いのか、しっかりと考えてみてください。また、具体的な研究計画を考えるに当たっては、そのテーマに関する専門的な論文をある程度は読み、どこまでが解明されていて、さらに深く追求していくべき課題は、何なのかを考えてみてください。「一緒にその課題の答えを見つけてみたい」と思える研究計画書をお待ちしています。
まずは、日本語教育コースのHPをスミからスミまで読んでください。研究計画書作成に当たっての、先輩たちからのアドバイスもあります。
上記のことが分からない研究計画書をお送りいただいても、お返事はできないと思いますので、ご了承ください。 また、研究生の受け入れを決める際には、書類選考のあと、面接を行わせていただきます。