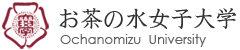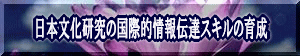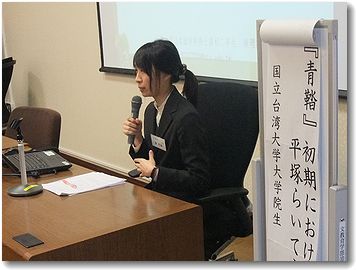第四回「国際日本学コンソーシアム」日本文学部会は、十一名の発表者を迎え、例年にもましての盛会であった。各発表者の発表内容については、別項に掲載されているので、ここでは、当日の発表・議論によって喚起された問題意識をめぐり、所感の形で述べることとする。
今回の発表のひとつの特徴は、発表者の関心が日本の〈戦後問題〉に集まったことである。「もはや戦後ではない」との『経済白書』(1956)の一文は、実情をはなれ一人歩きした感が強いが(実際は、宮本輝『泥の河』が見事に形象化しているように、昭和30年代の日本は戦後状況のさなかにある)、あらためて、2009年の現在は〈戦後〉なのだろうか。言い換えれば、日本はいつ、どのようにして、真に〈戦後〉の終結を自信を持って宣言することができるのだろうか。 申河慶氏による「大衆文化からみるBC級戦犯裁判と「責任」」は、1959年と2008年の二回にわたって制作された映画『私は貝になりたい』をめぐり、きわめてアクチュアルな問題意識を提出したものである。不明にして知らなかったが、氏によれば両作の脚本はともに橋本忍による。しかし、両作には根本的な差異が存在する。それは「戦争責任」の配置をめぐる問題である(詳細は氏の文章を参照されたい)。とすれば、ここでもっとも私たちが考えるべきは、なぜ、この二つめの『私は貝になりたい』が、日本の〈いま・ここ〉において再映画化されねばならなかったか、ということである。それはどのような日本の現在を表象し、どのような〈私たち〉の欲望を映し出すのか。 2000年代に入り、〈大東亜戦争〉を〈愛のための戦いの物語〉として再解釈、というより、新たな語りの枠組みをもって再編する映画・テレビドラマが複数制作されたことは記憶に新しい。あからさまなナショナリズム昂揚の作品には、私たちは警戒心を抱く。とくに、若い世代の受容層は、その一部にネオ・ナショナリズムの傾向が見られるとしても、概して、ナショナリズムの昂揚には拒否感を表明するだろう。しかし、自分の手の中にいるこのいたいけな赤子、懐かしい年老いた母、愛するあなたを守るために、自分は戦わねばならない、と語られるとき、誰がそれに抗うことが出来るだろう。もっとも危険なのはセンチメンタリズムに満ちた(偽)愛の言説である。これらの言説は、言うまでもなく、自分の戦う相手にも同じく愛するわが子や母がいる、という自明の事実は巧みに隠蔽する。そして〈愛〉する人を守るため、というもっともシンプルにして説得力に満ちた思いとともに私は(あなたは)戦場に赴く。 このような言説に、私たちはどのようにすれば対抗できるだろうか。その方法のひとつが、まさにこの「国際日本学コンソーシアム」であると私は思う。「国際日本学」をめぐっては、理論・方法において未だ試行錯誤の途上にある。学問としての成熟にはまだまだ時間が必要であろう。しかし、もっとも重要なのは〈眼〉である。自明と思われる事柄を多様な方向から見つめる視線、すなわち多様にして多元の問題意識にこそ、「国際日本学」をかかげ、「コンソーシアム」を開催する意義が存する。そしてさらに言うなら、私たちが生きる〈いま・ここ〉において、文学を研究する意義もまた、ここに存する。種々の(偽)愛の言説は、巧みな〈物語〉の姿で現れる。私たちを誘惑するそのような〈物語〉に抗うために、私たちは〈物語〉の構造を熟知せねばならない。 研究と呼ばれる私たちの営為が、しかしつねに、私たちの〈いま・ここ〉を照射するものとなるとき、「国際日本学」はその真の一歩を記したことになるだろう。 【文責・菅 聡子】
(2010/01/05up) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||