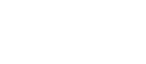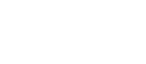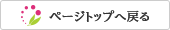ページの本文です。
XIAOZEXUAN
2025年5月20日更新
JSL環境の中国人日本語学習者の使役文・「てもらう」文の使い分けに関する習得研究
| 修了年度 | 2024度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | JSL環境の中国人日本語学習者の使役文・「てもらう」文の使い分けに関する習得研究 |
| 要旨 (1000字以内) |
使役文と「てもらう」文は典型的なヴォイス表現として、学習者にとって習得困難な文法項目であると考えられる。また、使役文と「てもらう」文は、他者の意志動作の引き起こしを表す事態に一定の共通性を持つとともに、待遇性や対人関係への配慮に関わる微妙な違いを表し分ける(早津 2005:134)。さらに、使役も「てもらう」も多くの場合では現代中国語で「让、叫、使(させる)」と訳せるので、中国人日本語学習者にとって習得しにくいことは想像に難くない。したがって、本研究では日本語を第二言語とする(Japanese as a Second Language、以下 JSL)中国人日本語学習者(以下、CJL)が同じ事態を表現できる使役文と授受補助動詞「てもらう」文をどの程度使い分けることができるかを明らかにすることを目的とする。 調査対象者はJSL環境の中上級CJL 26名(下位群13人、上位群13人)と成人日本語母語話者(以下、NS)20名である。研究構成について、CJLにフェイスシート、SPOT調査、文法テスト、優先度テスト、アンケート調査、NSにフェイスシート、優先度テスト、アンケート調査を実施した。本研究では、使役文と「てもらう」文が互換可能な場面を、「他者利用性の性質を持つ「サセル」文と「テモラウ」文が置き換え可能である」、「被使役者が一人称であり、使役者を非難する場合が「使役型テモラウ」文と置き換え可能である」、「使役者が利益を受け取らないような「サセル」文と「テモラウ」文が置き換え可能である」3つ取り上げ、親疎関係を「親しい関係」と「疎遠な関係」を設定して優先度テストを作成し、実施した。優先度テストの得点を三要因混合分散分析した。 結果は、同じ事態を表現する時に、使役と「てもらう」の使用傾向は、習熟度が異なるCJLとNSの間で異なる。CJLの習熟度が高くなるほど、NSに近い使用が可能になると考えられる。また、使役と「てもらう」の使用傾向は場面と親疎関係の影響を大きく受けることが確認された。なお、使役と「てもらう」の使用傾向は単純に親疎関係によって決定されるわけではなく、場面との相互作用によって影響を受けることが示された。 また、CJLとNSの使い分けが異なる場合、その理由を検討した。習熟度がNSとの使い分けの差異を説明する一因であると考えられる。なお、アンケートでCJL とNSの判断基準を調査した。その結果、判断基準の違いも理由の一つと思われる。下位群、上位群、NSのすべてにおいて、「人物間の関係性(上下関係)」が最も重視されているが、各グループには違いも見られた。下位群は「判断基準がない」と回答した者が見られ、上位群とNSは、視点、文法の正確性、利益の有無など、多様な基準を考慮して判断を行う傾向がある。 |