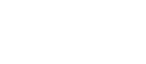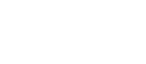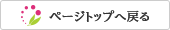ページの本文です。
黒木 里佳子
2025年5月20日更新
JSL高校生と日本人高校生による小論文の協働学習―ピア・レスポンスと振り返りに着目して―
| 修了年度 | 2024度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | JSL高校生と日本人高校生による小論文の協働学習―ピア・レスポンスと振り返りに着目して― |
| 要旨 (1000字以内) |
日本語指導が必要な児童生徒の数が増加する中、これまで生徒が日本語母語話者であることを前提としてきた高校でも、文化的・言語的な背景の異なる「多様な他者」が教室にいることを念頭に、授業の在り方を見直すことが求められている。 そこで本研究では、JSL 高校生と日本人高校生の両者が主体となって「水平的関係」のもとで対話し、協働できる授業の実現を目指して、小論文の協働学習授業を実施した。そして、そこでのピア・レスポンス中のやりとりと、学習者自身の振り返りから、両者の協働の可能性を探り、多様な他者の間に対話が生まれる授業づくりへの示唆を得ることを目的に次の 2 つの研究課題を設定した。 研究課題 1:JSL 高校生と日本人高校生は、小論文のピア・レスポンスにおいて、対称性のあるやりとりを行うか。 研究課題 2:JSL 高校生と日本人高校生は、小論文の協働学習をどのように振り返るか。 研究課題 1 について、3 人の JSL 高校生と日本人高校生 1 人の 3 つの組み合わせによるピア・レスポンス中のやりとりを、発話数と発話機能及び発話内容から分析した結果、JSL高校生と日本人高校生とのやりとりは、特に初期段階において非対称になる場合があるものの、その非対称性は固定的なものではなく、ピア・レスポンスを重ねる中で、やりとりの対称性が高まると共に、両者の関係性が作られていく様子が確認できた。またピア・レスポンスを通して、JSL 高校生と日本人高校生の双方が、互いの「発達の最近接領域」への働きかけを行っていることも示唆された。 加えて、研究課題 2 における、インタビューによる生徒の振り返りから、それぞれの生徒が、考える幅の広がりや、内省の深まり、教師による指導にはないピア活動のメリットなど、協働学習の意義を感じていることが明らかになった。それらはいずれも生徒同士の「水平的相互作用」によってもたらされたものであると言える。 「協働学習」とは、「複数の人が課題解決や目標達成のために、その過程を共有し、やりとりを通して互恵的に学びあうこと」であるが、今回の研究結果は、JSL 高校生と日本人高校生という言語的・文化的な背景が多様な生徒の間でも、協働学習が互恵性のある活動として機能することを示唆している。 |