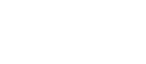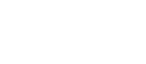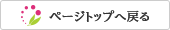ページの本文です。
劉 紫涵
2025年5月20日更新
「やさしい日本語」に関する認識―区役所職員と中国人留学生を対象として―
| 修了年度 | 2024度 |
|---|---|
| 修士論文題目 | 「やさしい日本語」に関する認識―区役所職員と中国人留学生を対象として― |
| 要旨 (1000字以内) |
法務省(2021)の統計によると、在留外国人は全体的に増加の傾向が見られ、様々な文化背景を持つ外国人と共生可能な環境作りが必要となっている(庵,2016)。しかしながら、多言語対応は理想であるが、実際は難しい(庵,2011)。このような状況の中、元々災害時の文脈から生まれた「やさしい日本語」が再定義され、平時における外国人への情報提供手段として観光など様々な分野で取り組みが広がっている。また、多文化社会における喫緊の言語政策課題の一つとして注目されてきた(嶋津,2011)。「やさしい日本語」により情報を発信する側の行政職員と情報を受け取る側の外国人がこの機能をどのように思っているかが不明である。そこで、本研究では、現在の区役所関係者及び日本在住中国人留学生の「やさしい日本語」に対する認識の様相を明らかにすることを目的とする。 研究手法としては、半構造化インタビューを主に用い、TA分析で参加者の「やさしい日本語」に対する認識を探った。これに加え、ロールプレイを通じて実際のコミュニケーションの場面を再現し、その中での言語の使用や調整の実態を把握した。また、フォローアップインタビューを実施し、初回のインタビューで得られたデータの詳細な分析を行い、NNSから5段階でNSの説明を評価してもらった。 結果としては、本研究の協力者である区役所の職員および中国人留学生全員が「やさしい日本語」を、意思疎通に役立つ調整ストラテジーとして位置づけていると認識していること、また、言語調整の前に、お互いを尊重し合う姿勢が重要視されていることも確認できた。留学生は「やさしい日本語」をNSによる好意的な配慮のための言語調整と捉える一方で、行政職員との間には言語使用の認識のギャップも見られた。職員は、区役所という公的場面において生じるさまざまな葛藤から「やさしい日本語」の限界を感じ、「やさしい日本語」はコミュニケーションの円滑化に一役買っているが、それだけでは完全な解決には至らず、更なる調整やサポートの必要性が明らかになった。 この結果を基に、今後の課題として、一般化に向けて、研究の範囲を広げることや、ロールプレイの内容のさらなる検討、実際の区役所の現場での問題点の詳細な把握が必要とされる。 |