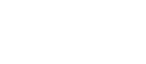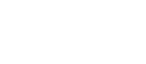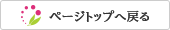ページの本文です。
Q&A 入学準備・福利厚生・進路・その他
2024年5月16日更新
入学準備
【問】合格していることがわかったら、大学に足を運ぶ必要がありますか?
【答】
試験結果は構内掲示の他、入試課を通じインターネットや郵便でもお知らせします。コース室からも、合格者へメールを送付します。
なお、合否の問い合わせに対しては、コース室では御答えできません。
【問】大学院での専門教育についていけるかどうか心配です。合格したら入学前にどのような準備をすればいいでしょうか?
【答】
修士課程合格者には、入学するまでに読んでおいたらいい本やその他の注意事項を記載した『入学前準備ガイド』を提供して大学院生活に備えてもらっています。(この資料の一部は、日本語教育コースのホームページ上でも閲覧できます。)
【問】合格したら入学前にさっそく宿題が出ると聞きましたが…。
【答】
他のことが全くできなくなるほど膨大な課題を課するわけではありませんが、入学前に読んでおいたらよい文献のリストや考えておいてほしい論題は合格発表と同時にお伝えすることにしています。
なぜなら、4月からの専門教育を順調に開始できるようにするためには、2月の合格発表から4月の授業開始までの約2か月間を有効に活用して準備を進めることはかなり重要であると考えられるからです。(新学期が始まるとさっそく授業やプロジェクトに忙殺される日々が始まり、夏も実習や集中講義が予定されていますので、入学前の春休みを逃せば、その次に各自の興味にあわせ文献を探してじっくり読んだり考えたりする時間が長期にわたってとれるのは早くて一年後の春休みになってしまいます。)それを考慮した上での「宿題」です。
福利厚生 ・財政援助
【問】奨学金制度はどうなっていますか?
【答】
次のページをご覧ください。
https://www.ocha.ac.jp/campuslife/scholarship/about.html
なお、日本人学生の方も含めて、入試合格者への案内に奨学金情報をまとめた冊子が同封されていますので、そちらもご参照ください。詳しくは学生・キャリア支援課までお問い合わせください。
【問】学生寮はありますか?
【答】
日本人学生の場合
「音羽館」、加えて大学から歩いて5分ぐらいのところにある「小石川寮」が日本人用の宿舎です。
外国人留学生の場合
「音羽館」が留学生向けの宿舎です。
入寮申し込み者が多数の場合、財政状態・宿舎の必要性などの条件を考慮したうえ選抜が行なわれます。詳しくは学生課に問い合わせてください。
詳細はこちらからご確認ください。
なお、どちらの寮に入居しても所定の手続きをとればインターネットに常時接続することができます。
【問】子供を連れて通学することはできますか?
【答】
現在、学内に有料の保育所(いずみナーサリー)が開設されています。
また生活科学部本館2の1階にはベビーベッド付きの授乳室(ベビールーム)があり、その他にも学内におむつ替えできる場所が12箇所あります。
本学における各種子育て支援については、こちらのページをご覧ください。
修了後の進路/博士後期課程
【問】就職先に関する情報はどうやって入手したらいいでしょうか?
【答】
お茶の水女子大学の日本語教育コースには、国内外の様々な日本語教育機関から公式/非公式に求人情報や教員紹介依頼が寄せられてきます。現に、その紹介で就職を決めた修了生も少なくありません。
しかし、そういったルートだけに頼り切るのではなく、自分でも積極的にインターネットや印刷媒体その他の経路を通じて就職情報を探索することをお勧めします。アンテナの広がりと粘り強さは就職活動において不可欠です。
それとともに、いざ機会が訪れた時に、それを受けるか断るか迅速に決断ができるような物心両面の準備を普段からしておくことも大切です。
【問】修士課程を修了した後、博士後期課程に進みたいと思っています。希望者は全員入学できるのでしょうか?
【答】
博士後期課程進学にあたっては、学内からの進学希望者も学外からの応募者と同一の基準に照らしあらためて入学試験を行ないます。他学科の教員を含めた審査員が修士論文研究の内容や今後の研究計画を詳しく審査しますので、全員が入学できるとは限りません。
【問】博士論文では過去にどのようなテーマがとりあげられているのでしょうか?
【答】
次のページを参照してください。
「お茶の水女子大学 博士授与名簿」
お茶の水女子大学博士論文リスト | お茶の水女子大学図書館 (ocha.ac.jp)
その他の質問
【問】お茶大日本語教育コースの現況をもっと詳しく知るためには、どうすればいいでしょうか?
【答】
在校生や修了生と知り合いになって話を聞くためには、例えば次のような学内研究会/学会/発表会に参加なさるとよろしいでしょう。
日本言語文化学研究会 + 大学院進学相談説明会(同日開催)
https://www.dc.ocha.ac.jp/comparative-cultures/jle/genbun/
第2言語習得研究会例会
https://kasla.jimdo.com
修士論文発表会 (1月末または2月初旬)
博士論文発表会
これらは全て、学外者に対しても公開されており、予定は日本語教育コースのホームページ上にも掲示されます。(日本言語文化学研究会と第2言語習得研究会は会員制組織ですが、非会員でも所定の参加費をはらえば会合に参加できます。)
なお、せっかくお目にかかってお話しする機会が持てるのであれば、このホームページやそのリンク先・各種印刷媒体を含め公開されている情報にはあらかじめ目を通し、質問のポイントを絞ってから来てくださるとお互いにとって実りの多い時間となるでしょう。
【問】研究生・科目等履修生・聴講生になるにはどうすればいいのですか?
【答】
「科目等履修生、聴講生、研究生の募集について」
http://www.ocha.ac.jp/campuslife/r_auditor/
【問】研究生になることを申し込んだら必ず受け入れてもらえるのでしょうか?
【答】
現有の研究生の数や教員の担当状況によっては、お断りせざるをえない場合もあります。