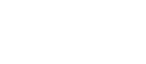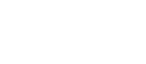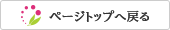ページの本文です。
Q&A 入学審査について
2021年9月15日更新
入学試験全般
【問】募集要綱はどうすれば入手できますか?
【答】
入試課のホームページから次の情報が入手できます。
「大学院博士前期課程 学生募集要項」
「大学院博士前期課程 外国人留学生 学生募集要項」
【問】大学院入試の倍率はどのぐらいですか?
【答】
倍率を意識して合格者数を調整しているわけではありませんが、結果的にはここ数年、日本語教育コースの全受験者のうち3分の1から2分の1前後が合格しているのが通例です。
【問】何人ぐらいが合格するのですか?
【答】
入学定員は12名です。年によっては、定員を数名程度超過して入学許可を出した例も過去にありました。
【問】一度受験して不合格だった場合、翌年以降に再受験するのは無駄でしょうか?
【答】
捲土重来の末合格を勝ち取った実例は多数あります。また、修士課程の入試に不合格だった人が他校の大学院に進んでから、本学の教員が主宰する研究プロジェクトに参加したり、博士後期課程進学時にお茶の水女子大学を再受験して合格した例もあります。合否に関わらず、「面接試験は面接官に顔を売る機会だ」というぐらいの気持ちで、前向きにとらえてください。
【問】お茶の水女子大学の修士課程では、日本語教育専攻と日本語学専攻は入試方法が異なるのですか?
【答】
はい、博士前期(修士)課程の日本語教育コースと日本語日本文学コース(日本語学・日本文学)は別の専攻で、入試もそれぞれ別個に行なわれます。この二つの専攻は試験日が重なっています(二月初旬)ので、同じ年に両方を受験することはできません。
【問】お茶の水女子大学の入試に関する情報はインターネット上で公開されていますか?
【答】
はい、次のページを参照してください。
「お茶の水女子大学 入試情報」 http://www.ao.ocha.ac.jp/
受験資格・適性
【問】社会人枠入試の受験資格の「2年間以上の日本語教育経験」とは、具体的にはどういう経験のことを指すのですか?連続して2年間勤務していなければいけないのですか?
【答】
この場合「日本語教育経験」とは、職務経験を証明するための正式な書類を発行できる、社会的に認知された機関での経験を指します。国内外の各種日本語教育機関(大学・日本語学校など)や政府機関(JICA、国際交流基金など)による海外派遣の他、地方自治体が主催するボランティア日本語教室などでも構いません。
勤務年限は通算して2年間の勤務経験があればよく、連続している必要はありません。
【問】実務経験がないのは不利ですか?
【答】
合否判定にあたっては、実務経験・専門知識・研究実績・言語技能など様々な角度からの評価を勘案します。日本語教育の経験や実績があれば判定にあたって一つの有利な材料にはなりえますが、それがなくとも他の点で優れた資質・適性を示すことができれば合格のチャンスは大いにあります。
【問】日本語教育能力検定資格についてはどのように扱われますか?
【答】
日本語能力検定試験合格を大学院の入学資格の一つに数えているわけではありませんが、能力検定を目指して勉強することは、幅広い関連知識を一通り通覧する機会としては有益でしょう。特に大学新卒者など実務経験の少ない方には、日本語教育専門家に至る一つの中間目標として検定試験を受験することもいいでしょう。
ただし、多肢選択などの客観式テストが多い能力検定試験と論述式の大学院入試とでは出題形式や問われる知識の深さが大きく異なりますので、検定試験に受かったからといってそれだけで、大学院入試で高得点をとれるという保証はありません。検定試験対策用の入門的な参考書の域にとどまらず、入試に先立っては各分野の専門的概説書にも目を通しておくことが必要でしょう。
【問】日本語教育能力検定試験の出題範囲が最近拡大されたと聞きましたが、その変化は大学院の入試問題にも反映されるのでしょうか?
【答】
順序はむしろ逆です。異文化間コミュニケーションや第二言語習得などは、日本語教育学の重要領域として従来から大学院で力を入れて研究されてきたものです。それらの領域がこれまで能力検定試験に充分に反映されていなかったのを是正するため、平成15年に検定試験の出題範囲が大幅に改定され、さらに平成23年に再度改定されました。
【問】教職免許をもっていると合否判定で有利ですか?
【答】
教職免許の有無自体が入試判定の決定的な判断材料になることはありません。
とはいえ、教職免許を取得する過程で学んだ関連知識や教員としての実務経験が日本語教育専門家としての教育・研究活動に様々な形で活かされた例は過去に多くあります。(国語はいうにおよばず、それ以外の教科/類別、例えば英語・社会科・音楽・体育・小学校などの教職免許をもって日本語教育の道に入って来られる方も少なくありません。)
また、教職免許に限らず、多様な知識技能や経験を持った人達が入学してこられることが望ましいので、自分の能力や実績は遠慮なくアピールしてください。
【問】一般入試の合格者は言語学系の学科の卒業生が多いと聞きました。それ以外の専攻だと不利な判定を受けるのでしょうか?
【答】
そんなことはありません。むしろ、心理学・認知科学・教育学・人文諸科学・社会科学や自然科学・工学なども含め、様々な背景知識を持った人達が入学して来られることによって日本語教育研究が多様化・活性化することを期待しています。現に、実験心理学的な言語処理研究、発達心理学的な会話コーパス分析、社会調査的手法をもちいた調査研究、異文化間心理学の枠組みにもとづくコミュニケーション研究、あるいはコンピューター通信・計算機言語学などの知識技能を外国語教育研究に活かせる場はどんどん広がっています。特に他専攻から受験する場合は、審査にあたる側としてもその応募動機が自ずと気になりますので、どうして日本語教育専門家を志すに至ったのかをわかりやすく説明すれば、審査官を納得させやすくなります。
また、最近では経営学・工学・看護学など学習者の専門分野での訓練研究を視野に入れた実戦即応の日本語準備教育が脚光を浴びていますので、専門職業人としての高度な知識技能を有する人材は日本語教師の候補としても貴重な存在です。
【問】学部時代の専攻が言語や教育とは全く無関係な分野だったので、大学院での専門教育についていけるかどうか自信がないのですが…。
【答】
言語や教育に関する基礎的な知識は日本語教育に関する研究を行なう上で必須ですが、修士課程に新しく入学してくる学生は言語学や外国語教育の専門家ばかりではないことを念頭において指導計画を立案しています。
とはいえ、そういった配慮の上にいつまでもあぐらを書いていては進歩は望めません。大学院生として入学した以上、入学前の経歴に関わらず一定水準以上の成果を達成することが当然のこととして要求されます。そのために必要な知識が不足しているなら、
- 入学するまでに関連文献を読んでおく
- 放送大学などを活用して基礎知識を補充する
- 学部生向けの基礎科目を聴講する
- 自主ゼミを結成したり学外の研究会に参加したりする
- 専門家のメーリングリストに加入する
など自分で智慧を絞ってその不足を補うことが「勉強のプロ」たる大学院生の腕の見せ所です。
過去の例をみても、こういった努力をたゆまず重ねた学生は着実に実力を伸ばしています。現に他分野の学部課程から日本語教育コースに入学してきて秀逸な修士論文や博士論文を書き上げ、学界で活躍している先輩が数多くいます。
【問】私はお茶の水女子大学の卒業生ですが、学部時代の専攻が言語文化学ではなく在学中に副プログラムの科目の受講しませんでした。入試では不利になるでしょうか?
【答】
在学中に日本語教育基礎コース科目を履修しなかったこと自体が理由で不合格になることはありません。受験者は全員同じ基準で採点評価されます。 ただし、これまでに関連分野の勉強を本格的にしたことがないのであれば、専門試験で高得点をあげるためには余分に勉強をしていただく必要があるでしょう。
【問】私は他の大学の3年生ですが、将来お茶の水女子大学大学院の日本語教育コー スを受験することを希望しています。その準備としてお茶大の日本語教育基礎コースの授業を履修あるいは聴講したいのですが、他大学在学中にお茶大の科目等履修生になることは可能でしょうか?
【答】
過去にはそういう事例もあります。ただし、大学によっては、自校在学者が別の大学の授業を履修することに厳しい制限を設けている場合もありますので、まずは自校の方針を確認してください。また、本学の側にも科目等履修生として受け入れるためには資格要件があるので、詳しくは入試課に問い合わせてください。
【問】研究生や科目等履修生・聴講生になると、翌年の大学院入試で有利ですか?
【答】
いいえ、特に有利不利ということはなく、外部からの受験者と全く同じ基準で採点します。
なお、10名前後の大学院入学定員に対し、研究生になりたいという希望は毎年何十件もありますので、たとえ研究生として受け入れられたとしても翌春の入学試験で合格するという保証は全くありません。
【問】私は既に修士号をひとつ持っているのですが、博士前期(修士)課程の日本語教育コースと博士後期課程の応用日本言語論講座を同じ年に受験することはできますか?
【答】
はい、できます。例年、博士前期(修士)課程の入試は二月、博士後期課程の入試は三月にあり、両方に出願・受験できます。両方とも合格してからどちらに入学するか決めることもできます。
【問】私は男ですが、お茶の水女子大学で日本語教育学を勉強したいと思います。何か方法はありませんか?
【答】
男性が正規の学生として本学に入学することはできないので、学士・修士・課程博士の学位を取得することもできません。また、聴講生、学部レベルの科目等履修生や研究生も女性に限られています。
ただし、単位互換協定を結んだ他大学からの交換学生としてであれば、男女を問わず大学院あるいは学部の授業に出ることが可能です。
また、研究をまとめて論文を提出し審査に合格すれば男性も本学の論文博士号を取得することができます。 (この場合、授業科目を履修する必要はありません。)
提出応募書類
【問】卒業論文のテーマは日本語教育と関係がないのですが、日本語教育に関する論文をあらためて別に書き提出しなければならないのでしょうか?
【答】
一般入試枠の受験者の場合は卒業論文またはそれにかわる報告書を提出することが必須ですが、論文のテーマは何であっても構いません。新卒予定の方でしたら、今書いている卒業論文(の草稿)をそのまま提出して差し支えありません。
【問】研究計画書はどの程度詳しく書けばいいのでしょうか?
【答】
入学審査の段階で審査教員が主に注目するのは、例えば次のような点です。
- どうして当該分野に興味を持ったのか
- 研究興味と研究計画案と将来設計の間に整合性があるか
- 研究分野の背景について基礎的な知識を有しているか
- 研究課題(リサーチクエスチョン)がはっきりしているか
- 研究課題(リサーチクエスチョン)の意義(必要性)をきちんと説明できているか
- 研究課題(リサーチクエスチョン)と研究アプローチの方向に整合性があるか
- 研究を進めるために必要な基本的な知識概念や方法論を把握しているか
- 論理展開は理にかなっているか
- ひとりよがりでない、第三者に読ませることを意識した書き方ができているか
- 基本的な表現能力を備えているか
以上のような点がしっかりしていれば、研究対象者の人数や質問紙の項目数などの詳細は入学してから詰めることができますし、諸条件も変化しうるので、細部まで計画が煮詰まっていないからといってそれだけで直ちに不合格になることはありません。総じていえば、「答えを、あるいは答えの出し方を知っているか」よりは「適確な、深い問いかけをすることができる」ことの方が研究者の資質として先決要件です。(もちろん、専門家の目からみても完成度の高い研究構想が応募時点で既にできあがっていれば、それに越したことはありません。)
なお、研究/志望動機の説明方法については様々な文献が出ていますので、参考にされるとよいかと思います。
【問】研究計画書を書くほど具体的な計画がまとまっていないのですが、どうすればいいでしょうか?
【答】
やはり、大学院で何をやりたいのか、はっきりした目標をもってから応募することをお勧めします。そのためにはたとえば 日本言語文化学研究会から刊行されているレビュー論文集などを手がかりに、関連する本学修了生の修士論文や各種学術雑誌の掲載論文をたどるとともに、学会や研究会に頻繁に足を運んで見聞を広めることをお勧めします。 言語教育に関するメーリングリストに加入したりメールマガジンを講読するのも、情報網を広げる上で有効です。
筆記試験
【問】過去の入試問題を見ることはできますか?
【答】
はい、次のページを参照してください。
「過去の入試問題」
http://www.ao.ocha.ac.jp/past_test/index.html
【問】英語の試験は難しいのですか?/読解中心ですか?
【答】
大学院での研究のために最低限必要な英語力(主に読解力)を念頭においていますので特別むずかしいというわけではありませんが、外国語試験の得点が基準点に達しないため苦杯をなめる受験者が例年何人かいることも事実です。
【問】専門筆記試験はどういう形式ですか?どういう範囲から問題が出ますか?
【答】
専門筆記試験問題は大別して、
- 基礎知識を確認する短答式問題
- 深い理解を問う論述式問題
という、ふたつの部門からなります。
ここ数年の入試問題は、主に下記の分野から出題されています:
- 日本語教育学一般
- 談話分析、会話分析
- 異文化間コミュニケーション、異文化間教育
- 認知言語学
- 第二言語習得・教育
- バイリンガル教育、リテラシー教育
- 社会言語学
- 研究方法論
【問】専門試験に備えてどのような勉強をすればいいでしょうか?
【答】
まずは過去の入試問題を入手してください。その出題範囲や発問形式を念頭においた上で、各分野の定評ある概説書を熟読し、実際に答案を書いてみることが試験準備の正攻法です。
他専攻から受験される方はもちろんですが、例え学部時代に言語学や日本語教育を専攻した方でも出題範囲と様式にあわせてきちんと知識を整理しておかないと、専門試験で思わぬ失点を重ね不覚をとることがないとはいえません。そのためにも、充分な準備をしてから入学試験に臨むことを強くお勧めします。
口述(面接)試験
【問】口述試験ではどんなことを聞かれるのですか?想定質問集はありますか?
【答】
志望動機、研究興味、具体的な研究計画、日本語教育経験、卒業論文の内容など様々な角度から質問されます。質問は受験者によってそれぞれ異なるので、あらかじめ決まった質問リストを用意することはできません。
【問】口述試験が受けられるのは、筆記試験の一次審査を通過した人だけですか?
【答】
これまで一貫して、言語・専門の筆記と口述面接の双方の試験を全受験者に実施してきました。(これまでのところ、いわゆる「足きり」を行なったことはありません。)
【問】他大学の大学院に併願していることを正直に言うと不利になりますか?
【答】
そんなことはありません。併願先をお尋ねするのは興味関心の方向などを知るための参考情報を得たいからに過ぎません。他の合格要件を全て満たしている応募者を、他大学と併願しているという理由で不合格にすることはありません。
その他の受験前準備
【問】入学前に学会に出席することは、あとあと役にたつでしょうか?
【答】
はい、応募前に少なくとも一度(できれば何度か)は「学会」あるいは「研究会」と名のつく会合に出てみることをお勧めします。各種の学会、とりわけ日本語教育学会や第二言語習得研究会全国大会に参加することで、現在どのような研究者がどのような研究を進めているかを広く知ることができ、大学院での研究目的をはっきりさせて充実した研究計画書を書き上げる上でも、アカデミックな雰囲気に慣れる意味でも、貴重な体験となります。一方、第二言語習得研究会地区部会のような小規模の研究集会は、先輩や同じ志をもつ仲間とのネットワークを広げ情報を収集するのに格好の場です。また、お茶の水女子大学日本言語文化学研究会はいうまでもなく、日本語教育コースの研究内容を知る上で格好の機会です。
また、いったん大学院に入学すればさっそく各種のプロジェクト計画や研究成果をあちこちで発表することになりますから、アカデミックな発表や学術会議とはどういうものであるのかについて、はっきりしたイメージをあらかじめつかんでいる必要があります。日本語教育関係だけでなく、言語学・国語学・教育学・英語教育学・認知科学などの関連学会からも得られるものは多くあります。