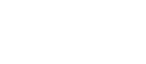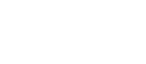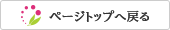- トップページ
- 大学院 人間文化創成科学研究科
- 博士後期課程
- 比較社会文化学専攻
- 表象芸術論領域
- 表象芸術論領域(博士後期課程 比較社会文化学専攻)
ページの本文です。
表象芸術論領域(博士後期課程 比較社会文化学専攻)
2025年4月3日更新
領域の概要
表象芸術論領域は、芸術・美術・服飾・文化論・舞踊・音楽・博物館学を中心に、文化表象・表現を多方面から専門的かつ横断的に追求する研究・教育を推し進め、とくに舞踊・音楽においては実践と理論の生産的融合を図りつつ、文化を人間理解・国際協力の強力な媒介として提言する人材を育成する。
領域担当教員と専門分野
| 担当教員 | 専門分野 |
|---|---|
| 小坂圭太 |
【ピアノ演奏】 ピアノという西欧近代特有の思考を体現するような楽器の演奏を通じ、「古典」の概念の検証を行うと同時に、ほとんど西欧化と同義語になっている今日の文化の「グローバル化」について考察する。 |
| 鈴木禎宏 |
【比較文化論】 「比較文化論」という方法論を構築する一方で、それを用いた文化的事象の解明を目指す。特に近代の日本のおかれた文化的状況を、ヨーロッパや他のアジア諸国との関係において考える。 |
|
中村美奈子 |
【民族舞踊学】 インドネシア(バリ島)の舞踊を中心に、日本を含むアジア地域の民族舞踊の調査・研究を主な領域としている。理論と実践の両面からアプローチを行い、舞踊記譜法などの分析手法を用いた舞踊の比較分析に関心を持っている。 |
| 難波知子 | 【日本服飾史】 明治時代以降の衣生活の変容を中心に、洋服の導入と和服の再編成、学校制服の成立と普及、服装文化の形成と継承などの問題を具体的事例を通して検討する。 |
| 井上登喜子 |
【音楽学】 音楽文化とその受容の諸相について、 |
| 新實五穂 |
【西洋服飾史】 19世紀フランスを中心に、ひとが服を身に着ける意味および服装における社会表象に関して分析し、人間の営為や時代の心性を明らかにすることを目指す。 |
| 福本まあや |
【舞踊表現論】 舞踊の教育的意義、社会的意義に関する既存の研究に整理・再検討を加え、そこから新たな研究課題と研究方法を創出し、人間と舞踊の関わりを複眼的に考察する。 |
| 土谷真紀 |
【日本美術史】 日本中世における絵画を中心に、作品の生成と享受の問題について物語、宗教といった視点から考察を行う。 |
| 岡千春 | 【臨床舞踊学】
舞踊と社会がつながる場を対象とし、そこでの舞踊の意義および課題について、具体的な事例の質的調査を通して、多角的に考察することを目指す。 |
| 浅井佑太 |
【音楽学】 二十世紀以降の作曲家の創作プロセスの研究を行っている。作曲的思考法・音楽語法と創作プロセスの関係性をスケッチ・自筆譜資料をもとに実証的に検証することを目指す。 |
| 内山尚子 | 【西洋美術史】 「芸術」を社会的文脈の中に位置付けて検討する立場から、20世紀のアメリカ合衆国を中心に、エスニック・マイノリティの芸術家による移動と「他者」表象に関心を持ち研究に取り組んでいる。 |