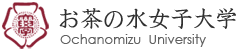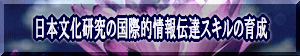2009年10月30日(金)、北京大学歴史学系教授の王小甫先生(中国古代史研究中心)をお招きして、公開講演会を開催しました。王先生は中国古代史、特に隋唐と吐蕃、大食の関係など東北アジア史がご専門で、『唐、吐蕃、大食政治関係史』(北京大学出版社、1992年)、『盛唐時代与東北亜政局』(編者、上海辞書出版社、2003年)などの著作がおありです。また、2006年から2009年まで行われた日中歴史共同研究のメンバーのお一人でもあります。
当日は、7世紀を中心とした東アジアの国際関係についてお話いただきました。隋唐帝国の成立と高句麗、百済、新羅といった朝鮮半島の国々との関係、新羅統一や渤海建国が東アジア世界に与えた影響などをふまえて、中国と日本の関係について、白村江戦を中心に語られました。隋唐側から見た視点で一貫している点が注目されます。 会の初めには、大学院教育イニシアティブの黄正建先生(中国社会科学院歴史研究所)講演会の時にもご挨拶いただいた学長羽入佐和子先生からお言葉をいただきました。会場には、本学から岸本美緒先生(中国明清史)、荻原千鶴先生(上代日本文学)も参加され、本学の院生・学生や、学外からも中国古代史の池田温先生、窪添慶文先生、気賀澤保規先生、高橋継男先生、金子修一先生、石見清裕先生、日本古代史の鈴木靖民先生、新川登亀男先生、榎本淳一先生、北京大学歴史学系の郭潤濤先生(中国明清史)、フランス国立高等研究院のシャルロッテ・フォン・ヴェアシュア先生(日本古代史)、他大学の中国古代史と日本古代史の若手研究者や院生の人たちも多数参加して、活発な討論が繰り広げられました。 日本史側から言うと、白村江戦は古代史における一大事なのですが、王先生は唐を中心とした歴史観から、当時唐にとってもっとも緊急な課題は高句麗との関係であり、白村江戦は遭遇戦であったという認識を示されました。また、白村江戦(白江口戦)に至った理由について、王先生は日本側の自負心と認識不足をあげられましたが、日本史の榎本淳一先生からは、当時唐も建国したばかりであり、唐と高句麗の関係からみても日本側は勝算をもっていたのではないかといった見解も披露され、議論は白熱しました。 古代の日中関係についての日本側の見方が中国にまだ十分伝えられていないこと、逆に中国側の見方も日本に十分には伝わっていないことが明らかになったと思います。日中歴史共同研究のような公式の場だけではなく、今回のような地道な相互交流によって、日中に共通した歴史認識を少しずつでも構築していく必要性があることを確認できたことが一番の成果だったと思います。 王先生は2009年8月から12月初めまで京都の龍谷大学に客員研究員として訪問中で、お忙しいなかを東京まで来ていただき、講演をしてくださったことに対して、心より感謝の意を表します。また、当日配布した資料の翻訳については、本学の和田英信先生(中国文学)が見てくださり、当日の通訳は本学の白蓮傑さん(本学博士後期課程)、高丹丹さん(本学研究留学生、北京大学博士課程)、補助は重田香澄さん(本学博士後期課程)が務めてくださいました。みなさまのご協力に心より御礼申し上げます。 【文責・古瀬 奈津子】
(2010/01/22up)     
   |
||||||||||||||||||||