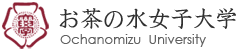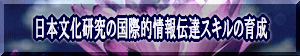現在でも日本の少女たちに愛読されているオルコット『若草物語』は、意外に早い時期から翻訳小説として日本に紹介されている。本講演では、明治39(1906)年に北田秋圃という若い女性による最初の翻訳『小婦人』をとりあげ、オリジナルとの比較を通して、明治翻訳小説としての特質や、秋圃がこの翻訳にこめたであろう、新しい女性像への期待などが明らかにされた。 『小婦人』では、舞台を日本に移していることから、明治期の翻訳にまま見られる不自然さ(現在の視点からすると滑稽な設定)が紹介され、会場の笑いを誘ったが、同時に、当時の日本の女子教育が良妻賢母主義へと一元化されつつあったなかで、本翻訳がその路線に添いつつも、新しい文化の紹介という観点から種々の魅力に富んだものであったことが論じられた。その一つは〈ホーム〉の概念であり、もう一つは現在でももっとも人気のある登場人物、ジョーの人物像についてである。とくに後者については、Tomboy Heroineジョーとお転婆ヒロイン孝代との比較から、両者の女性性の否定(拒絶)をめぐる差異が指摘された。 さらに、現在では無名の翻訳者・北田秋圃が、当時の文化背景のなかで許される限りの魅力的かつ挑戦的(というと言葉が強すぎるが)翻訳を試みていることが言及され、はるか明治の若い女性の志に、深く打たれるものがあった。 会場からは、『若草物語』をふくめた「少女小説」をめぐる日米比較の質疑等がなされ、興味深い議論がなされた。 【文責・菅 聡子】
(2009/08/10up)      

 
|
||||||||||||||||||||||