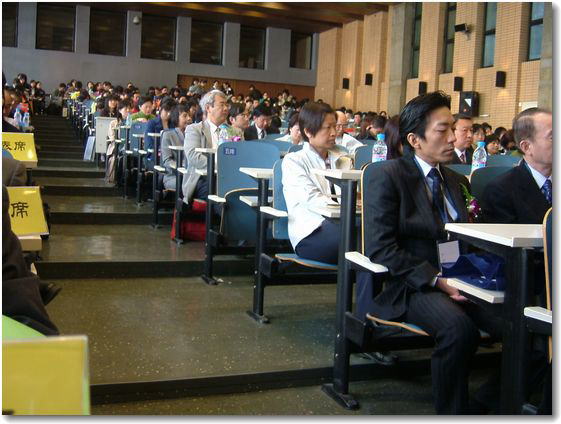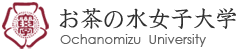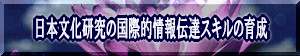日中韓3か国合同ジョイントゼミ
|
| 責任者 |
森山 新(比較日本学研究センター長) |
| 日時 |
2007年10月19日〜24日(5泊6日) |
| 場所 |
北京日本学研究センター(中国・北京市) |
| 主催 |
日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成プログラム、お茶の水女子大学比較日本学研究センター、北京日本学研究センター、同徳女子大学大学院日語日文学科 |
北京日本学研究センター主催の国際シンポジウム「21世紀東北アジアにおける日本研究」、及び日中韓3か国合同ジョイントゼミに参加するため、
10月19日から24日までの5泊6日間、本学からは教員4名、院生10名が訪中した。
これまで海外で行われるジョイントゼミは、日韓、日中といった2大学合同によるもので、日本語教育分野では2005年度に韓国・同徳女子大学、
2006年度に中国・北京日本学研究センターとの間で開催されてきた。
本年度は3か国が一同に会して行われることで、より多角的な 視野からの考察が可能となった。また時を同じくして、「21世紀東北アジアにおける日本研究」
という国際シンポジウムが行われ、187名にも及ぶ研究者が日本学各分野の研究を発表した。
このような場に参加することで、参加した院生たちは、自身の日本語教育・日本語学の分野のみならず、日本文学・文化・政治・経済など、
日本学全般の学際的な研究交流の場となったことも評価してよいであろう。
今回国際シンポジウム及び国際ジョイントゼミが日中韓3か国合同で行われたことは決して偶然ではなく、グローバル時代を迎え、日本学研究自体が、
国を超えた枠組みの中で多角的視野からなされるべきことを物語っていると言えるであろう。
◆開会式
9時から北京外国語大学にて国際シンポジウム「21世紀東北アジアにおける日本研究」に参加した。
主催の北京日本学研究センター、共催の日本国際交流基金、北京外国語大学、日本人間文化研究機構、後援の日本大使館などが挨拶を行った。
◆基調講演
午前中は以下のように3名による基調講演があった。
「東アジア地政文化は成り立つか−グローバルとローカルの間の東アジア論」濱下武志(龍谷大学) |
「江村北海と漢詩」W.J.ボート(オランダ国立ライデン大学) |
「21世紀の中国における日本政治経済研究の現状」易明(天津社会科学院) |
◆全体パネルディスカッション
午後は「文化の往還」と題しての全体パネルディスカッションが開催され、5名のパネラーによる発表がなされた。
「徳川吉宗の薬種国産化政策と近代的「知」の形成」笠谷和比古(国際日本文化研究センター) |
「東アジアにおける『剪灯新語』の受容」張龍妹(北京日本学研究センター) |
「『水滸画』の往還」大高洋司(国文学研究資料館) |
「歴史をこえた博物館資源の往還」野林厚志(国立民族学博物館) |
「中心・周辺・外郭という概念から見た東アジア」崔官(高麗大学) |

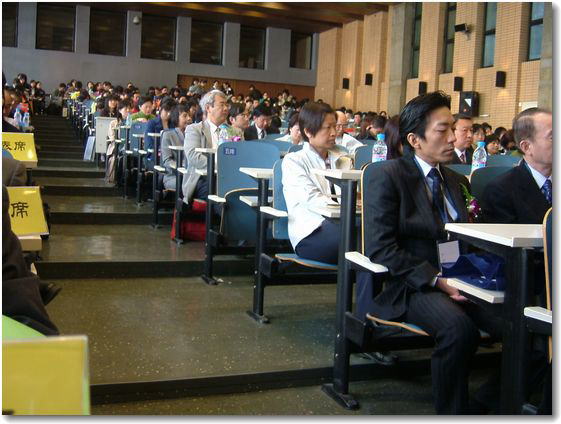 ◆歓迎レセプション
◆歓迎レセプション
夜は歓迎レセプションが近郊のホテルで開催された。
◆分野別パネルディスカッション
午前中は日本言語、日本語教育、日本文学、日本文化、日本政治、日本経済の6分野に分かれ、分野別パネルディスカッションが行われた。本学からは、
私(森山)が言語分野の「21世紀における日本語研究の新動向」に、岡崎、野々口両先生が日本語教育分野のパネルディスカッションに参加した。
| ◆日本言語分野パネルディスカッション |
| 主題 |
21世紀における日本語研究の新動向 |
| 司会 |
徐一平(北京日本学研究センター) |
| パネラー |
「中国における日本語研究について」修剛(天津外国語学院) |
| 「言語問題への対応を志向する日本語研究」相澤正夫(日本・国立国語研究所) |
| 「韓国の日本語研究について」全亨式(高麗大学) |
| 「日本語の習得・教育研究への認知言語学の応用可能性」森山新(お茶の水女子大学) |
| ◆日本語教育分野パネルディスカッション |
| 韓国編 |
「中級会話クラスにおけるプロジェクトワークの効果について」倉持香(ソウル女子大学) |
| 「実践的研究を活性化するための日本語教育学の構築」李徳奉(同徳女子大学) |
| 日本編 |
「学びの主体性を高める協働学習の意識化」野々口ちとせ(お茶の水女子大学) |
| 「学習者の主体性と教師の主導性」岡崎眸(お茶の水女子大学) |
| 中国編 |
「学習者の主体的な授業参加を導く教師の行動」冷麗敏(北京師範大学) |
| 「学習者の主体性を重んじた日本語教科書をめざして」林洪(北京師範大学)・曹大峰(北京日本学研究センター)・
篠崎摂子(国際交流基金日本語国際センター) |
| 「理系の考え方に学ぶ」陳俊森(華中科技大学) |
 ◆研究発表・ポスター発表
◆研究発表・ポスター発表
午後は研究発表やポスター発表が行われた。本学からは池田広子さんがポスター発表、楊峻さんが研究発表を行った。
「日本語教育実習における支援者のふり返りと考察」 池田広子(お茶の水女子大学) |
「精読授業にグループワークを取り入れる可能性」 楊峻(お茶の水女子大学) |
◆閉幕式
18:00より全体が一同に会し、それぞれの分野別報告が行われた。
中国・北京日本学研究センター、韓国・同徳女子大学校、そして本学の3大学による国際ジョイントゼミが開催された。北京日本学研究センターからは32名、
同徳女子大からは8名、そして本学からは9名、総勢50名もの院生が今回のジョイントゼミに参加した。指導教員としては、北京日本学研究センターの徐一平先生、
朱桂栄先生、同徳女子大から李徳奉先生、本学からは私(森山)とRFの池田先生が参加した。今回は参加者人数が多く、4つの分科会に分かれて分科会別の研究発表が行われ、
最後に全体会が行われた。
【第一部】全体会(3階多目的ホール)
| 8:15〜8:30 |
開会挨拶 森山新(お茶の水女子大学)、徐一平(北京日本学研究センター) |
| 8:30〜9:30 |
特別講演「広域日本語教育学構築のありかた」李徳奉(同徳女子大学) |
| 9:30〜9:35 |
記念撮影
|

 【第二部】分科会
【第二部】分科会
| ◆第1分科会 |
| 9:35〜10:20 |
(1)「中国におけるピア・レスポンスの可能性」
劉娜(お茶の水女子大学大学院) |
| 10:30〜11:15 |
(2)「交流型学習の現状分析と可能性−総合的日本語教育を目指して−」
西岡麻衣子(同徳女子大学大学院) |
| 11:15〜12:00 |
(3)「コミュニケーション能力養成の観点から見た日本語教科書のモデル会話― 中国の「総合日本語」教科書における相づちとフィラーの扱いを中心に―」
張金龍(北京日本学研究センター日本語・日本語教育コース) |
| 14:00〜14:45 |
(4)「精読授業にグループワークを取り入れる可能性」
楊峻(お茶の水女子大学大学院) |
| 14:45〜15:30 |
(5)「作文過程での内省を促す支援の効果」
高橋薫(お茶の水女子大学大学院) |
| 15:40〜16:25 |
(6)「韓国人の高齡者を対象にした日本語教育の方向」
張榮花(同徳女子大学大学院生) |
| 16:25〜16:30 |
まとめ
(発表者以外の参加者:曾艶、王剛、鄭嵐、李雪) |
| ◆第2分科会
|
| 9:35〜10:20 |
(1)「学習者の個別性に関する研究の必要性−心理類型論的な観点を中心に−」
申恩浄(お茶の水大学大学院研究生・同徳女子大学大学院) |
| 10:30〜11:15 |
(2)「中国の大学における日本語選択履修生のBELIEFSについて−日本語選択科目の改善を考える−」
李友敏(北京日本学研究センター) |
| 11:15〜12:00 |
(3)「学習リソースに対する学習者のビリーフについて」
柳川紘子(同徳女子大学大学院) |
| 14:00〜14:45 |
(4)「中国人日本語学習者における格助詞「に」「で」「を」についての習得研究」
冉愛玲(北京日本学研究センター) |
| 14:45〜15:30 |
(5)「第二言語習得において学習者の個人差が学習成果に与える影響」
向山陽子(お茶の水女子大学大学院) |
| 15:40〜16:25 |
(6)「中国の日本語教育における日本事情(日本文化・日本概況)教育の実態と課題―北京の大学を調査対象に」
張昭君(北京日本学研究センター) |
| 16:25〜16:30 |
まとめ
(発表者以外の参加者:楊雅琳、張舒鵬) |
| ◆第3分科会 |
| 9:35〜10:20 |
(1)「地域に暮らす定住外国人の日本語使用実態−ブラジル人の調査事例を通してー」
佐野香織(お茶の水女子大学大学院) |
| 10:30〜11:15 |
(2)「二言語環境にいる中国語を母語とする子どもの母語保持・育成に関わる要因―母語の認知面に注目して―」 穆紅(お茶の水女子大学大学院) |
| 11:15〜12:00 |
(3)「日本語会話(能力)における中級」
栗飯原美智(同徳女子大学大学院生 |
| 14:00〜14:45 |
(4)「複合辞の文法化に関する共時的考察−因果関係と逆接関係を表す複合接続助詞を中心に−」
夏瑞紅(北京日本学研究センター) |
| 14:45〜15:30 |
(5)「韓国における同じ漢字を使用する日本語動詞の習得状況に関する一考察」
金世恩(同徳女子大学大学院生) |
| 15:40〜16:25 |
(6)「自他両用法をもつ漢語サ変動詞について」
顧秋利(北京日本学研究センター) |
| 16:25〜16:30 |
まとめ
(発表者以外の参加者:森山京子、張卉、鄭新超、劉暁旭、沈燕菲、張慧、魏雲、馬傑萍) |
| ◆第4分科会 |
| 9:35〜10:20 |
(1)「中国人日本語学習者の話題転換の分析」
楊虹(お茶の水女子大学大学院) |
| 10:30〜11:15 |
(2)「テキストにおける「二人称代名詞」の使用の中日対照研究」
賀文静(北京日本学研究センター) |
| 11:15〜12:00 |
(3)「日本語学習者のための呼称と呼びかけの連関性研究」
崔祐寅(同徳女子大学大学院生) |
| 14:00〜14:45 |
(4)「色彩語の意味拡張メカニズムに関する研究−中国語の「赤」「紅」と日本語の「赤」「紅」を中心に−」
李静暁(北京日本学研究センター) |
| 14:45〜15:30 |
(5)「「[口尼](ne)」と「だろうか」について」
[ネ者]福海(北京日本学研究センター) |
| 15:40〜16:25 |
(6)「日本語における主観性の習得−言い切りの「た」を通して−」
石井佐智子(お茶の水女子大学大学院) |
| 16:25〜16:30 |
まとめ
(発表者以外の参加者:石立[王旬]、楼映青、田双燕、李煥雨、田暁黎、洪傑、王欣、芦茜、方[王路]) |
【第三部】総括(3階多目的ホール)分科会発表が終了後、各分科会の報告があり、最後に松岡先生の総括でジョイントゼミは締めくくられた。
| 16:30〜16:50 |
各グループの報告 (4グループ×5分) |
| 16:50〜17:00 |
総括&閉会挨拶 松岡榮志(北京日本学研究センター) |
| 17:20〜19:30 |
懇親会
|

24日、日本からの参加者が集まり、総括の場が持たれた。国を越えてのゼミを開催する場合、国家の間に存在する埋めるべき距離、克服すべき壁もそれだけ多くなる。
今回は教師主導ではなく学生主導の討論型のゼミが行われたが、このようなゼミ形態は国により、大学により定着の度合いが異なり、
参加者によって授業に臨む姿勢が異なってくる。また同じ日本語教育専攻といっても、言語、習得、教育など、研究テーマの焦点が国や大学、ゼミによってかなり異なってくる。
研究の方法論や指導法も異なる。さらに今回の場合、本学からの参加者は全員が博士後期課程の院生であったが、同徳では半々、
北京日本学研究センターでは全員が修士であったなど、研究の深化の度合いも異なっていた。こういった多様性はうまく活用すれば研究に幅が出てくるわけであり、
海外大学院とのジョイントゼミが行われる主たる理由もそこにある。しかしこれらの様々な違いを克服していくためには、事前にできるだけ多くの情報交換を行い、
それぞれが他の国からの参加者の状況を十分把握しておくこと、開催期間中にもできるだけ接触の時間を増やすことが重要であろう。また、
ゼミを今回のように学生主導で行うためには、準備の段階から学生主導で行っていくこともよいのではないかと思う。また、参加者にレベルの違いがある場合、
例えば博士論文の進捗に合わせての分科会設定を行うなど、レベルごとのグループ編成を行うことも有効であろうと思われる。
開催期間中、北京日本学研究センターの徐一平先生、曹大峰先生、同徳女子大学の李徳奉先生、そして本学の私(森山)との間で話し合いが持たれ、
今後もこのような3大学合同のジョイントゼミを継続したいとの意向が確認された。のみならず、テレビ会議システムなどを 利用し、日常的に合同ゼミを開催し、
交流ができればといった意見が出た。この点については本学でも推進中であることから、今後ぜひとも実現をしていきたいと思っている。
【文責 森山新】
(2007/11/30up)