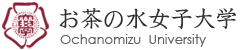
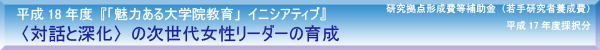
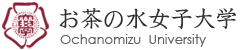 |
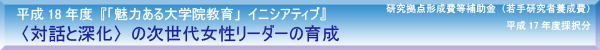 |
東京イタリア人女性協会・お茶の水女子大学・イタリア文化会館共催
|
||||||||
| 2006年11月23日から26日にかけて、イタリア文化会館(東
京・九段)にて、標記の会議が開催された。お茶の水女子大学としては、平成18年度『魅力ある大学院教育』イニシアティブ「<対話と深化>の次世代女性
リーダーの育成」事業の一環としておこなったものである。 この会議の目的は、日伊両国の女性をめぐる状況について多角的な比較検討をおこない、もってお互いの文化と社会をより深く認識するための第一歩とするこ とにある。 会議の発案は約1年半ほど前にさかのぼり、主催団体の間で交渉と打ち合わせを重ね、実現にいたったものである。 |
||||||||
| 一日め(23日)は、主催三団体の代表者による簡単な挨拶ののち、
職
場でのmobbingをテーマにしたF.コメンチーニ監督作品「ママは負けない(Mi piace
lavorare:直訳は「私は働くことが好きだ」)」(2004年)が上映され、次いで同作品についてのパネル・ディスカッションが行われた。会場を埋
め尽くした満員の聴衆に、渥美雅子弁護士が日本の職場で女性が直面している諸問題をユーモアたっぷりに解説し、ジェノヴァ大学のG.デ・シモーネ教授がこ
れに応じてイタリア労働法の背景を専門家として紹介した。また十文字学園女子大学の松本侑壬子教授は本作品を内外の映画史と関連づけて論じ、日本の映画人
たちが目指すべき方向性を示唆した。 |
||||||||
| 二日め(25日)は、冒頭に駐日イタリア大使、扇千景参議院議長な
ど
の挨拶があり、続けて東京イタリア人女性協会のA.チェネリーニ・ボーヴァ大使夫人と本学の羽入佐和子副学長が、それぞれイタリアと日本の女性を取り
巻く、とくに家族、教育、労働、文化などについての状況を統計的に概観し、会議全体への問題提起をおこなった。 第一部は小谷の司会のもとで、トリーノ大学のC.サラチェーノ教授、本学の石井クンツ昌子教授が、両国の女性の生活について詳細な家族社会学的分析をお こない、円より子参議院議員が歴史的概観をおこなった。政策面での課題と、個々人(とくに男性)の意識改革という、次元を異にする二つの問題があることが 確認された。 第二部では、本学の篠塚英子教授のコーディネートにより、両国を代表する女性デザイナーであるR.Missoni氏と森英恵氏がお互いの職業的生涯に つ いてスライドなどを交えて率直に語り合った。 昼食休憩を挟んで、午後の第三部では、両国の法律家4名(デ・シモーネ教授、浅倉むつ子早稲田大学教授、松浦千譽拓殖大学教授、榊原富士子弁護士) が、東京イタリア人女性協会のC.イオーリ弁護士の司会のもとで女性の労働や家族に関わる法および政策上の諸問題について専門的な知見を披瀝しながら議論 し、 活発な意見交換をおこなった。ここでは、とくに近年の両国における労働法の動向が焦点となった。 最後に、サラチェーノ教授と羽入副学長の司会で全パネリストによるラウンドテーブル形式の総括討議がおこなわれ、フロアからも意見が相次いだ。最終的 に、政策の次元と個々人の意識の問題を区別したうえで統合的に考えていくべきこと、われわれが討議している問題は民主主義の問題であることが確認された。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| 三日め(26日)は、本学の菅聡子助教授(当時)と東京イタリア人
女性協会のL.テスタヴェルデ氏の司会により、
両国を代表する作家である桐野夏生氏とE.ジャニーニ・ベロッティ氏との間で、とくに桐野氏の作品『OUT』をめぐって密度の高い対談がおこなわれた。最
後に桐野氏は、女性と男性の相互理解成立の可能性について述べ、この問いかけが、数日間にわたる会議全体を締めくくる発言となった。 |
||||||||
|
||||||||
| 小谷眞男(生活科学部
助教授)記 |