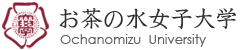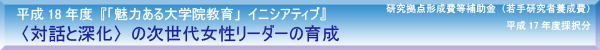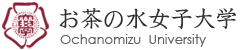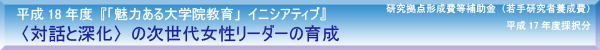|
ご挨拶
北京共同ゼミによせて
|
|
|
森山 新 |
|
|
|
|
|
このたびはこのように北京の地において第2回のジョイン
ト教育プログラムが実現できたことを心からうれしく思っております。私が北京日本学研究センターを初めて訪れたのは2002年に天津外大で日本語教育国際
研究討論会が行われた際で、最終日に本センターを訪れ、大学院の授業に参加しました。その後2003年に本学で第3回国際日本学シンポジウムを開催し、
「国際日本学との連携による総合的日本語教育」と題したパネルが行われ、そこに徐一平先生をお招きする予定でした。しかしSARSの影響でお呼びすること
が困難となり、シンポジウムの中国からのパネリストは急遽、当時来日中であった方にお願いすることになりました。しかし徐先生にはぜひ一度本学にお呼びし
たいという気持ちは変わらず、11月に特別招請講演会を別途設け、「中国における日本語教育と日本学との連携」という題目で講演をしていただきました。そ
して2005年には本学と北京外大との間で学術交流協定が締結されました。この10月には協定が結ばれて第一号の国費留学生が本学にいらっしゃる予定で
す。
次に今回のこのようなジョイント教育が行われた背景についてご紹介したいと思います。昨年度本学では魅力ある大学院教育イニシアティブ人社系プログラム
「<対話と深化>の次世代女性リーダーの育成」が文科省に採択され、国際性・学際性・将来性をキーワードとした様々な大学院教育プログラムが
行われるようになりました。海外の大学院との間にジョイント教育やジョイントシンポジウムを実施したり、海外調査研究に助成したりすることを通じて、大学
院生が在学中から積極的に海外に出、研究や教育に参画できるようにしています。日本語教育の分野での海外大学院とのジョイント教育では、昨年度は韓国の同
徳女子大学との間で「グローバル時代の日本語教育」をテーマに第1回のジョイント教育が実施され、グローバル時代に日本語教育は何ができるかが議論されま
した。ご存知の通り、かつて日本語教育は韓国などの植民地支配の一翼を担うという誤ったグローバル化を推し進めた過去を持っています。したがってもし日本
語教育が過去を反省し、今日のグローバル時代に何らかのよき貢献ができるとするならば、一度はこのテーマを取り上げておきたいとの考えから、かつての被害
国韓国の地において、この問題を取り扱いました。そして今回の第2回は中国で行おうと思い、徐先生にご相談したところ快く引き受けてくださり、実現の運び
となりました。
日本語教育というととかく日本が本拠地であると考えがちですが、私は必ずしもそうであるとは考えていません。なぜなら日本国内以上に日本語学習者を有
し、日本語教育に日夜苦労しているのは、韓国や中国などの海外であるためです。その意味から、日本の学生にとっては海外の地において行われる日本語研究や
日本語教育研究を自身の目で見ることは大いに意味のあることですし、同時に海外で教育・研究に携わる皆様にもお役に立てると思っています。どうか短い期間
ですが、お互いがともに学ぶ有意義なひと時となりますよう心からお祈りいたします。
|
|
|

|
|
|
|
|
|